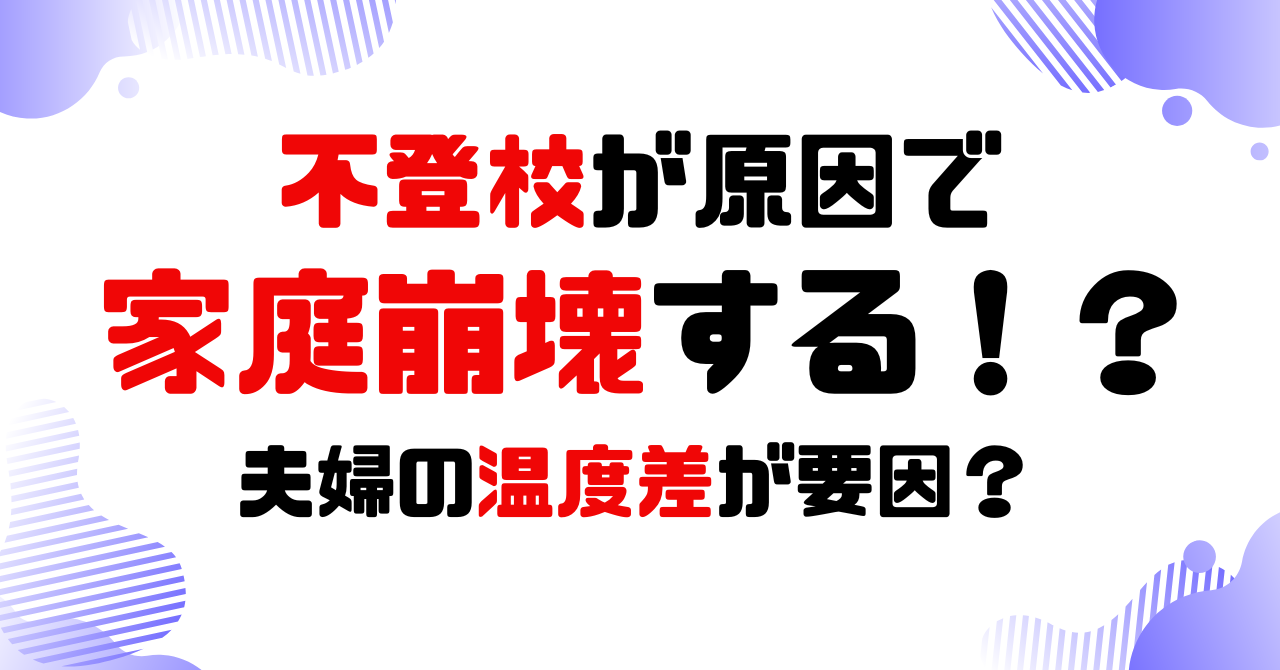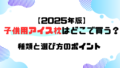子どもの不登校は、多くのご家庭にとって本当に大きな課題ですよね。
ある日、突然学校に行かなくなると、「これからどうすればいいんだろう…」と戸惑ってしまうこと、よくわかります。
そして、それがきっかけで、夫婦の間で意見がすれ違うこともあるかもしれません。
この記事では、不登校がご家庭にどんな影響を与えるのか、特に離婚の危機や夫婦の間の「温度差」が、どのように家族に影響するのかを、私の実体験を交えながらお話しします。
うちの子も6年間不登校なので、私が実際に感じてきたリアルな体験談が、今悩んでいらっしゃる方のヒントになるかと思います。
不登校は家庭崩壊につながる?

子どもが不登校になると、ご家庭の状況はガラッと変わります。
これまでの毎日が一変して、親には精神的にも経済的にも新しい負担がのしかかってきます。
不登校は「ただ学校に行かないだけ」と思われがちですが、実は家庭に与える影響は本当に幅広いんです。
まず一番に、親は子どもの将来のこと、教育費のこと、周りの目が気になったり、心理的なストレスがどんどん大きくなります。
教育費に関しては、「もし学校に行けていたら受けられたはずの教育」が難しくなる分、塾や通信教育などの費用が重くのしかかってくることも。

親が教えてあげようと思っても、一緒に勉強するのは大きな負担になりますよね。
それに、高校以降の学校選びの選択肢が狭まって、高校からの学費が高くなる可能性もあります。
こんな状況だと、夫婦の会話が不登校の話題ばかりになって、他の生活面でのコミュニケーションが減ってしまうこともあります。
家庭が崩壊してしまう心理的な理由としては、親が抱えるストレスが溜まって、夫婦間の会話が減ったり、ケンカが増えたりすることもあるんです。
子どものことを真剣に考えれば考えるほど、その負担は重くなりますよね。
特に、不登校が原因で家庭が不安定になるケースでは、不登校への対応について夫婦の間で意見が対立してしまうことも考えられます。
例えば、一方の親は「何としても学校に戻すべきだ」と考える一方で、もう一方の親は「子どもの心の安定が一番大事」と考えるなど、何を優先するかで気持ちがすれ違いが生じることも…。
もし、こうした夫婦間の認識のずれが解消されないままだと、お互いの関係がギクシャクして、家庭の雰囲気が悪くなってしまうことにつながります。そして、不登校の責任を相手に押し付け合ってしまうようなことさえ、起こりえます。
我が家の場合、不登校になってからは、母である私が「休んでいても家で勉強するなら、まあいいんじゃないかな」という意見でした。
でも、夫は「やっぱり学校には行くべきだ!」と、よく意見がぶつかることがありました。

私自身も最初は「学校へ行くべき」と思っていましたが、毎日子どもの様子を間近で見ているうちに、無理やり行かせて苦しめるのは違う、という考えに変わっていったんです。でも、仕事でなかなか子どもとじっくり関われない夫には、それが理解できずにいました。
こんなふうに意見が対立し続けると、夫婦の間に少しずつ亀裂が入っていくのを肌で感じました。
親の関わり方の違いが引き起こす離婚の危機

不登校の問題に対する親の関わり方って、性別によって傾向が見られることがあります。
この親の役割の違いが、夫婦間の「温度差」、つまり考え方のずれを生んで、結果的に離婚の危機へと発展してしまうこともあるんです。
父親から見た不登校の課題としては、「仕事の責任」と「家庭の問題への関わり」の間で葛藤を抱えるケースがよくあります。
「世間体」や「子どもの将来」への不安から、早く問題を解決しようと焦るあまり、子どもや奥さんに対してつい厳しい態度を取ってしまうこともあるようです。
また、仕事で昼間の子どもの様子を直接知る機会が少ないので、問題の深刻さに対する認識が、母親と違う場合もあります。
一方、母親が抱える悩みは、子どもの不登校に毎日向き合うことから、より深刻な精神的な負担を抱えやすい傾向があります。
子どもの状態に対する強い責任感から、「私のせいだ…」と自分を追い詰めてしまったり、孤立感が募りやすかったりして、心も体も疲れ果ててしまうケースも少なくありません。

実際に、うちの子の性格は私に似ているので、「私に似てしまったからかな…」とか、「あの時もう少し自己肯定感を高める接し方をしていればよかった…」なんて、過去の後悔がどっと押し寄せてくることがあります。
それに、他の子どもたちが元気に学校へ向かっている姿を見るだけでも、胸が締め付けられるほど辛くなることも。「不登校」という事実を受け入れるだけでも、本当に大変なんです。
こんな状況の中で、もし夫からの理解が足りないと感じたら、夫婦間の信頼関係に亀裂が入ってしまいますよね。その結果、離婚の可能性が高まってしまうこともあります。
実際に、「夫が不登校の原因を私だけのせいだと思っているように感じて、夫婦関係が悪化しました」といった声も聞こえてきます。この夫婦間の「温度差」は、家庭が壊れてしまうのを防ぐ上で、とても大切な課題なんです。
離婚の危機を乗り越えるには?
家族の絆を守るためには、夫婦がお互いの立場や気持ちを理解しようと努力して、同じ認識を持つことが何よりも大切です。
例えば、父親がもっと積極的に家庭の問題に関わって、母親の精神的な負担を少しでも減らすような行動を取ることで、夫婦関係はきっと改善に向かうはずです。
それから、お互いの気持ちをまずは受け止めて、「これからどうすればいいのか」をじっくり話し合うことがすごく重要になります。そして、つい忘れがちですが、日頃から感謝の言葉を伝え合うことも、夫婦関係を円滑にする上でとても大切です。
父親の中には、「仕事さえしていれば家族の責任は果たしている」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、子どもの人生に関わることは、父親の仕事でもあります。もちろん、忙しいのはよくわかります。でも、夫婦で協力し合わないと、心の溝は深まるばかりです。
不登校に直面する日常とは
不登校のご家庭が日々抱える課題には、子どもの生活リズムの乱れ、勉強の進み具合、将来への不安、そして何よりも、お子さん自身の心の状態への配慮が挙げられます。
親は、学校との連携、学校以外の勉強方法、子どもの安心できる居場所探しなど、毎日たくさんの課題と向き合わなければなりません。
最近は、デイサービスなどで子どもを受け入れてくれる居場所も少しは探しやすくなりましたが、そもそも子ども自身が「外の世界と関わってみたい!」と一歩踏み出さない限り、なかなか難しいことですよね。
そして、不登校が原因で離婚に至るケースがあるのは、不登校が夫婦関係にどれほど深刻な影響を与えるかを示しています。
不登校問題への対応方針の違いや、長期間にわたる精神的なストレスが原因で、最終的に離婚という選択をする夫婦もいらっしゃいます。これは、不登校が「家庭の安定を大きく揺るがしかねない要因」となり得ることを物語っています。
家庭崩壊を防ぐためのヒント
不登校による家庭崩壊を防ぎ、家族みんなで前向きな道を歩むためには、具体的な対策がとても重要です。
まず、不登校の子どもへの理解と、適切な関わり方が最優先されます。
子どもが不登校になる背景は様々なので、その理由を理解し、子どもの気持ちに寄り添う姿勢が何よりも求められます。
無理やり学校に行かせようとするのは避け、ご家庭が子どもにとって安全で安心できる場所であることを、しっかりと確立することが大切です。
次に、家族みんなで協力することも重要です。不登校は、子ども一人の問題ではなく、家族みんなで取り組むべき課題として捉えるべきなんです!
夫婦間はもちろん、兄弟も含めて家族全員で話し合い、それぞれの役割を理解し合うことが、家族の絆を強くします。
特に、夫婦間の「温度差」をなくすために、積極的に話し合いの時間を持つことがとても大切です。
お互いの意見や感情を否定せずに、落ち着いて話し合い、夫婦で共通の理解と、これからの方向性を見つけることが重要になります。
さらに、専門家のアドバイスを活用することも有効です。
スクールカウンセラー、教育相談機関、児童精神科医など、不登校の問題に詳しい機関から話を聞き、客観的なアドバイスやサポートを受けることで、「不登校って一体どんな状態なんだろう?」という共通の認識を夫婦で持てるため、これからの方向性がまとまりやすくなります。
母親一人だけでアドバイスを聞いても、父親が不登校に理解がなければ、それを活かすことができません。できることなら、夫婦一緒に専門家のアドバイスを受けるのが良いと私は思います。
家庭崩壊から立ち直るために
もし今、ご家庭が深刻な状況だと感じていらっしゃる場合でも、家族の絆を取り戻す方法は必ずあります。
家族の絆を再生するための手順としては、まず夫婦間の問題に真正面から向き合い、話し合いを通じて信頼関係をもう一度築き直すことが挙げられます。
その上で、子どもとの関係を見つめ直し、子どものペースを尊重しながら、少しずつ前向きな変化を促していくことが大切です。
家族の関係が壊れてしまうのは簡単なことですが、このような困難に直面した時にそれを乗り越えられたら、家族の絆はきっと以前よりもずっと強くなるはずです。
まとめ
わが子が不登校になると、「どうしよう…」「不安でたまらない…」といった気持ちがどっと押し寄せてきて、どう対応すればいいのか途方に暮れてしまうこともありますよね。片方の親だけでは、問題を解決するのは本当に難しいことです。そして、夫婦はそれぞれ別の人間ですから、当然同じ方向を向くのも簡単ではありません。
でも、だからこそ、この困難を夫婦で力を合わせて乗り越えた時に、家族の絆がぐっと深まると私は信じています。
「甘えだ」「だらしない」といった言葉だけで片付けてしまうのは簡単ですが、それでは、子どもが大人になった時に親のことを恨んでしまうだけかもしれません。
また、子どもにとっても、家族みんなが味方になって支えてくれることは、何よりの心の支えとなることでしょう。勉強ができなくても、こうした家族の絆の方が、生きていく上で確実に重要だと私は思います。
うちの息子も、不登校歴6年目に突入しました。
一時期は学校へ行けたこともあり、その時は「やっと解放された!」と思ったこともありましたが、不登校に戻ってしまい、再び長く暗いトンネルに引き戻されたような感覚です。
それでも、この子がいなければ、一生「不登校は甘えだ!」という考えの人間だったと思うと、新しい考え方を与えてもらえた貴重な経験だと、今では思えるようになってきました。
不登校の子どもは、現在約34万6千人います。
参照:文部科学省/令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について
いつわが子が不登校になるか、明日は我が身です。このブログ記事が、不登校とその関連する家庭の問題に直面している皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。