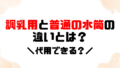「先生やお父さんには癇癪起こさないのに、母親にだけ何で癇癪起こすの…?」
癇癪(かんしゃく)持ちの子供のことで、このように思ったことはありませんか?
毎日一緒にいる母親だからこそ、ぶつけられる。頭ではわかっていても、心がついていかない日もありますよね。
小学生になると、行動範囲が広がり自我が芽生え、親への甘えや反発心が入り混じる複雑な時期になります。
この記事では、母親にだけ癇癪を起こす小学生の心理と対処法を解説します。
母親にだけ癇癪を起こすのはなぜ?実体験から見えた心理
私の娘も、4年前から母親の私にだけ癇癪を起します。今は少し落ち着いていますが、当時は大変でした。
児童会館から帰るたびに叩かれ蹴られ、家に帰ってからも暴れ、泣き叫ぶ日々。ひどい時は2時間×3回ほど暴れました。馬乗りになって押さえつけても、噛みつかれ、頭突きによって口の中を切ることもありました。
私の身体は毎日青アザだらけで、常に追い詰められていました。しかし、旦那が帰宅するとピタッと泣き止むので、癇癪の大変さを理解してもらえませんでした。
母親は子どもにとって「一番安心できる存在」です。そのため、感情をぶつけやすく、癇癪の対象になってしまいます。
医師の判断で、一時的に気持ちを落ち着ける薬が処方される場合もあります。
薬は一時的なサポートですが、親子の負担を軽減する手段の一つです。
小学生が癇癪を起こす原因
癇癪の原因は子どもによって異なります。私の経験を踏まえると、主に以下の要因があります。
- 感情コントロールや語彙力が未熟で、気持ちをうまく伝えられない
- 家庭や学校のストレス
- 親に甘えたい、試したい心理
- 生まれつきの性格や発達障害の可能性
うちの場合、朝から学校、学校後は児童会館、その後宿題、夕食・お風呂、時間が余らなければゲームもできないという、スローペースの娘にはストレスのたまるスケジュールが大きな原因でした。
外では良い子、家でだけ癇癪が起こる理由
家は子どもにとって最も安心できる場所です。
外では良い子にしていても、家ではリラックスして甘えたくなる反動が癇癪として現れます。
また、母親にどれだけ愛されているか確認したい心理も関係します。感情のコントロールが未熟なため、些細なことで怒りを爆発させてしまうこともあります。
癇癪とワガママの違い
癇癪とワガママは似ていますが、意味が違います。
ワガママ:自分の要求を通すことが目的で、感情爆発の程度は穏やか。
癇癪:感情をコントロールできず、泣き叫ぶ・暴れる・叩く・蹴る・噛むなどの行動を伴う。本人も止めたくても止められない。
癇癪の症状と学校・家庭への影響
癇癪は次のような症状が見られます。
- 泣き叫ぶ、物を投げる、暴れる、噛む、叩く、蹴る、暴言
- 学校や友人関係に影響することもある
- ストレスの悪循環で、さらに癇癪が増える
うちの娘は家庭でのみ激しい癇癪を起こしましたが、子どもによっては学校でも起こることがあります。
癇癪を起こした時の対処法
1. 見守る
- 怪我をしそうなものを片付け、安全な場所へ避難
- 話しかけず、まずは落ち着くのを待ちましょう
- 暴力的な場合は自分の体を守りつつ、刺激しないようにしましょう(刺激すると、さらに悪化することがあります)
癇癪中は何も聞こえないと思うので、話が聞ける状態になってから「悲しかったね」「悔しかったね」と寄り添う言葉をかけます。
2. 感情コントロールの練習
- 専門機関で少しずつ練習
- 心理セラピーを受ける
- 必要に応じて病院で薬を処方してもらうと気持ちが落ち着きやすい場合もあります
3. コミュニケーションを増やす
- 機嫌の良い時間に好きなことを一緒に体験
- お菓子作りやゲームなど、楽しめる活動を提案
コミュニケーションが不足していると、将来不登校につながることもあります。実体験から感じたことですので、下記記事を参考にしてください。
>>不登校の理由がわからないときに親ができること|6年間の体験+最新データで見える現実
家庭でできるサポート
- 父親も愛情表現をわかりやすく伝える
- 家族全体で協力し、信頼関係を積み重ねる
- 学校や児童相談所、病院など周囲の支援も活用
自宅学習で癇癪を減らす工夫
自宅で学習習慣を整えるツールも有効です。うちの娘の場合、学校で支給されるタブレットを使った学習では、教科書より集中して取り組める様子が見られました。
また、紙教材でも、計画を立てて少しずつ進めることで、子どもが自分のペースで学習でき、癇癪が起きる前に落ち着いて勉強に取り組めることがあります。
こうした経験から、タブレット教材や紙教材をうまく組み合わせることで、学習をスムーズに進めやすく、親子のストレスを軽減できる可能性があります。
自宅学習用としては、ゲーム感覚で進められるタブレット教材「スマイルゼミ」も一つの選択肢です。
\資料請求はこちらから/
◆スマイルゼミ◆タブレットで学ぶ 【小学生向け通信教育】が誕生!癇癪を減らすための環境づくり
落ち着けるスペースを用意し、騒音や刺激を減らすことで、子どもが安心して過ごせます。
さらに、ホワイトボードなどに一日のスケジュールを書き、子どもが見て分かりやすくすることで落ち着くこともあります。
壁紙に貼れるタイプのホワイトボードなら、お絵描きにも使えて便利です。
まとめ
母親にだけ癇癪を起こす小学生の心理は、安心できる存在だからこそ感情をぶつけやすいということが大きな要因です。
- 原因を理解し、環境を整える
- 見守る・寄り添う・コミュニケーションを増やす
- 家族全体で協力し、必要に応じて専門家や病院に相談する
- 学習は紙教材・タブレット教材を活用し、スムーズに進める
実体験からも、癇癪は親にとって大変ですが、子どもも苦しんでいることを忘れず、少しずつ対応していくことが大切です。
癇癪はすぐに治るものではありません。
それでも、親子の信頼関係を少しずつ築いていくことで、確実に落ち着く日が増えていきます。
「治ったかな?」と思ってもまた数カ月後に再発することもあります。日々、子どもとコミュニケーションを取り乗り越えていきましょう。