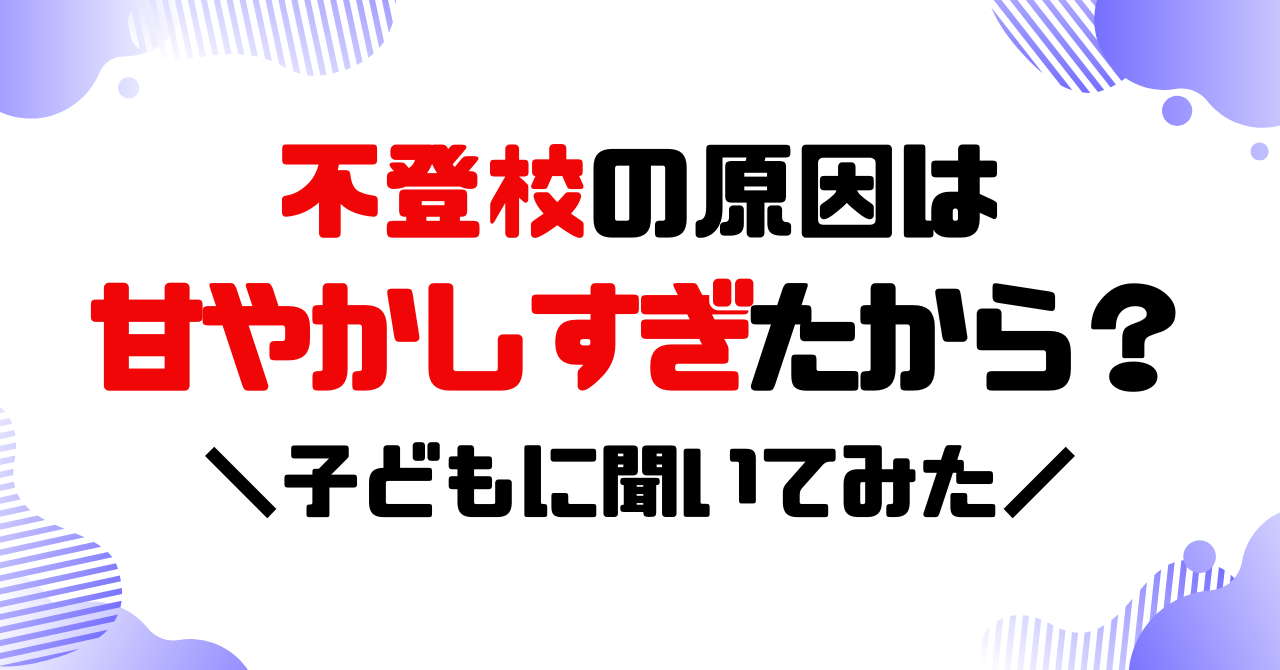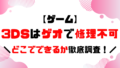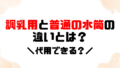最近、不登校の子どもが増え、文部科学省の調査でも過去最多を更新しています。(参照:文部科学省、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)
家庭での関わり方が、子どもの学校生活に大きく影響することは間違いありません。
「甘やかしすぎたのでは?」「もっと厳しくすべきだった?」ーーそんな迷いを抱く方も少なくありません。
この記事では、不登校の背景にある原因から、「甘やかし」と「過保護」の客観的な違い、発達障害との関連、そして登校を促す具体的なサポート方法を、約6年間の不登校中息子の体験談とともに、徹底的に解説します。
不登校は甘えなのか?原因を知ることが第一歩
不登校は、親から見ると「怠け」「甘え」と見えてしまうかもしれませんが、多くの場合、子どもにとっては「心がこれ以上耐えられない」というSOSサインです。
不登校の背景には、一つではない複雑な原因が潜んでいます。
- 精神的・身体的な問題: 発達障害(ASD/ADHD)、うつ病、不安障害、適応障害、朝の体調不良(起立性調節障害など)。
- 家庭環境の影響: 家族間の不和、親からの過度な期待、厳しすぎるしつけ、あるいは生活リズムの乱れ。
- 学校での困難: いじめ、教員との関係、友人関係のトラブル、集団生活や校則への強いストレス。

息子の場合、外に出ると常に周囲の目を気にして緊張し、帰宅後はその疲労とストレスからゲームに没頭していました。これは、学校生活の精神的負荷が許容範囲を超えていたんだと思います。
甘やかしと過保護の違いとは?親が知っておくべき線引き
不登校の原因を考える上で、親自身の行動を客観視するためにも、「甘やかし」と「過保護」の正しい区別を知ることはとても大事です。
どちらも子どもの成長を邪魔する可能性がありますが、それぞれ特徴があります。
甘やかしとは?メリットとデメリット
「甘やかし」は、子どもの欲求を無条件に受け入れたり、叱るべき場面でも叱らずに許容する行動です。
「甘えさせる」とは違い、なんでも親が受け入れてしまうことです。
| 甘やかしのメリット | 甘やかしのデメリット |
| 適切な愛情があれば自己肯定感の土台になる | 自己中心的になり、他者への配慮が欠ける |
| 安心感から感情が安定しやすい | 忍耐力や我慢が苦手になる |
| 問題解決を他人に頼りがちになる |
メリットもありますが、甘やかしすぎるとデメリットの方が大きくなります。
なぜなら、子どもが「世の中は自分の思いどおりになる」と誤解し、困難に直面したときに立ち止まってしまうからです。
大切なのは、「甘やかす」ことではなく「甘えさせる」こと。
「甘やかす」は親の都合で欲求を満たすことですが、「甘えさせる」は子どもが安心して気持ちを出せるように受け止めることです。
叱るべきときはきちんと叱り、受け止めるときはしっかり抱きしめる。そのバランスこそが、子どもの心を安定させ、自立につながります。
過保護とは?子どもの自立を妨げる行動
一方過保護は、「子どもが困らないように」「失敗しないように」と、親が先回りして手を出しすぎる行動です。
これは愛情の裏返しである場合が多いですが、子どもの成長に大きな影響を与えます。
- 具体的な過保護の例:
- 自分でできる年齢なのに、毎朝親が持ち物や洋服をすべて準備している。
- 課題や宿題を子どもと一緒にやりすぎたり、答えを教えたりしてしまう。
- 子どもが悩んでいるときに、考えさせる間もなく親がアドバイスや答えを出してしまう。
過保護は結果として、子どもから挑戦や失敗の機会を奪い、自分で解決する力やストレス耐性を身につける機会を失わせてしまいます。
【体験談】厳しくしているつもりが「過保護」に?
私は息子に対し「厳しくしつけをしているつもり」でした。しかし、夫から「過保護すぎ」と指摘されたことがあります。
なぜなら、仕事と幼い妹の世話に追われる日々の中で、「早く片付けてしまいたい」「早く休みたい」という気持ちから、子どもが困っているときに思考する間もなく先回りして手を出すことが多くなっていました。
また、何か困って悩んでいるときには、一緒に考えてあげる余裕もなく、結論だけを伝えてしまうことが多くありました。

親の感覚と周囲の評価は必ずしも一致しません。
わが子を守りたいという気持ちが、いつの間にか子どもの自立の機会を奪う「過保護」につながっていないか、客観視することがとても大事だと、今になって感じています。
発達障害と不登校の関係とは?
発達障害(特にASDやADHD)を持つ子どもは、学校生活での困難が不登校に直結しやすい傾向があります。
- コミュニケーションや対人関係の困難: 周囲から理解されにくく、自己肯定感を低下させる。
- 強いこだわり・感覚過敏: 集団のルールや、教室の騒音、光、匂いなどに耐えられず疲弊する。
- 特性による失敗体験の積み重ね: 忘れ物が多い、授業についていけないなどの失敗から自信を失う。
対応策は?
- 医療機関で専門的な診断を受ける: 原因が明確になることで、親子の不安が軽減します。
- 支援級や通級指導教室の検討: 子どもの特性に合わせた学びの場を検討し、学校と連携します。
学年が上がると、本人が支援級を嫌がるケースも増えるため、専門家と相談の上、早めの判断が後悔を減らすことにつながります。
不登校の子どもをサポートする方法
子どもが心のエネルギーを充電し、再び学校へ向かう気持ちを取り戻すために、親が家庭でできることはさまざまあります。
家庭でできる具体的なサポートは?
| サポート内容 | 具体的な行動例 |
| 安全で居心地の良い環境づくり | 学校へ行かないことを批判や非難をせず、「休んでも大丈夫だよ」と伝えて安心させる。 |
| 生活リズムの安定 | 起床・就寝時間だけでも整え、活動のエネルギーを蓄える。 |
| 小さな目標設定 | 「学校の前まで行ってみる」「次の授業だけ出てみる」など、子ども自身が決められる達成しやすいスモールステップを設定する。 |
| 親子でコミュニケーションをとる | 「なぜ?」と問い詰めず、子どもの好きなゲームや動画の話題で目線を合わせて会話する。 |
子ども自身の意識改革を促す接し方
- 自己肯定感を育てる: 毎日小さなことを褒め、「あなたは大切な存在だ」というメッセージを伝え続けます。兄弟や他人と比較せず、「あなたのペースでいい」と肯定する姿勢が大切です。
- 失敗を経験させる: 宿題や持ち物の管理など、発達段階に応じて自分で責任を持たせ、忘れたら自分で先生に説明させるといった小さな失敗と自力での解決を経験させます。
- 強みを認識させる: 読書、ゲーム、絵など、学校以外の場所で見せる得意なことや好きなことを徹底的に褒め、「あなたはできる」という自信を育みます。

好きなことを褒めてあげるのは、中間目標なので、ここで褒めすぎると「他のことをやらない」ということにも繋がります。(私の息子はこのパターン)
褒めることで親子関係を円滑にし、社会生活につなげるのが目標なので、うまく調整しましょう。
不登校克服には時間が必要
不登校の克服には、焦りは禁物です。息子の場合、約6年間不登校が続いており、いまだに継続中です。行けたりする時期もありますが、それも数カ月で終わってしまったり…まだまだ不安定です。
親としては焦らず長期的に見守る姿勢が最も大切だと痛感しています。
息子の不登校の原因と克服のきっかけとは?
ある時、息子に不登校の原因を聞くと、「体調の弱さ」「過去のトラウマ」、そして「母の厳しい躾」が原因だと話してくれました。
不登校になってからは、気持ちに寄り添うに意識してきましたが、子どもからすると「何も変わってない」ように見えるとも言われました。
この経験から、登校再開は親の努力や対応だけで決まるものではなく、子どもの心のエネルギーが満たされる「タイミング」に左右されることが大きいと感じました。
ちなみに妹にも同じように接していますが、妹は学校が大好きです。
同じ親でも子どもによって反応が違うため、親のせいだけとは言い切れません。
もし今、自分を責めている方がいたら、どうか悲観しないでください。
長期視点でサポートしよう
「学校に行かせたい」という親の強い気持ちは、かえって子どもへの大きなプレッシャーとなります。不登校の期間は、学校で消耗したエネルギーの充電期間であり、親自身が子どものペースを尊重する「成長の時間」でもあります。
- 学校以外の学びを積極的に活用: 興味のあることを学ばせるため、塾、フリースクール、オンライン教材などを活用し、学びへの意欲を途切れさせないようにサポートしましょう。
- 子どもの才能を信じる: 学校という枠組みにとらわれず、子どもの持つ才能や個性を伸ばすことに注力し、未来の選択肢を広げてあげましょう。何か好きなことを見つけるチャンスです!
まとめ:不登校は親子の成長に必要な時間
不登校は、親の「甘やかし」や「過保護」だけで起こるものではありません。それは、子どもが今の環境に限界を感じた結果であり、親子の関係性や生き方を見直すための貴重な機会でもあります。
親がまずすべきことは、自分を責めるのをやめ、子どもに寄り添い「安全な場所(家)」を提供することです。
子どもはいずれ、自ら次の一歩を踏み出す力を取り戻し始めるはずです。長期的な視点で、わが子の回復と成長を信じて見守り続けましょう。
関連記事
▶不登校が原因で家庭崩壊する?離婚危機は夫婦の温度差が要因?
▶不登校はずるい?運動会や修学旅行などの行事にだけ来るのはナゼ?