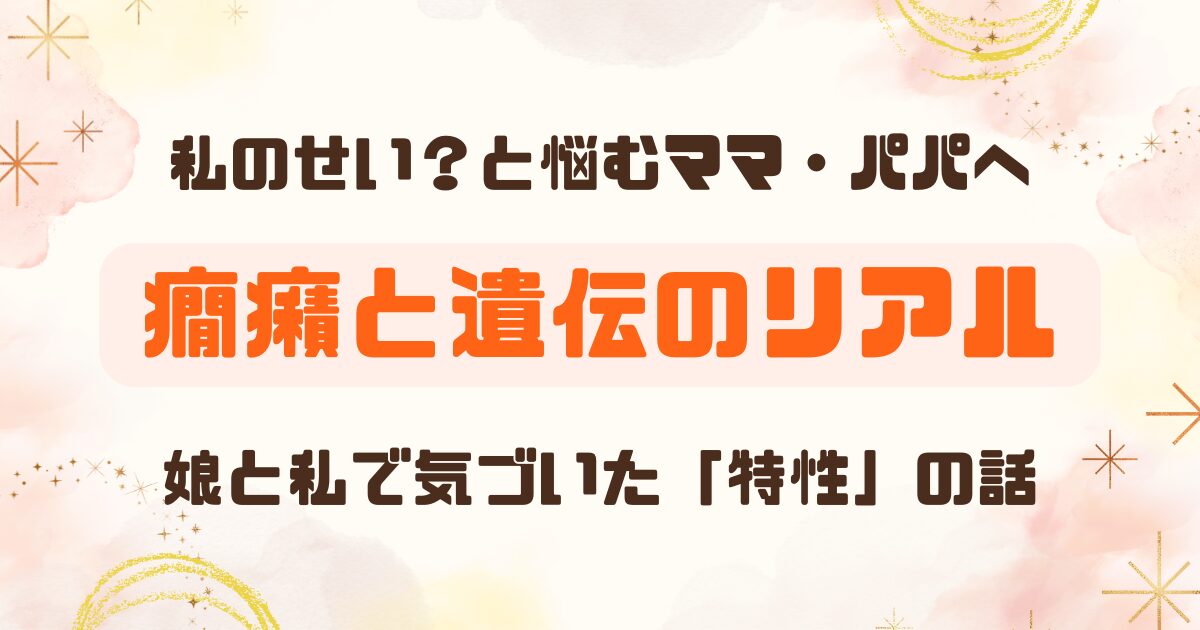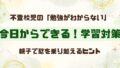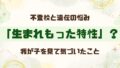子育てをしていると、予期せぬ壁にぶつかることがあります。私にとって、その一つが娘の癇癪でした。
年中ごろから突然癇癪を起こすようになり、保育園にお迎えに行くと泣き叫び叩いたり蹴ったりしました。
そんな娘の姿を見て、「どうしてなんだろう…」と悩む日々を送っていました。
娘の癇癪と向き合う中で、ふと頭をよぎったのが「もしかして、これって生まれつきの特性が関係してるのかな?」という疑問です。
今回は、娘の癇癪を通して私自身が感じたことを中心に、癇癪と生まれ持った特性の可能性を考えてみました。そして私たち家族がどのように向き合ってきたかについてお話したいと思います。
娘の癇癪の様子
まず、娘の癇癪がどのようなものだったかをお伝えさせてください。
行動を切り替えるときにスイッチが入る
例えば、「保育園から帰る」「お出かけの準備をする」など、場面の切り替えをするときに発動することが殆どです。
保育園や学校への準備やお迎えの際は、ほぼ毎日癇癪を起こしていました。
感情の爆発が激しい
ただ泣き叫ぶだけでなく、私の事を「蹴る」「叩く」「噛み付く」「引っ掻く」などありとあらゆる手段で攻撃することが多くありました。
なかなか落ち着かない
一度癇癪が始まると、こちらの声が届きません。大きな声で話すと娘が「うるさい!」と怒ることが多くありました。
また、癇癪の時間は1時間〜3時間くらいかかることもありました。今は数か月間は癇癪を起しておらず落ち着きましたが、当時は地獄のような毎日でした。
癇癪について学ぶ
娘の癇癪について悩む中で、私なりに色々と調べてみました。
癇癪の定義とは?
癇癪とは、感情のコントロールが一時的にできなくなり、激しい怒りや不満が爆発する状態のことです。
娘の場合、まさにこの定義に当てはまるような症状が見られました。特に、言葉でうまく気持ちを伝えられない幼い頃は、癇癪という形で感情を表していたのかもしれません。
「自分の言いたいことが言葉でうまく伝えられない」から暴れて意思表示をしているようにも見えたことは何度もあります。
癇癪を起こしやすい子どもの特徴とは?
一般的に、癇癪を起こしやすい子どもには、以下のような特徴があると言われています。
- 感情の起伏が激しい
- 我慢することが苦手
- 自分の要求が通らないとすぐにパニックになる
- 繊細で感受性が強い
しかし、これらの特徴のなかで、娘が唯一当てはまるのが「自分の要求が通らないとすぐパニックになる」点です。
特徴が全て当てはまるわけではないかと思います。
癇癪と発達障害の関連性
娘の癇癪がひどい時期には、「もしかして発達障害と関係があるのかな?」と不安になったこともありました。
しかし、発達障害が原因で癇癪のような行動が見られる場合もありますが、癇癪があるからといって必ずしも発達障害であるとは限りません。
娘の場合は、今のところそういった検査はまだ受けていないのでわかりませんが、気になる方は受けてみてもいいかもしれません。
癇癪は「生まれつきの特性」が関係するのか?
そして、私が一番気になっていた「癇癪は生まれつきの特性が関係するのか?」という疑問についてです。
インターネットでさまざまな情報を調べてみると、癇癪そのものが直接遺伝するというよりも、
- 感情のコントロールに関わる気質
- ストレスを感じやすいといった特性
が親子間で似る可能性はあるとのことでした。
私の家族を振り返ってみた
ふと自分の家族のことを振り返ってみました。
私の父も、短気で感情の波が激しかったんです。
- 自分の思い通りにならないと怒鳴りつける
- 物を投げる
- 自分の反対意見は聞かない
などという一面がありました。
また、私自身も、どちらかというと感情的な方かもしれません。
普段は大丈夫なのですが、
- 時間がなく追い詰められるとパニックになる
- 急いでいる時は、子供に対して怒鳴ってしまうこともある
これらは、ずっと普通のことだと思っていましたが、「一般的には普通ではない」と子どもの癇癪を通して知りました。
もちろん、性格や気質は生まれつきの特性だけではなく、育った環境や経験によっても大きく左右されます。
しかし、「もしかしたら、娘の癇癪の背景には、生まれつきの特性や性格の傾向も少しはあるのかもしれないな…」と感じるようになりました。
今は、パニックになったり、イライラするときは、深呼吸を数回繰り返しして落ち着くように心がけています。
生まれつきの特性だけでなく、環境も大切
ただ、生まれつきの特性が全てではないことも理解しています。
娘が成長するにつれて、言葉で自分の気持ちを伝えられるようになったり、我慢することを学んだりする中で、癇癪の頻度や激しさは徐々に落ち着いてきました。
小2になった今では、数カ月は癇癪を起こしていません。
これは、娘自身の成長はもちろん、私たち親の関わり方や、家庭環境も大きく影響しているのだと思います。
- あまり急かさない
- 多少の遅刻はOKとする
- 完璧を目指さない
これらをモットーに、肩の力を抜いて娘に向き合うように心がけています。
娘の癇癪から学んだこと
娘の癇癪と向き合う中で、本当に多くのことを学びました。
長女の癇癪を通して私が学んだこと
一番大きかったのは、癇癪を起こしてるときは本人も辛いということです。
癇癪を起こしている時は、「またか⋯」と自分本位で考えてたのですが、娘が癇癪後に「止めたいけど止められない⋯」と大泣きしたのを見て、本人が一番つらいことが分かりました。
また、癇癪の引き金を見つけることも重要だと気づきました。
娘の場合は、行動を切り替える時に癇癪が起こることがわかりました。とくに、「急がせてしまう」と癇癪が起きやすいと感じました。
例えば、娘が遅刻すると、私の仕事の時間にも影響が出てしまうので、「早くして!!」と毎日のように言っていました。
このように急かすと、プレッシャーに感じ、癇癪を起してしまうことが多かったんです。
なので、学校や習い事の多少の遅刻は大目に見ることにしています。
もちろん事前に対策できればいいのですが、早めに準備をしても癇癪を起こすときは起こすので、「もうそういうもんだ。」と割り切るようにしました。(でも、これが意外と辛かった)
また、夫の前では癇癪を起こすことがなかったので、夫がいるうちに娘の準備をしてもらったり、工夫するようにしました。
社会生活での癇癪の影響
娘が保育園や小学校で癇癪を起こすことで、他人を怪我させることは幸いありませんでした。
娘の場合は、「必ず」私にだけ癇癪を起こしていたので、そのへんは安心がありました。
しかし、癇癪を起こしているときに、誰かが娘を止めようすると、他の人にも手を出すことがありました。
今は定期的に病院へ行き、少しずつ、自分の感情をコントロールする方法を練習中です。
癇癪が起きないように心がけていること
娘の癇癪は、私たち家族にとって決して楽な道のりではありませんでしたが、娘の成長とともに、親も成長させてもらっていると感じています。
また、できるだけ癇癪を起さないように心がけるようにしています。
以下、具体的に気を付けていることです。
気持ちを言葉で伝える練習
日常会話の中で、「嬉しい」「悲しい」「悔しい」といった感情を表す言葉を教え、娘が自分の気持ちを言葉で表現できるよう促しています。
話を最後まで聞いてあげる
娘がイライラしてる時に、一人で落ち着くまで放っておくことを心がけてます。また、何か言いたそうなときは、時間がかかっても必ず最後まで聞くようにしています。
娘の言いたいことがうまく伝わってないときは、こちらが理解するまで何度も聞き返し、意思疎通をしっかりとるようにしています。
できたことを褒める
癇癪を起こさずにいられた時や、自分の気持ちを上手に伝えられた時には、大げさに褒めてあげるようにしています。
親として、自分自身を理解することも大切
娘の癇癪と向き合う中で、私自身も感情的になってしまうことがありました。
そんな時、「どうして私はこんなにイライラしてしまうんだろう?」と 、まず私自身が自分の感情を理解し、コントロールできるようになることが大切だと痛感しました。
「私がイライラするのも娘の癇癪と同じだな」と感じ、娘の辛さも分かるようになりました。
まとめ
癇癪はとても辛いものです。起こしてる本人はもちろん、周りの家族もしんどいです。
しかし、少しづつ練習していけばコントロールが出来るようになると私は娘を通して実感しました。
娘は今、数カ月間、癇癪を起こしていません。
もし、今、お子さんの癇癪で悩んでいる方がいたら、「一人で抱え込まないで」と伝えたいです。
この記事が、少しでも参考になれば幸いです。