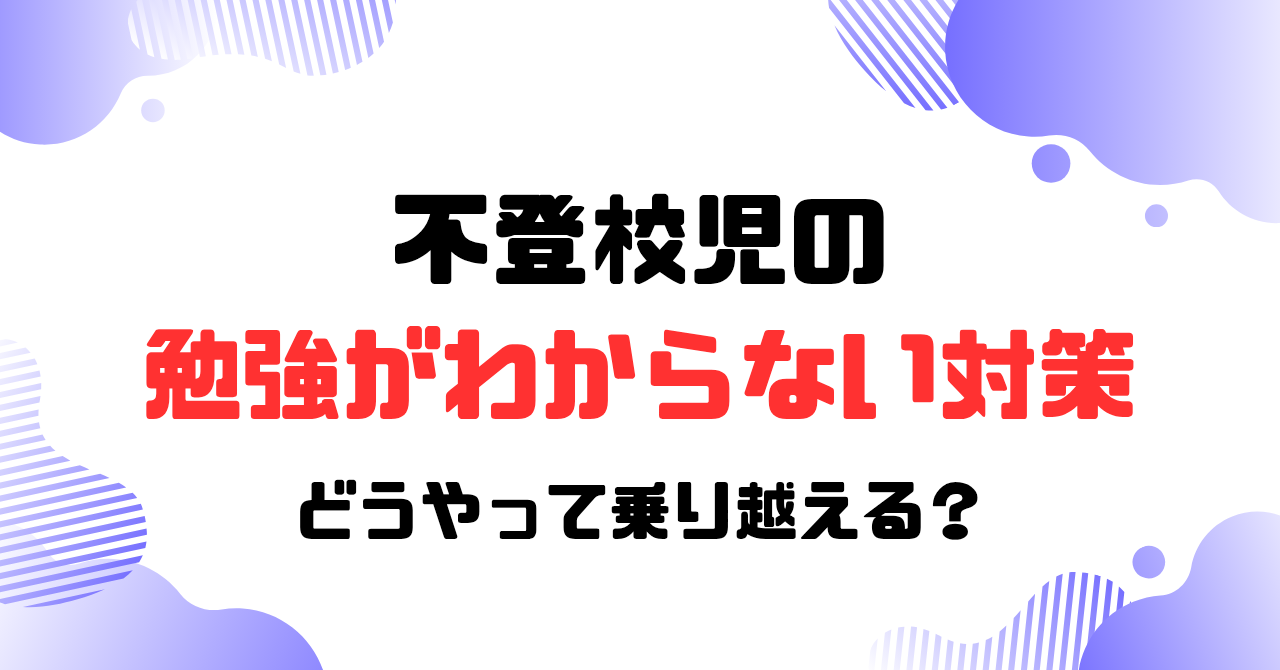不登校の子どもの学習について、「わからない」という状況は、親にとって大きな不安の種です。
特に、学習の遅れが長期間にわたる場合、その不安は計り知れません。
私自身も、中学1年生の息子が6年間不登校で、学習面での不安と日々向き合ってきました。
この経験が、同じような状況にいる方の一助となれば幸いです。
子どもの「わからない」を具体的に知る
まず、子どもが「何がわからない」と言っているのかをしっかり把握することが大事です。
具体的な勉強内容の把握
どの教科のどの単元がわからないのか?
漠然とした「全部わからない」ではなく、具体的にどこでつまずいているのかを洗い出します。
教科書や問題集を見て、子どもと一緒に確認しましょう。
実際に、問題文を一緒に読み解くところを見ていると、つまずきが分かります。
- 分からない場合は、「具体的に、問題文のどの部分がどう理解できないのか?」を聞く。
- 「分からない」ところがが「分からない」場合は、もう少し簡単な問題を出してみて、どの単元でつまずいているのか確認する。

無気力の子どもは、ここを乗り越えれるだけでも凄いです。
私の中一の息子は、最近やっとスムーズに乗り越えられるようになりました。
どの内容から復習が必要か?
場合によっては、学年を遡って基礎からやり直す必要があるかもしれません。
小学校低学年での勉強内容が身についてない場合は基礎ができていないので、そこからやり直すことになるかもしれません。

掛け算や割り算が頭に入ってないと、中学生の勉強はもちろん、小学校高学年の勉強もわかるわけがありません。
勉強の習慣が欠如
次に、勉強の習慣が身についていないことに焦点を当てていきましょう。
勉強そのものへの抵抗感
集中できない、すぐに飽きる、といった勉強の習慣の欠如が根本にある場合もあります。
これは、勉強の「内容」がわからないというより、「勉強の仕方」がわからない、あるいは「勉強すること」自体に意味を見出せない、といった問題です。
また、「勉強してなんの意味があるの?」「どうせ大人になっても必要ないでしょ」などというパターンもあります。
この場合は、そもそも「勉強をする意味」すら理解していないので、根気強く説明するしかありません。

私の息子の場合は、このパターンでした。
本人にやる気が出なければ、どれだけ親が頑張っても無理です。
そのたびに、「あなたが、将来なんの職業に就くかで、今必要な勉強かどうかが変わる。でも、まだ中学生で将来の夢が決まってないなら、いろんなことを学ぶことで、『得意な勉強』『苦手な勉強』が分かって、それが職業を選択するときに役立つかもしれない。」と伝えました。
それでも理解してくれないときは、「受験に必要だから勉強しなさい!受験に受からなければ将来の職業の選択肢が狭まるんだよ!」と厳しく伝えたこともあります。
生活リズムの乱れ
昼夜逆転など、生活リズムが乱れていると、そもそも学習に取り組むための体力がなく、集中力も続きません。
なので、勉強の習慣をつけるためにも、まずは生活リズムを整えることから始めましょう。
- 朝は、学校が始まるくらいの時間に起こす。
- 一緒に朝食を食べる。
- 朝起きることで、夜に自然と眠くなるリズムを作る。

何度起こしても起きないと、親の方がしんどくなりますが、諦めず根気強く頑張りましょう!
私の場合、根気強く何度も朝起こしましたが、息子が自ら起きる姿勢を見せないときは、あえてしばらく放っておいたこともありました。
すると、不思議なことに、自分から生活習慣を改善する姿勢が見られたのです。
もちろん、毎日自分で起きれるわけではありません。
ただ、生活リズムが崩れすぎて夜眠れなくなると、「夜起きてもゲームもできないし、テレビも好きな番組がなくて暇だから、頑張って朝起きよう」となったそうです。
子どもによって差はあると思いますが、あえて放任してみるのも一つの手段かもしれません。
効果的な学習目標の立て方
基本的な生活リズムと、子どものやる気が整ったら、学習目標を立てます。
小さな目標から始める
例えば、「1日10分だけ勉強をやる」「週に3回はオンライン教材に取り組む」など、心が折れない程度のハードルから始めましょう。
「絶対に達成できる!」という簡単な目標を設定がオススメです。

ここで達成ができないと、自己肯定感が落ちてしまうので、無理しない程度のハードルが大事です。
結果ではなく行動の評価を
できた内容だけでなく、「今日は頑張って10分勉強できたね」「自分で問題集を開けたのはすごいね」など、行動そのものを具体的に褒めることで、次の行動への意欲を促します。

「こんな簡単なことを褒めなきゃダメなの?」とも思いますが、実際に、寝てばかりの不登校の子どもが、机に向かって問題集を自ら開けるようになったら、結構な進歩ですよね!
できたことを可視化
スタンプカードやチェックシートなどを使って、学習に取り組めた日を記録し、達成感を味わわせることも有効です。
しかし、子どもが自ら記録してくれるといいのですが、本人がやろうとしない場合は、親の手間が増えるのでオススメしません。
学習環境と時間のルール作り
次に、場所と時間のルール化についてです。
自宅学習の時間の固定
「この時間はリビングで勉強する」「この時間はゲーム禁止」など、明確なルールを決め、それを守ることを促します。最初は子ども自身が設定した短い時間から始めるのがオススメです。
親に決められるよりも、子どもが自分で決めたほうが、時間を守りやすくなるかと思います。
親も一緒に取り組んでみる
子どもによっては、親が横で読書をしたり、簡単な作業をしたりと、同じ空間で集中して取り組む姿を見せることで、学習に入りやすくなることがあります。
親だけスマホやテレビを見ているとやる気が出なくなることもあるようなので、試してみる価値はあります。
なお、私の息子の場合は、問題文を自分で読解することができないことが多かったので、隣でつきっきりで教える事がほとんどでした。
おかげで、私自身も小学校高学年~中学校の勉強を再び学ぶことができました。

教えようとすると、意外と分からなくて戸惑うので、時間があれば一緒に勉強するのもアリです。
親子間のコミュニケーションにもつながるので一石二鳥です。
PCやタブレットでの学習法
紙媒体は苦手だけど、「PCやタブレットなら勉強ができる」という子どもいます。
そういう場合は積極的にデジタル機器を使用しましょう。
ゲーム感覚で出来る勉強法もあるので、紙よりも楽しく前向きに取り組めるかもしれません。
また、学校から配布されているPCやタブレットを勉強に活用するのも一つの手です。
自治体によって違うかもしれませんが、私の息子のPCにはドリルが入っているので、先生に許可を得たうえで、ドリルで勉強を進めています。
この方法だと、親が隣にいなくても自ら勉強してくれるようになりました。
塾や家庭教師の活用
しかし、子どもが自宅で勉強してくれるとは限りません。
また、勉強したとしても親が付きっ切りでサポートするのは難しいでしょう。
そのような場合は、フリースクール、個別指導塾、家庭教師など、プロの力を積極的に借りるべきです。
無理に親が全てを抱え込む必要はありません。
時には毅然とした態度も必要
学習そのものから逃避しようとしたり、ずるずると時間を浪費したりする場合には、親として「このままではいけない」というメッセージを伝えることも重要です。
感情的に怒るのではなく、冷静に「これだけはやる」「この時間は守る」というルールを徹底する姿勢を見せましょう。
子どもの将来に向けて「必要な勉強」ということを伝えましょう。
子どものメンタルの程度にもよりますが、中学生の場合は、内申点や受験の話もしておくべきです。
高校進学に向けた具体的な準備
通信制高校の検討
自宅での学習が中心となり、登校日数が少ない通信制高校は、不登校を経験したお子さんにとって有力な選択肢です。
サポート校と併用することで、手厚い学習支援や精神的なサポートを受けられる場合もあります。
定時制高校の検討
昼間に自分の時間を確保しつつ、基礎学力を身につけたい場合に適しています。
高校に通学しなくても大学受験資格が得られるため、選択肢の一つとして検討できます。
教育支援センターの活用
公的な施設である適応指導教室では、少人数での学習指導のほか、集団活動を通じて社会性や協調性を育む機会を提供しています。学校への復帰を目指すステップとしても有効です。
まとめ
親の覚悟と継続的な働きかけ不登校のお子さんの勉強の問題は、一朝一夕には解決しません。
しかし、親が「甘やかし」と「突き放し」の間でバランスを取りながら、具体的な行動を促し、必要な支援を継続的に提供していく覚悟が求められます。
子どもの成長を信じ、時に厳しく、しかし愛情を持って接することで、必ず「わからない」を乗り越えて、自分の道を切り開いていく力をつけていくと信じています。
最後まで諦めずに、一緒に頑張りましょう!