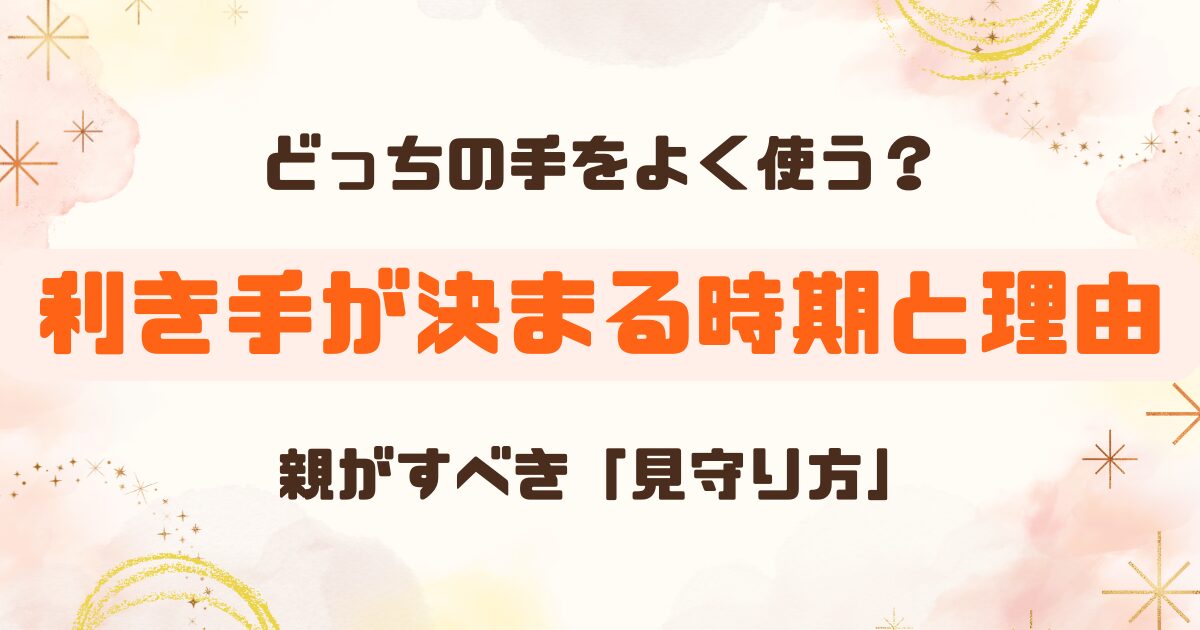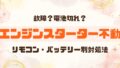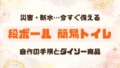「うちの子、どっちの手を使うんだろう?」「もしかして左利き?」「右利きに矯正した方がいいの?」
子どもの利き手について、こんな疑問や不安を抱える親は多いのではないでしょうか。最新の研究では、利き手が決まるメカニズムは非常に複雑で、遺伝や脳の発達、そして環境などさまざまな要因が絡み合っていると考えられています。
この記事では、子どもの利き手がいつ、どのようにして決まるのか、その科学的なメカニズムを分かりやすく解説します。
さらに、左利きの子どもへの接し方や、日常生活での具体的なサポート、おすすめグッズをご紹介します。
子どもの利き手はいつ決まる?成長段階ごとのサイン
「利き手」は、子どもが成長するにつれて少しずつ分かってきます。焦らず、子どもの自然な発達を見守ることが大切です。
新生児期~生後6ヶ月頃
この時期は、まだ利き手が決まっておらず、左右の手をほぼ対称に使います。おもちゃを両手で掴んだり、顔に左右の手を交互に持ってきたりする様子が見られます。
生後6ヶ月~1歳頃
この頃から、どちらかの手をメインで使う様子が出てくることがあります。特定のおもちゃを取るときや、離乳食を食べる際にスプーンに手を伸ばすときなどに、よく使う手があるか観察してみましょう。ただし、まだ安定しないことも多いです。
1歳~3歳頃
この時期には、利き手がよりはっきりとします。スプーンやフォーク、クレヨンなどを握るときに、同じ手を選ぶことが増えてきます。遊びの中で、どちらの手をよく使っているか意識して見てみましょう。
3歳~5歳頃
ほとんどの子どもがこの時期に利き手がはっきりと決まると言われています。字を書く、絵を描く、ハサミを使うといった細かい作業を通して、どちらかの手を優位に使うようになります。この頃には、右利きなのか左利きなのかを判断しやすくなるでしょう。
利き手が決まる過程には、遺伝と環境の両方が影響すると考えられています。子どもが自然に自分の利き手を選ぶのを、温かく見守ってあげることが重要です。
右利きと左利き、脳の働きに違いはある?
「右利きは左脳、左利きは右脳を使う」という話を聞いたことはありませんか?
私たちの脳は左右で異なる働きを担っていますが、利き手と脳の関連性は非常に複雑で、いまだ完全に解明されているわけではありません。
- 左脳の主な働き: 言語処理、論理的思考、計算、分析などが得意とされています。
- 右脳の主な働き: 空間認知、創造性、感情、直感的思考などが得意とされています。
一般的に、右利きの人(全人口の約90%)は左脳が言語処理の主担当となることが多いです。一方、左利きの人(全人口の約10%)は、約70%が左脳を言語処理に使い、残りの30%は右脳を使うか、両方の脳を使うと言われています。
つまり、「左利き=右脳がメインでクリエイティブ」と一概に言えるわけではなく、利き手と脳の機能には個人差が大きいのです。
左利きは「天才肌」って本当?
「左利きは天才肌」とよく言われますが、これはどうなのでしょうか?
確かに、歴史上の著名な芸術家や科学者、スポーツ選手の中には左利きが多くいます。たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチやアインシュタイン、ピカソ、ビル・ゲイツ、オバマ元大統領なども左利きだと言われています。
これは、左利きが右利きが多数を占める社会で生きていく中で、独自の視点や発想力を培う機会が多いためかもしれません。
既存のやり方にとらわれず、新しい解決策を模索する力が、創造性や問題解決能力の高さにつながる可能性は考えられます。
左利きが生まれる理由
子どもの利き手がどのように決まるのか、科学者たちは長年研究を続けています。現在では、遺伝的要因が大きく関係しているという「遺伝説」が主流となっています。
研究によると、親の利き手の組み合わせによって、子どもが左利きになる確率は以下のようになると言われています。
- 親が両方とも右利きの場合:約9.5%
- 親の片方が左利きの場合:約19.5%
- 親が両方とも左利きの場合:約26.1%
しかし、親がどちらも右利きでも左利きの子どもが生まれることも多く、完全に遺伝だけで決まるわけではありません。胎児期の脳の発達や、生まれてからの環境要因なども複雑に絡み合っていると考えられています。
左利きのメリットとデメリット、そして親ができるサポート
左利きは世界人口の約10%と少数派。右利きが基準の社会で生きる上でのメリットとデメリットを理解してあげることが大切です。
左利きのメリット
- 独特の視点と問題解決能力: 右利き用のツールや環境に合わせる中で、自然と工夫する力が養われます。これが、既存の枠にとらわれない柔軟な思考や問題解決能力につながると言われています。
- スポーツでの優位性: テニス、野球、ボクシングなど、相手と対峙するスポーツでは、左利きならではのプレースタイルが相手にとって「読みにくい」「慣れていない」ため、有利になることがあります。
左利きのデメリットと対策
日常生活には、右利き用に作られたものが多く、左利きの人にとっては不便を感じる場面が少なくありません。
日常生活の道具の例:
- バイキングのスープのお玉、キッチンベラ
- 缶切り、はさみ、定規
- 自動販売機のコイン投入口、改札の電子カードタッチ位置
- トイレのレバー、ハーモニカのホース位置など
対策と親のサポート:
- 左利き用グッズの活用: はさみや定規、包丁など、左利き用の便利なアイテムが増えています。無理に右利き用を使わせず、専用グッズを揃えてあげましょう。最近では、文具店やオンラインストアで多く見つかります。
- 道具の工夫: お玉などは左右どちらでも使えるものを選んだり、必要に応じて向きを変えてあげたりするなどの配慮を。
- 書き方や文字の工夫: 左手で書くと文字が隠れてしまったり、インクで手が汚れたりすることがあります。斜め書きを試したり、筆記用具の選び方を工夫したりすると良いでしょう。
- 環境の整備: 食卓での席順を工夫して、隣の人と腕がぶつからないようにするなど、ちょっとした配慮が快適さにつながります。家族で食事する際は、利き手によって座る位置を決めておくとスムーズです。
右利きへの「矯正」は必要?
「左利きだと不便だから右利きに直した方がいい」という考え方が、一昔前には主流でした。しかし、現在では無理な利き手矯正は避けるべきという意見が一般的です。
無理な矯正が子どもに与える影響は?
- 精神的ストレス: 利き手は自然に決まるものであり、それを無理に変えようとすると、子どもは大きなストレスや混乱を感じてしまいます。「自分の体が間違っている」と自己肯定感が下がってしまうリスクもあります。
- 学習への影響: 言語処理や書き取り、読み書きの際に混乱が生じ、学習効率が低下する可能性があるという研究もあります。
- 運動能力・器用さの低下: 慣れない手を使うことで、本来持っている運動能力や手先の器用さが十分に発揮できなくなることも考えられます。
親ができること
親が右利きで子どもが左利きの場合、日常生活で戸惑うことも多いでしょう。しかし、大切なのは子どもの自然な利き手を受け入れ、最大限にサポートしてあげることです。
- 「どちらの手を使ってもいいよ」という肯定的な声かけ: 子どもがどちらの手を使っても、否定せずに温かく見守りましょう。
- 左利き用の道具を準備する: 子どもがストレスなく生活できるよう、必要な道具を揃えてあげることが第一歩です。
- 困っていることに耳を傾ける: 「これ、使いにくいな」「どうやったらいいの?」といった子どもの声に耳を傾け、一緒に解決策を考えてあげましょう。
昔に比べて左利き用のアイテムも増え、社会の理解も深まっています。
親が子どもと一緒に左利きの世界を体験してみる(例えば、左手で食事をしてみる、左手で文字を書いてみるなど)と、新たな発見があり、子どもの気持ちに寄り添えるようになるかもしれません。
まとめ
子どもの利き手がいつ、どのように決まるのかは、多くの親にとって関心の高いテーマです。遺伝や脳の発達、環境などさまざまな要因が複雑に絡み合って利き手が決まること、そして無理な利き手矯正は避けるべきだということが、お分かりいただけたのではないでしょうか。
右利きが多数派の社会で、左利きの子どもが不便さを感じる場面は確かにあります。しかし、それは「個性」の一つとして捉え、親が適切なサポートをしてあげることで、子どもは自信を持って成長していくことができます。
利き手は、その子のユニークな特性です!
子どもの個性を尊重し、それぞれの「利き手ライフ」を一緒に楽しみ、サポートしてあげましょう!
こちらの本を読むと「左利きの凄さ」が理解できると思います。