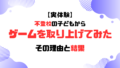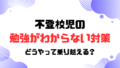共働き家庭が増える現代において、「もしかして、うちの子も…?」と不登校を心配する声も少なくありません。
共働きであること自体が不登校の直接的な原因になるわけではありませんが、家庭環境や親子のコミュニケーションに不登校につながる要因が隠されていることもあります。
この記事では、私自身が子どもが生まれてからずっと共働きで育児をしてきた中で、12歳の不登校の子どもを持つ経験を通して学んだ、共働き家庭が不登校問題とどう向き合うべきかについて、経験者の視点からお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
共働き家庭と不登校は関係ある?
共働き家庭が増加する中で、子どもの不登校は社会的な課題となっています。
共働きだと、子どもとの時間が限られ十分なコミュニケーションが取れなかったり、仕事や育児で忙しく親がストレスを抱えやすくなったりすることは否定できません。
しかし、「共働きだから不登校になりやすい」と一概には言えません。
実際に、我が家は共働き家庭で、長男(12歳)は7歳から不登校です。しかし、長女8歳は学校が大好きで、毎日登校しています。
同じ親でも、子どもによって違うのであれば、親のせいではありません。
実は、不登校には様々な要因が複雑に絡み合っています。
そして、不登校になりやすい家庭には、いくつか特徴が見られることがあります。
例えば、過干渉や無関心、完璧主義な親、親子間のコミュニケーション不足などが挙げられます。
共働き家庭になると、仕事が忙しいあまり、子どもの心の変化に気づきにくい、あるいは子どもの話をじっくり聞く時間が取れないといった状況が、不登校のリスクを高める可能性はあります。
もちろんこれらが当てはまったからと言って、必ず「不登校」につながるわけでもありません。
実体験から学んだ不登校の原因
私自身の家庭も共働きで、子どもが不登校を経験しました。その中で痛感したのは、共働きゆえのストレスが家庭環境に影響し、子どもにも影響を与えていたことです。
夫の帰りが遅く、ワンオペ育児が続き、全て自分だけでこなさなければならないと、心に余裕がない日々が続きます。
また、常に時間に追われ、子どもへの接し方がおざなりになったり、些細なことで感情的になったりすることがありました。

「早くして!」「まだなの?」「時間ないよ!」が私の口癖でした。
このような家庭環境は、子どもに心理的なプレッシャーをあたえるだけでなく、精神的に追い詰めていたんだと思います。
例えば、「学校に遅刻せずに行きなさい」「宿題は必ず提出しなさい」「〇時になったら、お風呂入りなさい」など、私自身は「出来て当たり前」だと思っていたのですが、子どもは「出来ないとダメな人間なんだ」と感じることもあったようです。
また、第三者に指摘されて気づいたことは、「出来ないことを指摘していて、出来ることを褒めていない」と言われました。

実際に、自分でも思い返してみると、テストを返してもらったときに、90点だとしたら、「残りの10点のミス」を先に指摘して、「90点を取ったこと」は褒めていなかったことに気づきました。
このような些細な積み重ねで、子どものメンタルが崩壊してしまったのではないかと思います。
子どもが不登校になるサインは、最初は見過ごしてしまうような小さな変化から現れることが多いです。
朝起きられない、体調不良を訴える、学校の話をしたがらない、元気がない、いつもと違う様子が見られたら注意が必要です。
子どもが登校を拒否する理由も、年齢によって異なります。
小学生の場合は「何で嫌なのか分からない」などということが多かったのですが、中学生になると、勉強の進捗状況、友達関係、将来への不安など、より複雑になってくるようです。
不登校問題対策に必要なコミュニケーション
不登校問題を乗り越える上で最も重要だと感じたのは、親子のコミュニケーションです。親子のコミュニケーションを改善するためには、まず「聞く」ことに徹することが大切です。
子どもの話を遮らず、最後まで耳を傾け、子どもの気持ちを否定せずに受け止めることが大事です。
なかでも「否定しないこと」はとても重要です。
たとえ間違った意見だとしても、「そういう考え方もあるんだね」と一度受けて止めてあげましょう。
こちらが初めから否定してしまうと、「何を言っても無駄だから話したくない」に繋がって悪循環です。
短い時間でも、毎日子どもと向き合い、今日あった出来事や感じたことを話す時間を作るように心がけるといいでしょう。
また、学校との連携も欠かせません。
担任の先生やスクールカウンセラーと積極的に情報共有し、子どもの学校での様子を把握することで、家庭と学校が一体となって子どもをサポートできます。
友達との交流不足も、不登校の一因となることがあります。
学校以外の場所で安心して過ごせる居場所や、気の合う友達と交流する機会を作ることも大切です。
気の合う友達がいない場合は、デイサービスや習い事など、学校以外の場所でほかの人との交流を取れるようにしてあげると、社会とのつながりを保てるきっかけになります。
共働き家庭が行うべきサポートと対策
共働き家庭だからこそ、子どもの不登校問題に対して意識的に取り組む必要があります。
親は仕事と育児の両立で忙しいと、子どもとの時間確保が難しいと感じることもあるでしょう。
しかし、わずかな時間でも意識的に子どもと向き合う時間を作ることが大切です。

例えば、「家事は後回しにする」「晩御飯はたまには手を抜く」「掃除機はロボットに任せる」など、少しでも時間を作れるといいですよね!
その上で、子どもの自己肯定感を育むことは、不登校対策の基本です。
テストの点数や成績だけでなく、小さな努力や成長を認め、褒めることで、『自分は価値のある人間だ』と感じられるようにサポートすることが大事です
完璧を求めすぎず、プレッシャーを軽減するための家庭内ルールを作ることも大切です。親の考えで『〇〇でなければならない』という決めつけはせずに、子どもの気持ちに寄り添った柔軟な対応を心がけましょう。」
そして、不登校問題に悩んだら、一人で抱え込まず、専門機関の支援を頼ることも重要です。
教育センター、精神科医、児童相談所など、様々な相談窓口があります。色々なところで話を聞くと、自分の考えでは分からなかったことが分かることもあります。
新たな発見があるかもしれないので、積極的に相談してみるといいと思います。
まとめ
共働き家庭において、不登校は避けて通れない課題の一つかもしれません。
しかし、親が子どもの成長を促すために家庭の役割を理解し、安心できる環境を整えることで、不登校のリスクを減らし、子どもが健やかに育つ手助けができます。
仕事と育児の両立は決して簡単ではありませんが、夫婦で協力し、時には外部のサポートも借りながら、子どもとの時間を大切にすること、そして何よりも子どもの心の声に耳を傾けることが、不登校対策の第一歩となります。
もし今、子どもの不登校で悩んでいるなら、まずは専門家や信頼できる人に相談することから始めてみませんか?