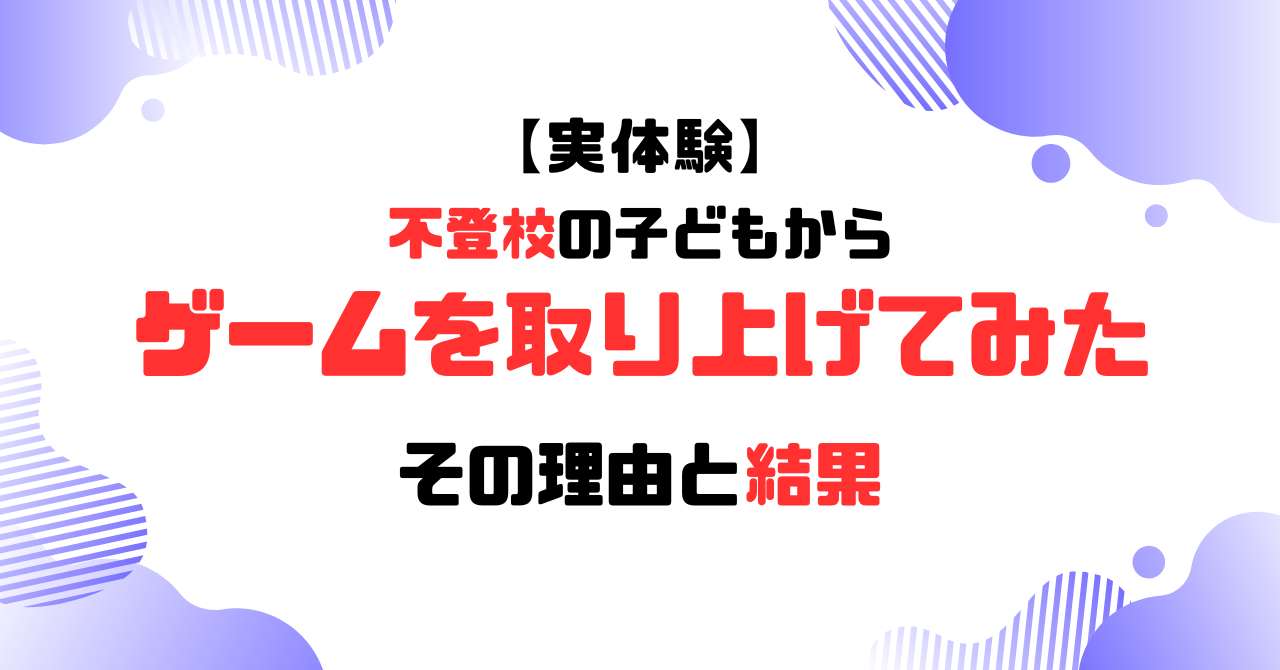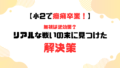不登校とゲームの関係に悩む保護者の方は少なくありません。
「学校に行かないのに勉強せずにゲームしてる⋯」そんな姿を見ていると「ゲームを取り上げる」という選択肢が出てくるのは当然です。
この記事は、実際に不登校の子どもからゲームを取り上げたリアルな体験談です。
取り上げようか悩んでいる方の参考になればが幸いです。
不登校の子どもに対するゲーム取り上げの理由
不登校の子どもからゲームを取り上げることを考えるには、いくつかの理由があります。
子どものゲーム依存
不登校だとリアルな交友関係が希薄になるうえ、架空のゲームの世界にのめり込んでしまい生活リズムの乱れも構わず、ゲームに没頭してしまうことがあります。
このようなゲーム依存は、勉強だけでなく、日常生活全般に深刻な影響が出てきます。当然近くで見ている親としては、将来への強い不安を感じます。
親のイライラとストレス
子どもの不登校が長期化すると、親は様々な葛藤を抱えます。
子どもの無気力な姿や、何度声をかけても反応がない状況に、イライラやストレスが募ることが多くなります。
「親は一生懸命働いてるのに、勉強せずに寝るかゲームしてばかり」
と強い憤りを感じることもあるでしょう。
ゲームがその原因の一つだと感じると、「ゲームを取り上げるしかない」という考えに至るのも無理はありません。
ゲームを取り上げると逆効果?
しかし、安易にゲームを取り上げることは、かえって状況を悪化させる可能性があります。
暴れる子どもに対する家庭の対応
ゲームを取り上げられた子どもが激しく抵抗し、暴れることもあります。
親子の間で激しい口論や衝突が起こり、家庭内の雰囲気は最悪になることも…。
こうなると、子どもの心の状態はさらに不安定になり、不登校がより深刻化する可能性もあります。
ゲーム禁止がもたらす影響とは?
ゲームを禁止することで、唯一の居場所や楽しみがなくなり、さらに孤立したり、生きる意欲がなくなることもあります。
また、隠れてゲームをするようになったり、親との関係が悪化したりと、信頼関係が大きく損なわれることも懸念されます。
子どもから取り上げた理由と結果
そんなデメリットを理解しながらも、「現状をなんとか打破したい!!」「何もしないと変わらない!」との思いで、今回取り上げようと決意しました。
前回は、自傷行為などがあったので、「完全に取り上げる」のが怖くてできませんでしたが、今回はメンタルが安定してそうなので、一歩踏み込んでみようと思います。
私がゲームを取り上げた理由
私の息子は中学校一年生で不登校歴は、6年目になります。
一時的に学校へ行けることもあるのですが、基本的には家に引きこもっている状態です。
我が家のゲームのルールは「学校が終わる時間にゲームしてOK」にしていたのですが、学校へ行かないうえに、勉強はせず、日中はずっと寝て、夕方からゲームという最悪な生活リズムになっていたからです。
もちろん家の手伝いもしてくれません。
「親として放っておくと、子どもにとって良くないのでは⋯」という気持ちはもちろんですが、こっちは一生懸命働いて家事もしてるのに「何もしない子供」への苛立ちの方が大きかったかもしれません。
取り上げた結果は?
もちろん取り上げる前には、きちんと子どもと話をし、納得させたうえで取り上げました。
しかし、納得していたと思っていたのは親だけで、子どもは隠れてゲームやスマホで遊んでいました。
隠れて使ってるのを見つけるたびに、子どもに注意するようにし、再び取り上げますが、反省せずに数回繰り返します。
子どもが「ごめんなさい」と言うたび、私は「そんなことを繰り返してたら信用できなくなるよ」と、諭すように言いました。

心ではダメだと分かっていても、手を伸ばしてしまうのは「依存になっているのでは⋯?」と不安になりました。
物理的に子どもが取り返せないようにすることも考えましたが、それでは意味がないと考え、あえて毎回同じ場所に片付けました。
どうしても、子ども自身に気づいてもらい、納得し理解してもらいたいと感じたからです。
数回繰り返し叱ると、自ら反省したようで、隠れて遊ぶことはなくなったと思います。(隠れて遊ぶ現場を見ていないだけかもしれませんが⋯)
叱るときにかけた言葉は、
「あなたが寝ていたりゲームしている間に、他の子は勉強をどんどん進めてる。」
「お父さんもお母さんも家のために一生懸命働いてる。」
「それなのに、何もせずに自分だけゲームだけするのは、ズルいと思わない?」
と冷静に声をかけました。
それでも初めは、ふさぎ込むことが多かったので、「本当にこの𠮟り方でいいんだろうか?」と自問自答することが多々あり、メンタルが削られました。
そんな試行錯誤する中で、時には毅然とした態度も必要だと感じ、無視される場面ではこちらも徹底的に無視する、という対応もとりました。
そのかいあってか、同じことをやられる気持ちが分かったようで、そこから徐々に、家の手伝いや勉強に積極的に向き合うようになってくれたので、子どもに伝わったのかな?と感じています。
実体験から学んだことは?
ゲームを取り上げた当初は、ゲームにそんなに依存するならば、二度とゲームなんかさせたくない!と考えていました。
しかし、何度も取り返す姿を見て、ゲームが心の支えになってることに気づきました。
実際に土日にゲームをしているときはイキイキしてるんです。
それほどゲームがしたいならなぜ学校に行かない?という疑問もありますが、それとこれとはまた別のようです。
いまは、できる限り子どものゲームの話を聞き、土日には「どんなゲームで、どんな内容の事を進めているのか?」を見るように心がけています。
不登校の子どもに対する適切な対応方法は?
では、ゲームとの付き合い方について、どのようにアプローチすればよいのでしょうか。
ゲームとの付き合い方
ゲームを完全に排除するのではなく、ゲームとの健全な付き合い方を子どもと一緒に考えていくことが重要です。
まずは、なぜゲームに没頭するのか、ゲームを通して何を得ているのか、子どもの気持ちに寄り添って理解しようと努めましょう。
子どもが遊んでるゲームを一緒にプレイして、楽しさを分かち合うのも一つの方法です。
実際にゲームを体験してみると、客観的に見たときと考え方が変わるかもしれません。
また、一方的な禁止ではなく、ゲームをする時間や内容について、子どもと話し合って具体的なルールを設定することが大事です。
例えば、「ゲームは〇時まで」「勉強が終わってから」など、必ず親子で納得できる落としどころを見つけましょう。
納得していないと、隠れてゲームをするなどよくない方向につながる可能性があります。

親の前では、納得しているふりをしていても、私の息子のように「実は納得していなかった」というパターンもあると思います。
また、ルールは守れなかった場合のペナルティも明確にしておくと良いでしょう。

実際に、子供が隠れて遊んでいたときに、約束した時点で一緒にペナルティを決めておけばよかったと痛感しました。
これは、ゲームの使用を制限するだけでなく、「子どもが目標を持って前向きに取り組めるようなきっかけになれば」という思いからでした。
依存から回復するための方法は?
ゲーム依存が疑われる場合は、専門機関への相談も検討しましょう。
カウンセリングなどを通して、ゲーム以外の新たな興味や居場所を見つけるためのサポートも必要です。
デイサービスなどに通える場合は、子どもにあった環境を見つけてあげると、外に出る機会が増えるので、ゲーム以外のことに目を向けるチャンスかもしれません。
学校との連携の重要性
不登校改善には、家庭だけでなく学校との連携も不可欠です。
学校の先生と子どもの状況を共有し、協力してサポート体制を築くことで、子どもは安心感を持ち、少しずつ社会との繋がりを取り戻しやすくなります。
実際に、不登校になってからは、学校の先生が定期に話す機会を設けてくれているので、学校と離れすぎない距離感を保てています。
先生と話すのも楽しそうに会話は出来るので、絶妙にいいバランスを保ててるのかな?と感じています。
まとめと今後の展望
ゲームを一方的に取り上げるのではなく、子どもとの対話を深め、親子関係を良好にし、向き合うことが不登校改善への第一歩なのは間違いありません。
ゲームは悪者ではなく、使い方次第では親子で共通の話題にもなります!
子どもとの関係性やメンタルバランスを考え、上手に使いこなすようにしていきましょう!
この記事が、不登校に悩む保護者の方の一助となれば幸いです。