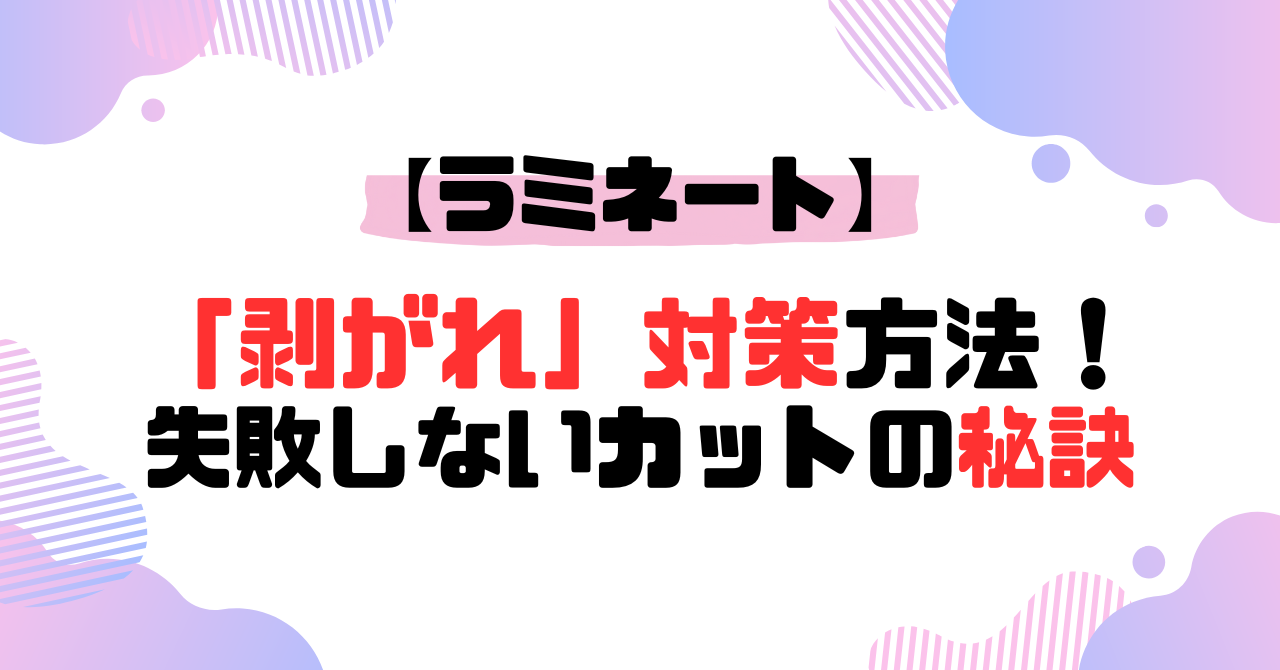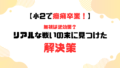ラミネート加工は、大切な書類や写真を水濡れや汚れから守り、長持ちさせる便利な方法です。
しかし、「切ると剥がれてしまう」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、ラミネート加工の基本から、カットのコツ、そして剥がれを防ぐための対策まで、きれいに仕上げるための秘訣を徹底解説します。
ラミネートとは?仕組みを解説

ラミネートとは、紙などの素材を透明なフィルムで挟み込み、熱と圧力で圧着する加工のことです。
これにより、原稿を保護し、耐久性や防水性を高めることができます。店舗のPOP、メニュー、名刺、写真など、幅広い用途で活用されています。
ラミネート加工のメリット・デメリット
ラミネート加工を始める前に、メリット・デメリットも知っておきましょう。
メリット
耐久性の向上
破れや折れを防ぎ、長期保存が可能になります。
防水・防汚
水濡れや汚れから原稿を守ります。
再利用が可能
強度が上がるので、繰り返し使用するものの保護に適しています。
デメリット
コスト
ラミネーターやフィルムの購入費用がかかります。
修正ができない
一度ラミネートすると元に戻せません。
かさばる
厚みが出るため、保管場所を取る場合があります。
光の反射
光が反射して見えにくい場合があります。
ラミネーターの種類と選び方
ラミネーターには大きく分けて「ホットラミネーター」と「コールドラミネーター」があります。
ホットラミネーター
熱でフィルムを溶かし圧着するタイプで、家庭用から業務用まで幅広く普及しています。光沢のある仕上がりが特徴です。
コールドラミネーター
熱を使わず、フィルムの粘着力で圧着するタイプです。
熱に弱い写真や感熱紙の加工に適しています。
どちらのラミネータでも選ぶ際は、使用頻度、加工したいサイズ、ウォームアップ時間、加工速度、そして予算などを考慮しましょう。
ラミネート加工に必要な道具

きれいなラミネート加工の第一歩は、丁寧な準備です。
必要なアイテムを揃えて取り掛かることが、きれいなラミネート加工にするコツです。
必要な道具のリスト
ラミネーター
使用したいサイズに対応するものを選びましょう。
ラミネートフィルム
ラミネーターの機種に合った厚み(ミクロン)とサイズを選びます。
ラミネートする素材
ラミネートしたい写真や書類など。
カッターマット
カット作業時にテーブルを傷つけないために必要です。いらない雑誌などでも対応できます。
カッターナイフ
直線カットに便利です。
ハサミ
細かい部分や曲線カットに便利です。
定規
正確なカットに必須です。金属製だとより安定します。
マイクロファイバークロスまたはメガネ拭き
原稿やフィルムのホコリ、指紋を取り除くために使います。
フィルムのサイズと選び方
ラミネートフィルムは、A4、A3などのサイズがあり、厚みも様々です。
サイズは、素材よりも一回り大きいサイズのフィルムを選びましょう。余白がないと剥がれやすくなります。
厚み(ミクロン数)によって使い勝手が変わりますので、用途に合った厚みを選びましょう。
一般的には100ミクロンが多く、手軽に手に入ります。厚みが増すほど丈夫になりますが、曲げにくくなるので気を付けてください。
また、ラミネーター(機械本体)で対応できる厚みの異なりますので、併せて確認しましょう。
100ミクロン
一般的な用途に最適。名刺や写真など。
150ミクロン
より丈夫にしたい場合に。メニューや掲示物など。
250ミクロン
最も丈夫で、何度も触るものや屋外での使用に。
ラミネート加工の注意点
ラミネートする前に以下のことを注意しましょう。
インクの乾燥
インクジェットプリンターで印刷したものは、完全にインクが乾いてからラミネートしましょう。乾いていないと、フィルムの中でにじんでしまうことがあります。
ホコリ・指紋の除去
原稿にホコリや指紋が付いていると、そのままラミネートされてしまい、仕上がりが悪くなります。作業前にクロスで丁寧に拭き取りましょう。
紙のしわ・折れ
しわや折れがあると、その部分に気泡ができやすくなります。できるだけ平らな状態にしておきましょう。
厚みの確認
極端に厚い紙や凹凸のあるものは、ラミネートできない場合や、機械の故障につながる可能性があります。ラミネーターの対応厚みを確認しましょう。
失敗しない!ラミネートのカットのコツ
ラミネート加工で「剥がれる」というトラブルは、カットの仕方に原因があることがほとんどです。
ここでは、剥がれを防ぐための正確なカット方法と余白の取り方を解説します。
カッターを使用した切り方のコツ
直線カットには、カッターが最も適しています。カッターでカットする際のコツがあるので、以下を試してみてください。
カッターマットを敷く
作業台を保護し、カッターの刃を傷めないためにも必ず敷きましょう。
定規をしっかりと固定する
定規がずれると切り口が歪んでしまうため、しっかりと押さえます。滑り止め付きの定規がおすすめです。
刃は新しいものを
切れ味が悪いと、フィルムが波打ったり、綺麗に切れません。新しい刃を使うか、こまめに刃を折って新しい部分を使いましょう。
力を入れすぎず、数回に分けて切る
一度に切ろうとすると、フィルムが歪んだり、刃が滑って危険です。軽く力を入れて数回なぞるように切ると、きれいに仕上がります。
ハサミを使った切り方のコツ
曲線や複雑な形にカットする場合はハサミを使います。
切れ味の良いハサミを使う
切れ味が悪いと、切り口がガタガタになったり、フィルムが裂けてしまうことがあります。
ゆっくりと、一気に切ろうとしない
特に曲線は、少しずつ刃を進めるように切ると滑らかに仕上がります。
角を丸くする(※推奨)
角がとがったままだと、そこから剥がれてしまいます。角を丸くすると、剥がれにくくなるだけでなく、安全性が向上するのでオススメです。
切る際の余白はどのくらい必要?
ここが「剥がれる」を左右する最も重要なポイントです。
理想的な余白は、素材の端から3mm〜5mm程度です。この余白が、フィルムが原稿としっかりと圧着されるための「のりしろ」のような役割を果たします。
余白が少なすぎると、フィルムが原稿から剥がれやすくなり、耐久性も損なわれます。
逆に余白が広すぎると、見た目が不格好になったり、かさばる原因になります。
ラミネート加工の手順

準備とカットの重要性を理解したところで、いよいよラミネート加工の具体的な手順と、気泡や汚れを防ぐためのコツを見ていきましょう。
ラミネート加工の流れ
ラミネート加工は、以下の手順で進めます。
①ラミネーターの準備
電源を入れ、設定温度(使用するフィルムの厚みに合わせる)まで温めます。機種によってウォームアップ時間は異なりますが、一般的に5〜10分程度です。
完全に温まるまで待つことが重要です。ランプなどで準備完了を知らせてくれる機種もあります。
②原稿のセット
ラミネートフィルムを開き、原稿を中央に配置します。この時、ホコリや指紋が付かないように注意しながら、慎重に置きます。
原稿の周囲に均等な余白ができるように調整します。 フィルムを閉じ、しわや気泡が入らないように軽く押さえます。
③ラミネート開始
フィルムの閉じた側から、ラミネーターの投入口にまっすぐ挿入します。
この時、斜めに入れたり、無理に押し込んだりすると、フィルムが詰まったり、気泡やしわの原因になります。
ラミネーターが自動でフィルムを引き込み、加工が始まります。
④加工後の取り出しと冷却
加工されたフィルムが排出口から出てきたら、完全にラミネーターから出てくるまで待ちます。
熱くなっているので、やけどに注意しながら取り出します。
取り出したラミネート品は、平らな場所で完全に冷まします。
冷める過程でフィルムがしっかりと定着します。
急いで触ったり、無理に曲げたりすると、仕上がりが悪くなることがあります。
気泡やホコリを防ぐためのコツ
気泡やホコリが入るのを防ぐためにもコツがあります。
ラミネーターの温度設定を適切に
フィルムの厚みに合った温度に設定しないと、フィルムが十分に溶けず気泡が入ったり、逆に熱すぎて変形したりします。
ゆっくりと投入する
特に大型のラミネートの場合、急いで投入すると空気を取り込みやすくなります。ゆっくりと、まっすぐに送り込みましょう。
原稿とフィルムの間にホコリを挟まない
これが気泡や黒い点となって残る最大の原因です。作業前に必ず原稿とフィルムをきれいに拭き取りましょう。
フィルムのしわを伸ばす
フィルムに最初からしわがあると、そのままラミネートされてしまいます。セットする際に、しわがないか確認し、あれば軽く伸ばしてからセットしましょう。
耳なし加工とは?
「耳なし加工」とは、素材の端までぴったりとフィルムを貼り合わせ、余白をほとんど残さない加工方法です。見た目がスッキリし、かさばらないというメリットがありますが、剥がれやすくなるリスクも伴います。
耳なし加工を試す場合は、以下の点に注意してください。
高性能なラミネーターを使用する
一般的な家庭用ラミネーターでは、耳なし加工は難しい場合があります。業務用など、より均一な熱と圧力をかけられる機種が推奨されます。
厚手のフィルムを選ぶ
薄いフィルムだと、剥がれやすくなります。150ミクロン以上の厚手のフィルムを選ぶと、比較的安定します。
事前にテストする
大切な素材を加工する前に、必ず不要な紙でテストを行い、剥がれないか確認しましょう。
加工後のカットはギリギリに
原稿の輪郭に合わせて、できるだけ余白を残さずに丁寧にカットします。この際、カッターの切れ味と定規の固定が非常に重要になります。
基本的には、剥がれを防ぐためには3mm〜5mmの余白を残すことを推奨します。
耳なし加工は、上級者向けのテクニックと認識しておきましょう。
ラミネート加工の応用テクニック

ここからは、さらに仕上がりを高めたり、特殊な用途でラミネートを活用するための応用テクニックをご紹介します。
ギリギリまで切るためのポイント
「剥がれるのが怖いけど、できるだけ余白を少なくしたい!」という場合、以下のポイントに注目しましょう。
高精度なカッターなどを使う
切れ味の良いカッターや、専用のペーパーカッター(裁断機)は、直線カットにおいて非常に高い精度を発揮します。
複数回に分けて丁寧にカット
一気に切ろうとせず、軽い力で数回刃を走らせることで、フィルムへの負荷を減らし、剥がれを防ぎながらギリギリを狙えます。
角は丸くする
ギリギリにカットしても、角を丸くすることで剥がれが起きにくくなります。
カットしてからの注意事項
ラミネート加工を施し、カットした後にも注意すべき点がいくつかあります。
完全に冷ます
カットする前に完全に冷めていないと、フィルムが不安定で剥がれやすくなります。
力を加えない
カット後に無理に曲げたり、強い力を加えたりすると、フィルムが浮き上がったり、剥がれてしまう可能性があります。
保管方法
直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での保管は避けましょう。変形や変色の原因になります。平らな状態で保管し、重いものを上に置かないようにしましょう。
よくある質問とトラブルの疑問
ラミネート加工中に起こりやすい疑問やトラブル、そしてその解決策について解説します。
ラミネート加工についての基礎的な質問
Q: ラミネートフィルムに表裏はある?
A: 基本的に両面同じように見えますが、片面がより密着しやすいように加工されているフィルムもあります。製品説明を読みましょう。迷ったら、少しざらつきがある方を内側(素材側)にするのが一般的です。
Q: ラミネートできないものはある?
A: 感熱紙(レシートなど)、クレヨンなど描かれたもの、厚すぎるもの、熱に弱いものはラミネートできません。機械の故障や原稿の変質につながる可能性があるのでやめましょう。
加工後の保管方法や耐久性について
保管方法は?
ラミネート加工品は、直射日光や高温多湿を避けて保管しましょう。反りや変色、剥がれの原因になります。平らな場所に置くか、ファイルなどに挟んで保管するのがベストです。
耐久性はどのくらい?
正しくラミネートされたものは高い耐久性があります。
水濡れや汚れ、破れに強いため、屋外での掲示や頻繁に手で触れるものに適しています。
ただし、鋭利なもので傷つけたり、無理に曲げたりすると剥がれや破損にが起こることがあります。
失敗した場合の対処法は?
気泡が入ってしまった場合
小さな気泡であれば、針で穴を開け、その上から熱を加えて圧着することで目立たなくできる場合があります。ただし、小さな穴が見える場合があります。完全に消すのは難しいでしょう。
また、大きな気泡やしわは、残念ながらやり直しがほとんど不可能です。
フィルムが詰まってしまった場合
無理に引き抜こうとせず、ラミネーターの逆転ボタンを試しててみましょう。
逆転ボタンがない場合やつまりが解消されない場合は、電源を切ります。
ラミネーターが完全に冷めてから、メーカーの指示に従ってカバーを開けて取り出すか、修理を依頼しましょう。
自分で修理しようと、無理に分解すると故障の原因になります。
剥がれてしまった場合
余白が少なすぎたか、ラミネート温度が低すぎた可能性が高いです。
部分的に剥がれただけであれば、その部分を再度ラミネーターに通して圧着できることもありますが、この場合は高確率で、再び剥がれてしまう可能性があります。
そのため、基本的には新しいフィルムで加工し直すのが最も確実です。
まとめ
ラミネート加工をするには、しっかりと準備をし、丁寧に作業することで、剝がれにくくすることが可能です。
ぜひこの記事を参考に、ラミネートで自分だけのオリジナルアイテム作りを楽しんでください。