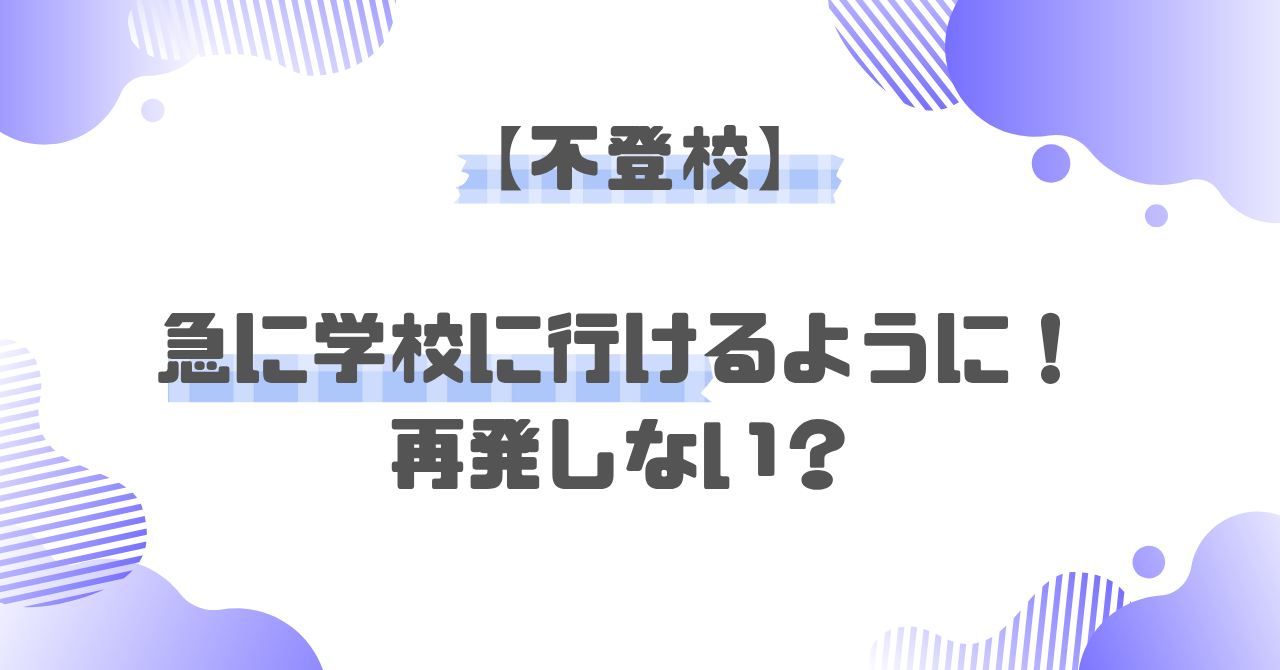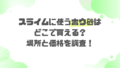「不登校だったのに、急に学校に行き始めた。どうして…?」
不登校の子どもがいると、このようなことも起こります。

実際に私の息子が急に登校し始めました。
しかし、再発しないか不安になりますよね。
この記事では、実体験での不登校の理由と登校し始めた「きっかけ」を書いていきます。
不登校の子供、急に学校に通い始めた!なぜ?
不登校の子どもが急に学校へと向かうと嬉しい半面、不安も押し寄せてきますよね。

無理して登校してないかな…?
何かを変えたわけではないのに、急に登校し始めると、不安になることもあります。
もしも、子供が無理をしていたら、もっと状況が悪化する可能性があります。
理由を調査してみました。
突然の登校、子供の心境に何が?
急に登校し始めた子供には、どのような心境の変化があるのでしょうか?
実際に、自分で気づいた「きっかけ」を子どもに聞いてみました。
スマホ・ゲーム没収ルール
普段「学校へ行けてないときは、スマホ・ゲームを取り上げる」とルールを決めました。
もちろん子供と話し合い、子供が納得した上で実行することにしました。
子供としては、どうしてもスマホ・ゲームをしたいので、それが原動力となり、学校へと向かう力になったようです。
しかし、子どもによっては無理に取り上げると危険な場合もあります。
子供の様子を見ながら、子供とルールを話し合ってスマホ・ゲームの取り上げは考えなければ危険なこともあるので、気をつけましょう。
友達関係の重要性
友達関係も、学校へ向かう力になった要因です。
不登校の間もスマホで友達と連絡はとっており、ゲームの話題で仲良くなっていました。
学校へ行くと、ゲームの話しを直接できるので、頑張って行こうという気持ちにつながったようです。
自己肯定感の高まり
最後に、自己肯定感が高まったのが一番の要因だと思います。
不登校の間は「俺なんか生きてる価値ない、死にたい…」などネガティブな発言ばかりでしたが、学校に行けるようになると、「これくらい大丈夫!」などと、ポジティブな発言が増えました。
自己肯定感高まり、学校に行くのが怖くなくなったんだと思います。

自己肯定感を高めるためには、家族間でコミュニケーションとり、子どもの意見を尊重するようにしました。
不登校の再発の可能性は?
不登校の再発が心配ですが、再発率はどの程度か調査しました。
不登校の再発率の平均は?
実は不登校の再発率は意外と高く、約70〜80%と言われています。
そのため、一度登校したからといって、完全に不登校を克服したと油断しないようにしましょう。

私の子供も、不登校→登校→不登校→登校と何度か繰り返しています。
その為、今でも油断できません。
不登校は再発しやすいため注意が必要
不登校は原因が根本から改善していないと再発する可能性があります。
とりあえず学校へ登校したとしても、やはりストレスを感じ、また不登校になってしまうことは珍しくありません。
私の息子も4年生の時に、学校に行けた時期がありました。
しかし、5年生に進級したとたんに、再び不登校になりました。
不登校の原因は何だったのか?
不登校の原因は、色々な事がからみあって起こります。
子どもによって様々な理由があるので、一概に「これ!」という理由は分かりません。
また、子供自身もハッキリとわからないことがあります。
しかし、不登校〜登校に変化していく様子を見ていると「これが原因だったのかな?」と心当たりがあることがありました。
体調不良
もともと、生まれつきお腹が弱く、下痢〜便秘を繰り返す体質でした。
初めのうちは学校に行きたくないから「お腹が痛い」って言ってるのかな?と思っていましたが、5年も腹痛を訴えていたので、体質なんだと思います。
もちろん、病院で検査もしましたが、原因は不明。
メンタルクリニックにも行きましたが…『これ!』と言った解決方法は見つけれませんでした。
一応、薬も処方されましたが、薬を飲むと逆にもっと悪化するということに….。
途方に暮れて諦めていましたが、色々試してみてある食べ物だと大丈夫なのが分かり、それを毎日朝食にすると体調整い、学校に行けるきっかけになりました。
学校生活でのストレス
また、ストレスが大きかったのもあります。
ストレスを受ける理由は、「大勢の人の中にいる時間が長いから苦痛」とのこと。
そのために私がしたことは、人間は誰しも「好きなことをしている間は、ストレスを感じにくい」ので、あえてショッピングモールなど人の多いところに、「子どもが好きな物を、買いに行く」ようにしました。
うちの場合は、それが合っていたようで、人混みに慣れることができました。
自己肯定感の低下
また、自己肯定感の低下は大きな要因でした。
不登校になった当初は、「できないこと」を指摘してましたが、専門家の方の意見などを聞くと、「できること」を指摘することのほうが、自己肯定感は上がるとのこと。

大人でも仕事で怒られてばっかりだと嫌になりますよね。
出来たことを褒めてから、「こうしたら、もっと良くなるよ」と伝えるようにしました。
子供自身の思いや気持ちを理解する
結論から言うと、一番大事なのは「子どもの気持ちを理解すること」です。
それ以上に大事なことはないと思います。
親子の絆があれば、子どもは安心できる環境が整います。
逆に親が否定ばかりしていると、子どもはずっと安心ができません。
むしろ信頼関係が崩れるので、親子関係が悪化する可能性があります。
子供の好きなことを理解する
子どもが好きなことを知っていますか?
親が興味を持つと、子どもは話してくれることが多いです。
もし、話してくれなくても、親から子供の世界に飛び込むと、子どもは心を開いてくれると思います。
子供の好きなことを否定しないで、興味を持って話しを聞いてあげてみてください。
本人の意志を尊重する
どんなことでも、本人の意思を尊重することが大事です。
学校に行きたくないなら「行かなくてもいい」という選択肢を与えてあげてください。

私は、行き渋りの段階で『学校は行かなきゃダメ』と言ってしまい、不登校につながりました。
子供の意思の尊重は、とても重要てす。
学校は、大人が勝手に決めたルールです。
その中で子どもが辛い思いをするなら、そこまでして「学校に行く選択肢」は重要ではありません。
もちろん尊重しすぎて、主導権を握られるのは別の話ですが、基本は子供の意見を尊重するべきだと思います。
親自身のサポートも!
とは言っても、不登校を支えるのは、親にとってもストレスが溜まります。
「仕事辞めなきゃいけない?」
「昼ごはん用意しなきゃ」
「勉強ついていけるのかな?」
など、親も知らず知らずの内に、少しづつ小さなストレスが溜まっていき、辛いのは事実です。

よく、「子どもが宿題をしない!」などで親子喧嘩したと聞きますが、「学校に行ってるだけでいいじゃん!!」と感じます。
不登校の親からすると、そんな話ですら、ストレスに感じますよね。。
適度に子供と距離感をとり、親自身も息抜きすることが大事です。
学校以外の居場所を
子供の為にも、親のためにも、学校以外の選択肢は大事だと思います。
まずは、専門家等に相談してみて、子どもがどのような状況なのか客観的に見ることが大事です。