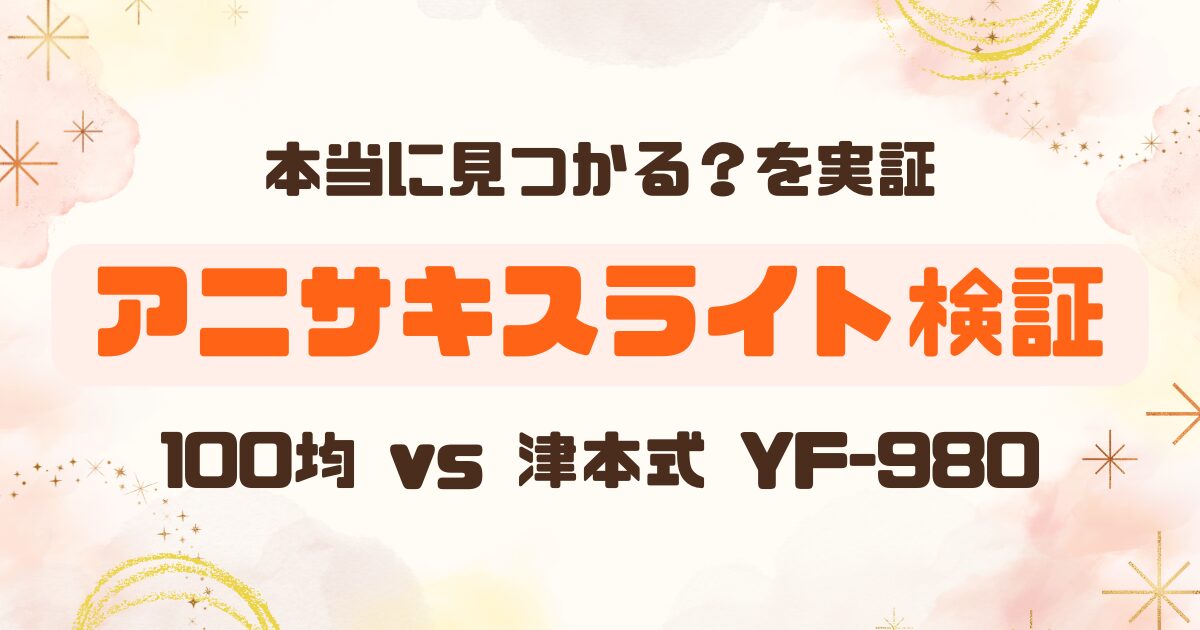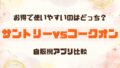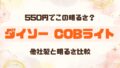生の魚を食べるときに、どうしても頭をよぎるのが「アニサキス」の存在です。
ニュースで食中毒の事例を目にすると、「うちの刺身は大丈夫かな?」と心配になる方も多いのではないでしょうか。お腹の激痛や嘔吐を引き起こすと聞けば、できることなら確実に避けたいものです。
そんな中で「ライトを当てればアニサキスが見えるらしい」という話を聞くと、つい試してみたくなりますよね。
でも実際のところ、ライトで照らして目視で確認することに、本当に意味があるのでしょうか。
そこで今回は、実際に 100均で売られているUVライト と、プロも使う 津本式アニサキスライト(YF-980) を用意して検証しました。どこまで違いがあるのか、体験談を交えて紹介します。
アニサキスライトの仕組みとは
そもそもアニサキスライトはなぜアニサキスが見えるのでしょうか?
アニサキスは、「リポフスチン」という蛍光物質がふくまれているため、紫外線(365nm前後)を当てることにより、白く光って見えます。しかし、この波長が合わなければ魚の身と馴染んで見づらいんです。
また、ライトを当てたからといって、全てのアニサキスが必ず見えるわけではありません。魚の身の中に入り込んでしまった場合は、見えづらくなるのでご注意を!
100均と津本式アニサキスライトの比較
100均のUVライトと津本式のアニサキスライトで比較検証してみました。
100均ライト(ハンディタイプ)のスペック
100均で「アニサキス用ライト」という商品は見つけることができませんでした。その為、レジン硬化用のUVライトを使用してみます。

今回はセリアで購入しました。
| ライト名 | 価格 | サイズ | 電源 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 100均UVライト(ハンディ) | 110円(税込) | 約9cm | 単4電池×3 | 青色LED、レジン硬化用、光量弱め |
100均UVライトをサバに照射してみた結果
こちらのサバに、UVライトを当てて反応を検証します。

サバの切り身に100均ライトを当ててみましたが、アニサキスらしき反応はほとんど確認できません。

光は出るものの暗めで、肉眼での判別は非常に厳しい印象です。
「浅い部分にいる寄生虫が見えることもある」と言われますが、光量も波長も不足しているため、家庭で目視するにはほぼ無理でした。
白い壁に当てても、薄暗い光なのがわかります。

津本式アニサキスライト(YF-980)のスペック
100均ライトではほとんど見えなかったため、次は津本式アニサキスライト YF-980を使用します。

| ライト名 | 価格 | サイズ | 電源 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 津本式アニサキスライト YF-980 | 約4~5,000円 | 約16cm | 単三電池×2 | 特定波長(可視光+UV中間)、肉眼でアニサキス浮き上がる |
このライトは、特定波長を発することでアニサキスが光を反射し、肉眼で浮き上がって見えるのが特徴です。
※ライトを直視すると危険なため、注意してください。
- 光源 紫外線LED
- 波長 365nm
- UV強度 約11mW/cm2
- 防水性 IPX7
魚をさばく際には、手が濡れているので、防水性能が付いてるのは実用的で嬉しいですね。
「Cタイプの充電式」もあります。
津本式ライトYF-980をサバに照射してみた結果
サバにライトを当てると、肉眼では全く見えなかった白い糸状のものが浮かび上がり、驚くほどはっきり確認できました。

子どもも「うわっ!」と声を上げるほどです。
今までテレビなどでは、見たことはありましたが、「本当にいるのかな?」と疑問に感じていました。しかし、実際に肉眼でアニサキスを見ることで、危険性をリアルに感じれたようです。
以下、拡大写真です。

さらにライトを手に当てるとほんのり温かさを感じ、床を照らすと細かなゴミまでくっきり見えるなど、光の強さと波長の違いを実感しました。ライトの色も100均と違うことが分かります。

アニサキスライトを選ぶときのコツ
アニサキスライトは波長や光量によって見えやすさが変わります。家庭用で使う場合は、紫外線365nm前後で出力の強いライトを選ぶと、アニサキスが浮かび上がりやすくなります。また、手持ちタイプか据え置き型か、電池式か充電式かも、使うシーンに合わせて選ぶと便利です。
今回使用した津本のアニサキスライトは電池式ですが、充電式のタイプもあります。
アニサキスライトの限界と食中毒を防ぐ確実な方法
100均ライトではほとんど見えませんが、津本式ライトを使うと肉眼で確認できます。ただし、魚の内部に潜り込んだアニサキスまでは見えないため、ライトはあくまで補助ツールです。
確実に食中毒を防ぐ方法はシンプルです。
- 70℃以上で加熱する
- −20℃で24時間以上冷凍する
どちらかを行えば、アニサキスは死滅します。刺身で食べる場合でも、リスクは残ることを覚えておきましょう。
まとめ│アニサキスライトは補助ツールとして意味がある
アニサキスライトは、ライトだけでは魚の内部に潜む寄生虫を全て見つけられるわけではありません。
しかし、津本式ライトを使えば肉眼では分からない寄生虫を浮かび上がらせることができ、リスクを減らす補助道具として役立ちます。
家庭で魚を扱う安心材料や、子どもと一緒に食の安全を学ぶ観察ツールとして活用できます。
頻繁に使用する場合は充電タイプが扱いやすく、購入は少し高めですが、経験としては十分価値があります。
刺身を食べる場合でも、70℃以上で加熱する、または−20℃で24時間以上冷凍するなどの方法と組み合わせることで、より確実にアニサキスのリスクを防げます。
魚を自分でさばく方であれば、一つあると便利なライトです。
▶ダイソーで手に入る釣り用品はこちらの記事で紹介しています。