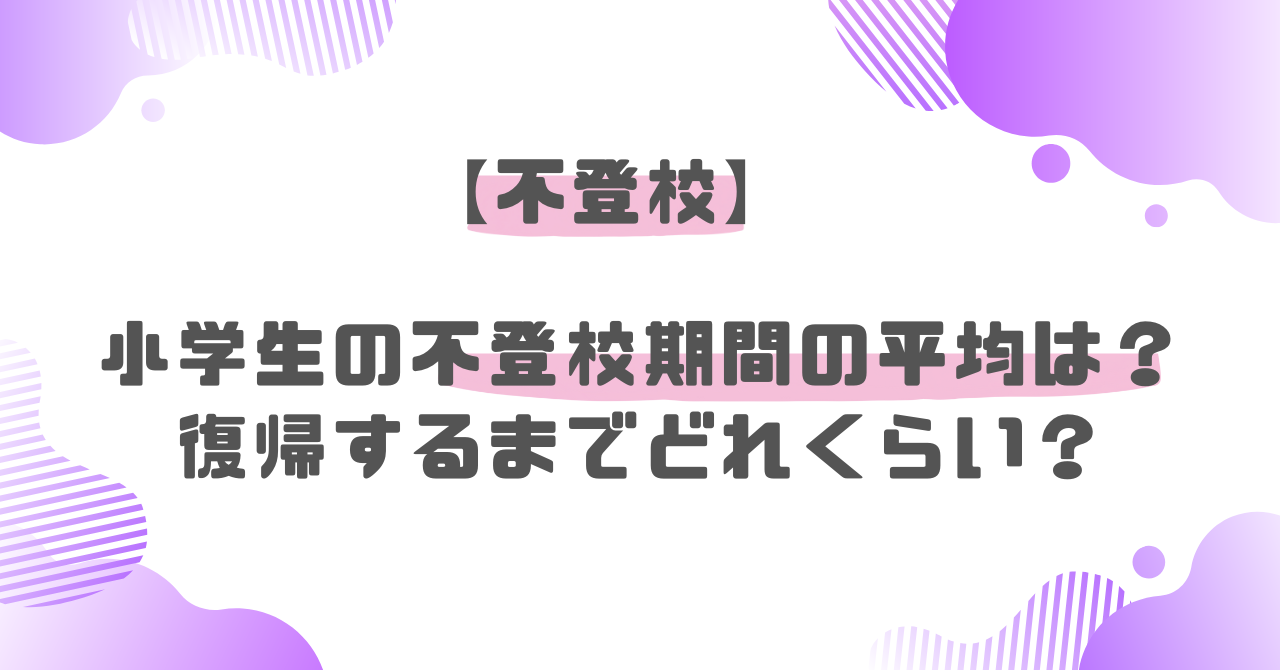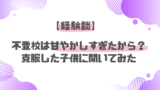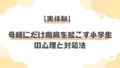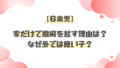「うちの子、学校に行きたがらない…」そんな状態が続いているならば、もしかしたら不登校なのかもしれません。
文部科学省の調査によると、小学生の不登校は年々増加傾向にあり、珍しいことではありません。
この記事では、小学生の不登校期間の平均や、復帰までの道のりについて、ご紹介します。
子供の状況に合わせながら焦らず、温かく見守っていくためのご参考になればと思います。
小学生の不登校についての基本情報
まずは、具体的にどのような状態だと不登校となるのか解説します。
不登校の定義とは?
不登校とは、様々な要因により、子どもが学校に行きたくても行けない、または行かない状態を指します。
文部科学省の定義では、
「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的な要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
引用元 文部科学省 不登校の現状に関する認識
とされています。
小学生における不登校の現状は?
小学生の不登校は、ここ数年増加傾向にあり、大きな社会問題となっていますね。
以下に、文部科学省の調査結果などを参考に、小学生の不登校の現状をまとめます。
- 令和5年度の小学生の不登校児童数は、130,370人で、過去最多を記録しました。
- 11年連続で不登校児は増加しており、深刻な状況が続いています。
- どれほど増加しているかと言うと、10年前と比べると5.4倍に増加しているんです。

数値を見ると、思ってた以上に増加傾向なのが分かりますね。
不登校の要因は、友達とののトラブル、勉強についていけない、先生との関係、家庭環境、本人の体調など様々な要因が絡み合って起きることが多いです。
不登校の平均期間
それでは、不登校の平均期間はどのくらいなんでしょうか?
一般的な平均期間は、3ヶ月から1年程度と言われています。
言われていますが、個々の状況や環境によって変わるので、この期間を過ぎたからと言って登校できるわけではありません。

私の息子は小学2年生から行きしぶりが始まり、小学生の終わりまで不登校でした。
子供によって変わるので、平均期間はあまり参考にならないかもしれません。
不登校克服までの道のり
不登校を克服するまでの道のりは、どのような段階を踏めばいいのか見てみましょう。
不登校克服のための7段階とは?
不登校を克服するには、7つの段階があるとされています。
それぞれの段階は、子供がどのような状態なのか知っておくと、子供も親も心が楽になると思います。
行きしぶり期
まず最初の行きしぶり期。子供が学校に行きたくないと感じる時期です。
朝学校に行きたがらなかったり、学校に行っても友達とコミュニケーションをとらなかったり、少し様子が変化します。これは、最初の兆候なので、子供の話をよく聞いてあげましょう。
葛藤期
次に、行きたくない気持ちが強くなる時期です。
ここで「甘えだ」と決めつけて、無理に行かせようとすると、子供はさらに嫌がります。
学校も親のこともどんどん嫌いになってしまうので、子供の気持ちを受け止めてあげましょう。
安定期
毎日学校に行かないことが普通になります。親からするとモヤモヤしますが、子供の気持ちは落ち着いてくる時期です。
もしこの時期に、子供が興味を持つことや好きなことを見つけてあげると、家で楽しみながら過ごせるようになるでしょう。
ムズムズ期
少しずつ外に出ることや、友達などと関わることに興味を持ち始める時期です。無理させずに、焦らず社会との関わりをサポートしてあげましょう。
リハビリ期
少しづつ、学校や勉強に対して意欲が戻ってくる時期。可能であれば、フリースクールや家庭教師を利用して、今までの遅れを取り戻すサポートを。
活動期
学校に戻る準備が出来た時期。学校側とも連携を取りながら、子供が安心して学校に通えるようにしてあげましょう。
復帰期
子供が学校に通い始める時期です。少しづつ通常の生活に戻るように助けてあげましょう。
復帰後は少し不安定だと思うので、サポートしてあげながら様子を見てあげてください。
回復期に向けた具体的な方法
私が感じた手ごたえのある具体的な方法です。
①親子のコミュニケーションを増やす
具体的には、親子間で一緒に出来ることを探しましょう。
私の場合は、子供がゲームやポケモンが好きだったので、同じソフトを購入して一緒にゲームをするようにしました。
子供も自分も一緒に楽しめると、前向きにコミュニケーションが取れますよね。
また、親がイライラしていると子供にも伝わるので、心にゆとりを持てるようにすると子供の様子も変わるかもしれません。

仕事や家事に追われていると、時間が過ぎるのがあっという間で、イライラしてしまいますよね。
仕事の時間を減らしたり、家事を手抜きしたりなど、親の負担が減ると自然と子供にも変化が出るかもしれません。
②小さなことでも感謝の言葉と褒める言葉を
次に、自己肯定感を高めるための方法です。
小さなことでもいいので、子供のいいことを探し、そのたびに褒めることです。
人間は褒められると嬉しいので(大人でも嬉しいですよね)その褒めが積み重なると、子供の自己肯定感が高まります。
また、感謝の言葉も同じく積み重なっていきますl
子供が出来た行動によっていい変化が起きたのであれば、すかさず褒めてあげましょう。
例えば、「電気を消してくれた」「お皿を下げてくれた」など親が思う当たり前の行動でも、それでも褒めてあげましょう。

私は、褒めるのが苦手でしたが、なんとかして褒めるところを見つけようとしているうちに、ゲーム感覚のように取り組めるようになりました。
③子供の好きなことの話を沢山聞いてあげる
子供は好きな話を沢山聞いてくれると、相手に信頼感を持ちます。
大人でも、同じ趣味の人と話すと楽しいですよね?そのイメージで、子供の話を聞いてあげます。
時間に限りがある人は、「〇時からご飯を作るから〇時まで聞くね。」と子供に伝えると意外と受け入れてくれます。
不登校から抜けだす兆しとは
外に遊びに行こうとしたり、ポジティブな意見が少しづつでてくると、よい兆候がでている可能性が高いです。
また、興味を失っていた活動に取り組もうとしようとします。例えば、スポーツや勉強などに前向きな姿勢が見えます。
積極性が出てくると、自分で「今日は1時間だけ学校に行く」など、出来そうな範囲でやり遂げようと頑張り始めます。
学校との連携
不登校の間も、学校と連携をして、子供がいつでも学校に戻りやすい雰囲気を作ってあげることが大事です。
先生との連携の重要性
先生と信頼関係がないと、行きたい気持ちになっても行きにくくなりがちです。
せっかく行きたい気持ちになっても、行きにくいと足が遠のいてしまうので、放課後にプリントだけでももらうなど、先生との関係性を絶たない様に気を付けてあげることが大事です。
フリースクールやディサービスの活用
不登校の間は社会生活が絶たれてしまうので、学校以外で参加できそうならば、フリースクールやディサービスなどを活用するのもいいかと思います。
子供によっては、学校以外だと何故かすんなり行けたりすることもあるみたいなので、子供の様子を見ながら試してみる価値はあります。
子供が元気を取り戻すためには?
不登校の克服には、子供自身が元気を取り戻さなければ難しいです。
子供の元気を取り戻すには、「好きなことを見つけてあげる!」です。
なんでもいいと思います。ゲームでも動画でもメイクでも動物でも何でもいいので、子供が興味を示す「何か」を探しましょう。
好きなことをしているときはポジティブになれるので、自然と生きる活力が湧いてきます。
そして、好きなことがあるならば、親も褒めやすくもなるので、自己肯定感も上がりやすくなります。
不登校からの復帰
子供のやる気が高まってきて、自ら外の世界と関わろうとし始めたら、復帰の時期が来ているのかもしれません。
復帰が出来そうな状況になったら、少しづつ学校へ向けるようにサポートしてあげましょう。
朝から最後の時間まで学校に行けるのが理想ですが、復帰したばかりだとまだ不安定なこともあると思うので、一日1時間だけなど少しづつでも学校へ向かうことが出来れば、褒めてあげましょう。
学校に行けない状態から、行けることになっただけでも凄いので、おおらかな気持ちでいることが大事です。
たとえ、一日くらい行けなくても「昨日少し行けたからいいんじゃない?」など前向きな言葉をかけてあげることが大事です。
ネガティブな言葉を伝えてしまうと、子供も親もどんどんネガティブ思考になるので、ポジティブな言葉を選んで口に出すと、考え方も前向きに変われるチャンスだと思いますよ。
しかし、親だけだと「子供の好きなことが見つからない」「褒めるタイミングが分からない」とつまずくことがあると思います。
不登校専門オンライン個別指導のティントルは、子供だけではなく親の相談にも乗ってもらえるので、普段一人で抱え込んでることを相談することが出来ます。
1人で抱え込むのは辛いと思うので、どこかにはけ口があると少しはストレスが発散できると思います。
不登校心理士の資格を持ったスタッフがサポートしてくれるのも心強いですよ。
また勉強だけではなく、子供が外との関わりを持てる環境を提供してくれるので「人と話すことから挑戦したい」などの目標でも大丈夫です。
なので、好きなゲームの話をしてもいいですし、子供に合わせたレベルの勉強を教えてもらえます。
家に一人でこもってばかりだと、社会に取り残されたようで、親も心配になってしまいますよね。
体験は無料ですので、一歩踏み出すきっかけとしてチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
きっかけを作る!【ティントル 不登校専門オンライン個別指導】環境が少し変わると、何か新しい発見があるかもしれません。