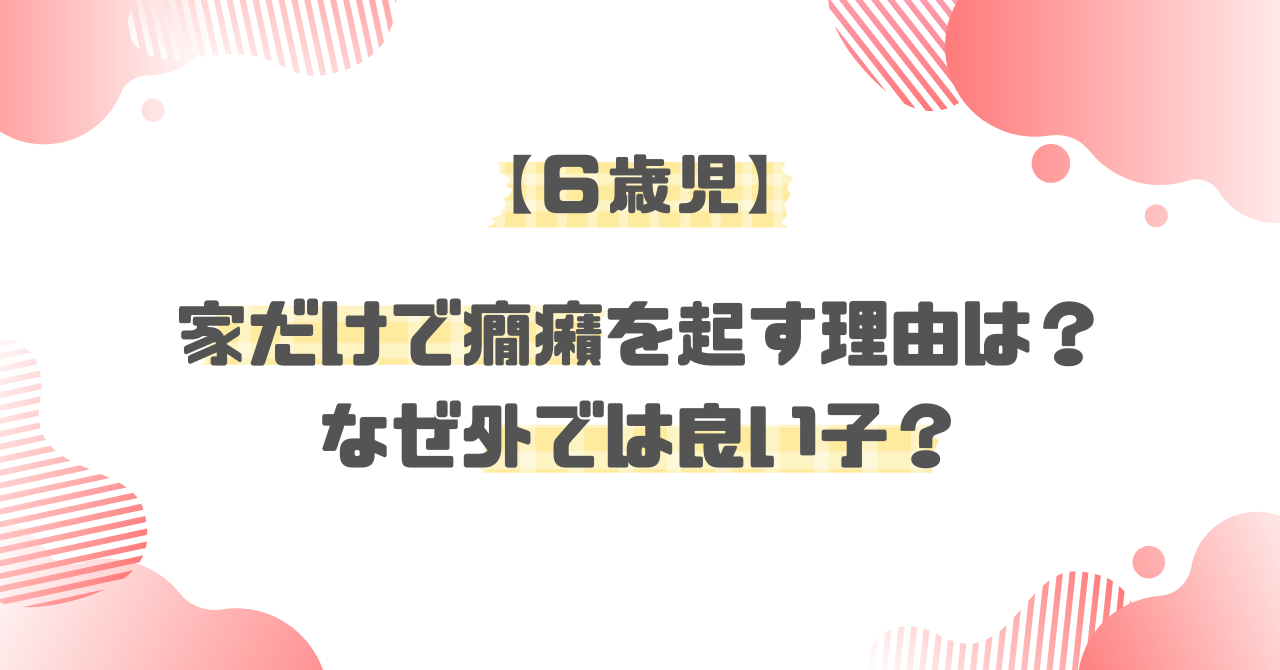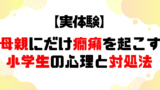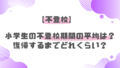6歳でも癇癪を起すと、心配になりますよね。
「もう小学生なのにだいじょうぶなのかな…?」「ほかの子は癇癪起さないのにうちの子だけ…」など不安になることもあるかと思います。

私の娘は4年前から癇癪を起しています。
実体験に基づいた記事です。ご参考にしてください。
子どもの癇癪とは何か?
子供の癇癪とは、自分の要求が通らないなど、自分が納得できないことがあると怒りスイッチが入ってしまい、自分でも止められない状態になることです。
止めなくてはいけないことは理解していても、止められないので、癇癪が起こってしまったら落ち着くまで待つしかありません。
泣き叫ぶ、暴れる、叩く、蹴るなど様々な行動をします。
家だけで癇癪を起こすのはなぜ
家は心の落ち着く場所です。
そして、心の許せる家族がいる場所ですので、ありのままの自分で入れます。
特に、母親は子供にとって特別な存在。自分を受け止めてほしい存在です。
学校との態度の違い
「学校では良い子なのに、なぜ家でだけ癇癪をおこすの?」と思う方もいると思います。
なぜなら、学校は緊張感をもって過ごす場所だから、癇癪を起しにくいです。
家でだけ癇癪を起すということは、それだけ家で安心しているんだと思います。

私の娘は、学校では癇癪を起しません。
私がいる時のみなので、先生や旦那は癇癪の状態を知らず…
私一人だけで戦う日々です。
癇癪を起こす子供の発達障害は関係ある?
癇癪は、発達障害とも関連性はあります。
しかし、癇癪持ちだからと言って発達障害というわけではありません。
発達障害は、病院で検査を受けなければ診断されません。
もし、気になるのであれば、検査をしている病院へ相談してみると、いいと思います。

まずは、子供の特性を知り、それに合わせた方法を考えるといいと思います。
母親にだけ癇癪を起こす理由
子供は母親といると安心します。癇癪を起こすことで、子供は感情出してストレスを発散させています。
ただ、日常的に母親が一貫した対応を取らないなどの行動をしていると、子供は混乱することがあります。
その為「どうすればいいの?」と不安になり癇癪を起こしやすくなります。
家庭内での親子関係
子供と一緒にコミュニケーションをとり、何かを共有することが出来ると安心感と信頼感が高まります。また、子供への共感や理解も大事です。
子供の話をよく聞いてあげると、絆が深まります。
子供が好きなアニメを見たり、一緒にお菓子を作ったり、一緒に工作したり、何か共有できる思い出があると子供からも寄り添ってくれると思います。
癇癪は甘えや依存?
甘えや依存の可能性のありますが、それだけではありません。
自分の感情を表現したり、親にかまってもらいたいという思いから癇癪につながることもあります。

私の娘も、「私が絶対に困るタイミング」で癇癪を起してるように感じました。
家庭環境が及ぼす影響は
家庭環境は子供の人生のベースになります。
親がイライラしていると、子供もストレスを抱えますが、親がニコニコしていると子供もニコニコになります。
また、親子間のコミュニケーションをとっている家庭は、子供のコミュニケーション能力のスキルアップにもなります。
コミュニケーション能力があると、友人関係や学校生活でも役立ちます。
家庭内で会話がないと、子供は何を話せばいいのか学べず、一人の世界にこもってしまう可能性もあります。

私自身、幼少期は「会話がない家庭」で育ったので、コミュニケーション能力が成長せず、社会に出てから困りました。今でも苦手意識はあります。
子どもが抱えるストレス
子供は何気にストレスを感じています。
特に、特性のある子供だとなおさらです。
例えば、切り替えが不得意な子供は、学校の授業だけでもストレスがたまるハズです。
時間ごとに区切られ、自分の満足できるところまで勉強できないと、それはストレスですよね。
その小さなストレスが積み重なって大きな癇癪につながることも少なくないようです。
癇癪を理解しよう
子供の発達や心理面はとても大事です。癇癪は、急激な怒りの発作のようなことを指します。止めたくても止められません。
大人に何かを伝える時に、語彙力が足らず感情がうまく表現できない時にも癇癪が起きます。
大人と子供だとやはり感じ方や受け取り方など少しの違いが出ると思うのですが、それが上手に伝わらないのがもどかしいようです。

この点は、色々な言葉を覚えて成長を待ちましょう。
また、普段と違った行動をしてストレスを受けると癇癪につながる可能性もあります。
発表会や運動会などのイベントの前後は、通常よりも癇癪が起こりやすい時期です。
癇癪対策と家での対応方法
癇癪が起きた時にどうすればいいのか分からないですよね。子供が6歳の時に実際に体験した方法をご紹介します。
私が感じた効果的な癇癪対策【即効性】
あまりオススメはしませんが、「どうしても今すぐ止めたい!」というときもありますよね。
そんな時は、癇癪中に「聞きなれない音」など普段耳にしない音や場面を与えました。
なかなか自分で試すことは難しいのですが、例えば地震アラームの音とか、インターホンが鳴るとか、家の前をダンプカーが通るとか、普段の生活では耳にしない少しびっくりするような音だと、そちらに気が向いて収まることが多いと感じました。
何か音源を探しておいて、癇癪が起きた時にならすと一時的に収まるかもしれません。
しかし、子供が怖がることもありますし、何度も繰り返すと効果はなくなるので、あくまでその場しのぎの対処法です。
私が感じた効果的な癇癪対策【長期的】
やはり、長期的に癇癪と向き合うのが一番の解決策です。
私が色々な専門家の方から聞いて、実践したのは「子供とのコミュニケーションを増やす」です。
共働きだと、なかなか時間をとるのが難しくなりますが、根本から癇癪を直すには、コミュニケーションが大事なんだと気づかされました。
仕事で時間に追われて「早くして!」と言っていた時よりも、仕事を休んでいる間の方が私自身の心にも余裕があるので、「癇癪起きたら学校やすませよう!」と気軽に考えるようになれました。
そうすると、自分自身も子供とよく向き合えるようになり、そうすると子供も私に優しくしてくれるようになりました。
もちろん、子供によっては生まれつきの子もいますし、すべての原因がコミュニケーションで直るわけではありませんが、試していただきたい方法の一つです。
日常的な対応の仕方
常に心に余裕を持つことを心掛けると、家族みんな笑顔になれる近道だと思います。
現実はなかなか難しいものがありますが、嘘でも笑顔を作っていると、本当に楽しい気持ちになると心理学的にも言われています。
私自身も、一度立ち止まりました。そのタイミングで、子供の癇癪がウソのように収まりました。
まだ時々「癇癪起きるかな?」と感じる場面もありますが、一番ひどい時よりも8割くらいは収まっています。
何を変えたのか?と聞かれると、やはり仕事を一時的に休み立ち止まり、心に余裕をもたせたからかな?と感じます。
仕事をしないと収入面では凄く心配ですが、それよりも子供の心の方が大事なのかもしれないと、今更ながら気づきました。
癇癪がひどい場合は、保護者も一度立ち止まって子供と向き合ってみると新しい道が開けるかもしれません。