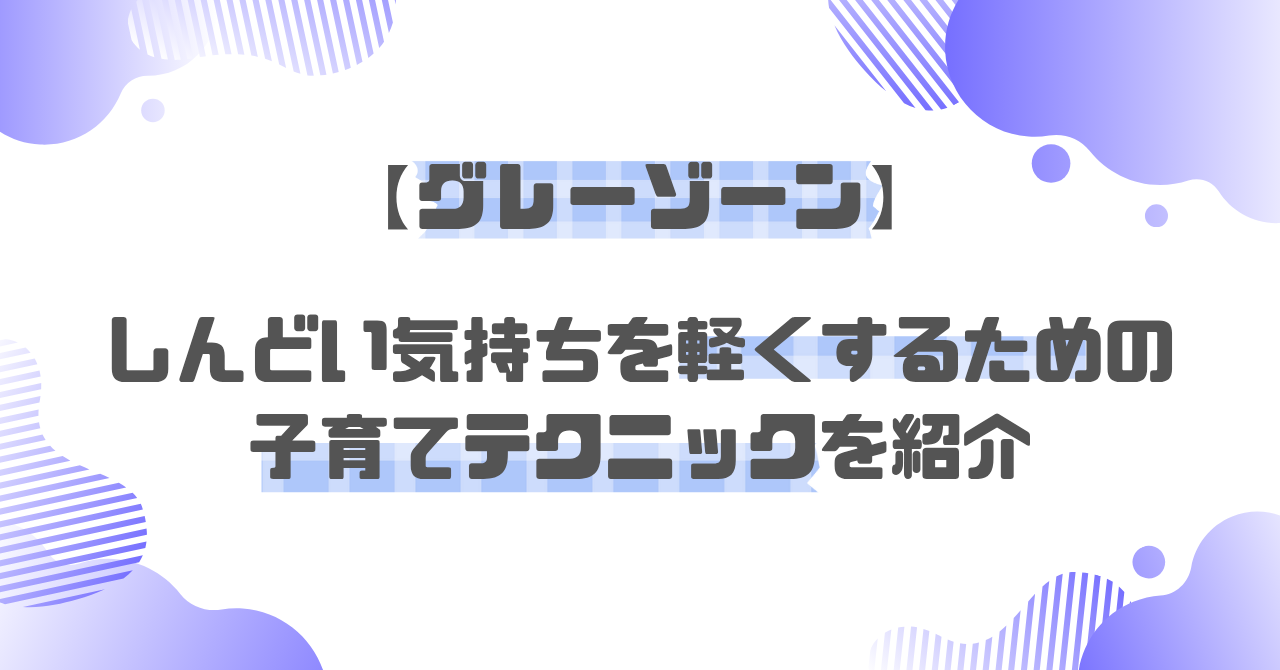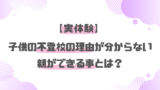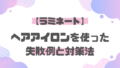「もしかして、うちの子の発達障害のグレーゾーンかも…」
そう感じながらも、はっきりとした診断が下りず、一人で悩んでいませんか?
グレーゾーンの子供の育児は、周りからの理解が得られにくいので、不安や孤独を抱えやすいです。

なかなか気軽に相談できることでもありません。
しかし、グレゾーンと言っても幅は広いので、子どもにあった対応方法を身につけることが大事です。
この記事を読んで、少しでもお子さんの才能を伸ばせると「しんどい」気持ちも軽くすることができます。
この記事では、グレーゾーンのお子さんの特性を理解し、具体的な子育てテクニックをご紹介します。ぜひ参考に、お子さんとご自身に合った方法を見つけてみてください。

私の息子はグレーゾーンです。
病院で検査を受けました。この記事は実体験での「しんどさの克服方法」です。
グレーゾーンの子育てとは?
グレーゾーンの定義とは
発達障害グレーゾーンとは、いくつかの特性や症状が見られるが、発達障害の診断基準を完全には満たさないため、正式な診断には至らない場合のことを指します。
グレーゾーンの子どもたちは、生活や勉強でしんどさを感じることが多いですが、正式な診断がつかないため、なかなか周囲の理解や支援を得るのが難しかったりします。
発達障害とグレーゾーンの違い
発達障害とは
発達障害は、医師や専門家による診断基準がしっかりと定められており、これの基準に基づいて診断されます。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)などが発達障害にあります。
社会的なコミュニケーションの困難や注意力の欠如、多動性など、具体的な症状が見られます。
発達障害の診断を受けると、専門的な支援やサポートが受けやすくなります。
教育の場や病院での支援プランなどが提供されます。また、自治体によっては手帳を交付しているところも。手帳があると割引などをしてくれる施設もあるので、金銭的にも援助されます。
グレーゾーン
一方グレーゾーンとは、明確な診断基準には該当しません。しかし、いくつかの発達障害の特性が見られる状態を指します。それでも診断には至らないため、正式な発達障害とは認められないことが多いです。
また、グレーゾーンの子供は、特定の困難を抱えていますが、症状が軽度です。
その為、周囲の人が気づきにくく普段の生活や勉強などで、問題が表面化しにくいことも。
さらにグレーゾーンは診断がないため、公式な支援やサポートを受けることが難しい場合があります。
その子の特性に合わせた周囲の理解と柔軟な対応が求められます。
グレーゾーン育児がしんどい理由
周囲の理解と支援不足
一番しんどいと感じる部分は、診断がないため「周囲の理解や専門的な支援が得にくい」という点です。
診断がなければ手帳などはないので、通常の人と変わらない生活になります。
そうなると、通常の人には簡単なことでも、グレーゾーンの人には困難なことが沢山出てきます。
しかし、診断はないので、周りからは「何でこんな簡単なこと出来ないの?」と思われることがあります。本人は自己肯定感が下がり、精神的に凄くしんどい状態になります。
そして、それをフォローする親もしんどいです。
親のストレス
周囲のフォローや何より、子供自身のフォローをしなければいけないので、疲れやすいです。
通常の人が出来ることが出来ないので、自己肯定感が下がりがちなため、フォローするのが大変です。
子どもの困難
子供自身が一番しんどい状況です。学校や社会での適応しづらく、本人は「何で自分だけ出来ないんだろう?」と悩んでしまうことも。
将来への不安
明確な診断がないため、将来の見通しが難しくなります。一般社会で適応できるのか不安になります。
対応の難しさ
子どもの状態が日々変化するため、一貫した対応が難しいです。
その日の子供の状態に合わせて、対応してあげなければなりません。
しんどい気持ちを軽くする子育てテクニック
グレーゾーンの育児はしんどいですが、その中でも日常生活でできる工夫と対策を紹介します。
長期的な方法になりますし、子供によっては合わないこともありますが、試す価値はあります。お子さんと一緒に、長い目で見て試してください。
視覚的なサポート
「スケジュール表」や「チェックリスト」など目で見て確認できる工夫を
視覚的な情報は子どもにとって分かりやすいようです。特に目で見るのが得意な子供には視覚的なサポートをしてあげるといいでしょう。
一日の見通しが立たなくて不安になる子供もいるので、毎日のスケジュールを示す表や、やることリストなどを作ると、一目で分かり効果があります。
図や絵を活用
文字だけだと、目で見ても伝わりにくいことがあるので、図や絵も取り入れると、より伝わりやすくなります。
また、キャラクターなどのシールを貼ってあげたりするだけでも、子供のテンションはあがります。
時間が把握できないときはタイマーを
「〇時になったら片づけてね」と言ってもなかなか片づけられないときは、残り時間が分かるタイマーを使用すると、「あとどのくらい時間があるか?」が可視化できるので分かりやすくなります。
ルーティンを決める
毎日のルーティン決める
毎日の作業を一定の順番で行うことで、子どもが「これの次はこれだ!」と分かりやすく、安心感を持ちやすくなります。
余裕のあるスケジュール
余裕を持ったスケジュールを立てることで、急な変化に対応しやすくなります。親も子供も焦らずに済むので、イライラも少なくなります。余裕は大事です。
環境を整える
静かな場所の用意
勉強や集中が必要な時は、静かで落ち着いた場所に連れて行ってあげると落ち着くことも。
整理整頓
物の位置を決めておき、整理整頓されていると、子どもが自分自身で物を見つけやすくなります。
片づける場所が分からない場合は、引き出しなどに物の写真を貼り付けておくと、目で見て判断できます。
ポジティブな声掛け
小さな成功を褒める
子どもの小さな成功や努力を見つけてあげましょう。小さなことを褒め続けると、それが積み重なることで、自己肯定感を高めるパワーに変わります。
目に見える形での評価
シールやスタンプなど、目で見て頑張ったことを確認できる方法だと、子供も理解しやすいです。
ストレスの軽減
毎日頑張ると疲れてしまうので、時にはだらけたり息抜きをしてストレスから解放されましょう!疲れているとイライラしてしまうので、休むのは大事です。人間ですから、たまには手抜きも必要です。
親自身のサポート
情報収集
グレーゾーンに関する情報を集めることで、適切な対策や支援を見つけやすくなります。
支援グループに参加する
同じような経験をしている親との交流や、専門家のアドバイスを受けることで、どのようにすればいいのか対処法などの情報も聞けることもあります。
同じ悩みを持つ親同士だと、しんどさを分かり合えるので、ストレスも軽減されます。
子どもの特性を理解する
グレーゾーンの子どもの特性を理解することは、親や教育者にはとても大事なことです。
子どもの好きなことを活かす
まずは、子供の好きなことを探してみましょう。普段の生活の中で何に興味を持っているのか?
何をしているとき夢中になっているのか?そのような視点でじっくり観察してみましょう。
子供の好きなことが見つかるはずです。
子供の好きなことが分からない場合は、親の方から色々な体験をさせてあげると見つかることもあります。
好きなことが見つかったら、好きなことを絡めると社会との関わりや、勉強につなげたりするのに役立ちます。
できないことを認めてあげる
グレーゾーンの子供は、通常の子供より出来ないことがあります。
出来なかった時は、「なんでできないの?」と否定的な声掛けでは自己肯定感が下がってしまうのでNG。
「一番初めはできなくても大丈夫だよ」「今回できなかったら、次はこうしてみるとできるかもよ?」など、次につながるポジティブな声掛けすると、子供も否定されないので、次からは前向きに取り組むことが出来るようになります。

私も、「失敗しないで成功するなんて無理だから、失敗して次どうするかの方が大事だよ」と声掛けするようにしたら、少しづつですが子供もポジティブな考え方に変わっていきました。
子どものペースに合わせてあげる
グレーゾーンの子供は、その子によってペースが異なります。
中には、切り替えが難しい子もいるので、子供を中心としたペースに合わせてあげましょう。
グレーゾーンの子どもを持つ親の悩み
金銭的な支援が受けにくい
グレーゾーンだと、正式な発達障害の診断がないので、金銭的な支援を受けにくいことがあります。
金銭的な支援が受けにくいのは、親にとって非常に困難です。

母親が子供のサポートで働けなくことがあるので、正直厳しいです。
自治体によっては、支援してくれるかもしれないので、まずは相談してみてください。
周囲との関係
グレーゾーンは、なかなか理解を得にくいことがあります。
親自身の周囲の人になんと伝えればいいのか?子供の友達になんと説明すればいいのか?悩むことは多々あります。
しかし、子供の状態があいまいに伝わっていると、逆に周りの人を遠ざけることになってしまうかもしれません。
周囲の人や教育者とオープンに話し合い透明性を持つことで、理解と協力が得やすくなります。
また、自治体によって判断基準が異なると思いますが、支援級などに入るのも子供の為にはいいのかもしれません。
教育に関する心配の対処法
教育の心配もつきませんよね。
まず学習の遅れは心配な場合は、オンライン学習ツールや塾などを活用しましょう。
オンライン学習ツールには、グレーゾーンや発達障害の子でも受けれるサービスがあります。
無料体験を数社受けてみて、子供に合ったオンライン学習ツールが見つかると、勉強がはかどるかと思います。
また学校での適応も心配です。先生やスクールカウンセラーと連携し、子供が学校で安心できる環境を整えましょう。
次に将来の進路の不安。対処法としては、出来るだけ早く子供の興味や特技を見つけてあげましょう。子供が興味を持っていることから、将来の進路が見えてくることがあります。キャリアカウンセリングを受けるとどのような道筋で進路を決めていけばいいのか、めどが立ちやすくなります。
学校では支援を受けれる?
担任の先生に相談してみると、通常級でも「座席の配置や授業中のサポート」などはしてくれることがあります。

私の息子の担任の先生は、ノートを書くのが遅い息子に対して、「書く必要がある所だけ青い線で囲う」という方法を提案してくれました。
しかし、通常級だと1人の先生で、数十人の子供のサポートをしてあげなければいけないので、サポートにも限界があるかと思います。
通級指導教室がある学校では、個別の指導や特別な支援を受けることができるので、どのような方法が子供に適しているのか、一度相談してみるといいかと思います。
子どもに合った環境を探す
学校が難しいようならば、学校以外の環境を探してあげましょう。
- フリースクール
- オンライン学習ツール
- 教育支援センター
- 習い事
など、子供が自己肯定感を落とさずに、楽しく頑張れそうな環境を探してあげることが大事です。
実体験から学ぶ失敗と成功
私の息子は、病院で検査を受けたところグレーゾーンでした。
初めは、「グレーゾーン?でも発達障害ではないなら、通常の子供と変わらないんじゃないの?」と安易な考えでなんの対処もしていませんでした。
その安易な考えの結果、5年間の不登校につながりました。
グレーゾーンだから不登校になった訳ではありませんが、私が対処しなかったことは要因の一つだったと思います。

今考えると、反省点が多すぎて書ききれません…。
同じように悩んでいる方は、参考にしてみてください。
今振り返ってみて、失敗したことと成功だったことを書き記してみました。
失敗だと感じたこと
子供のペースに合わせてあげなかった
一番大きな反省点はこれです。
家事や仕事、下の子の世話に追われて、予定通りに終わらないことにイライラすることも。
子どものペースではなく、大人のペースに合わせるようにしてしまっていた。
また、子供のペースでは難しい宿題も「やらなきゃいけないもの」と教え、宿題をさせるようにしていた。
褒めが足りなかった
出来ないことばかりに注目してしまい、出来ないことを注意していた。
「〇歳なら出来るのが当たり前」という考えに縛られていて、褒めることが少なかった。
コミュニケーション不足
子供の好きなこと、嫌いなことをしっかり理解してあげられていなかった。
時間がないということに追われてばかりで、自分メインの考え方しかできなかった。
子供ともっといろんな体験や情報などを共有するべきだった。
失敗から学んだ成功
子どもの好きなことを見つけることが出来た
子供が自ら「プログラミングをやってみたい」と申し出てきたので、すぐに体験させることにした。
3年ほど前から始めて、今も継続中。タイピングが速くなる度に、すごく嬉しそうな表情を見せています。

「好きこそものの上手なれ」って本当なんだなと実感しました。
好きなことだと、子供の吸収率は早いですね。
とにかく褒めまくる
グレーゾーンだと他のことが平均よりも下回っているので、なかなか褒めどころが見つからないこともありますが、小さなことでも褒めるようにしています。
- 学校へ行けた
- 学校でノートが書けた
- 給食が食べれた
- 昨日より早起きできた
など、息子は小学校高学年ですが「そんなこと?」と思うような小さなことでも、褒めるようにしています。
それのおかげなのか、子供の自己肯定感が高まり、いまではポジティブ思考になりました。

母親の言葉って、子供に凄く影響力があります。
まとめ
グレーゾーンの育児は、なかなかしんどいものがあります。
しかし、子供の特性を理解してサポートしてあげると、子供は安心して過ごせます。
その子によって得意不得意はかわるので、何か得意なことや居場所が見つかると安心して過ごせると思います。

子育てに正解はありません。
子どもに寄り添って、親子で一緒に楽しく過ごせるといいですよね。