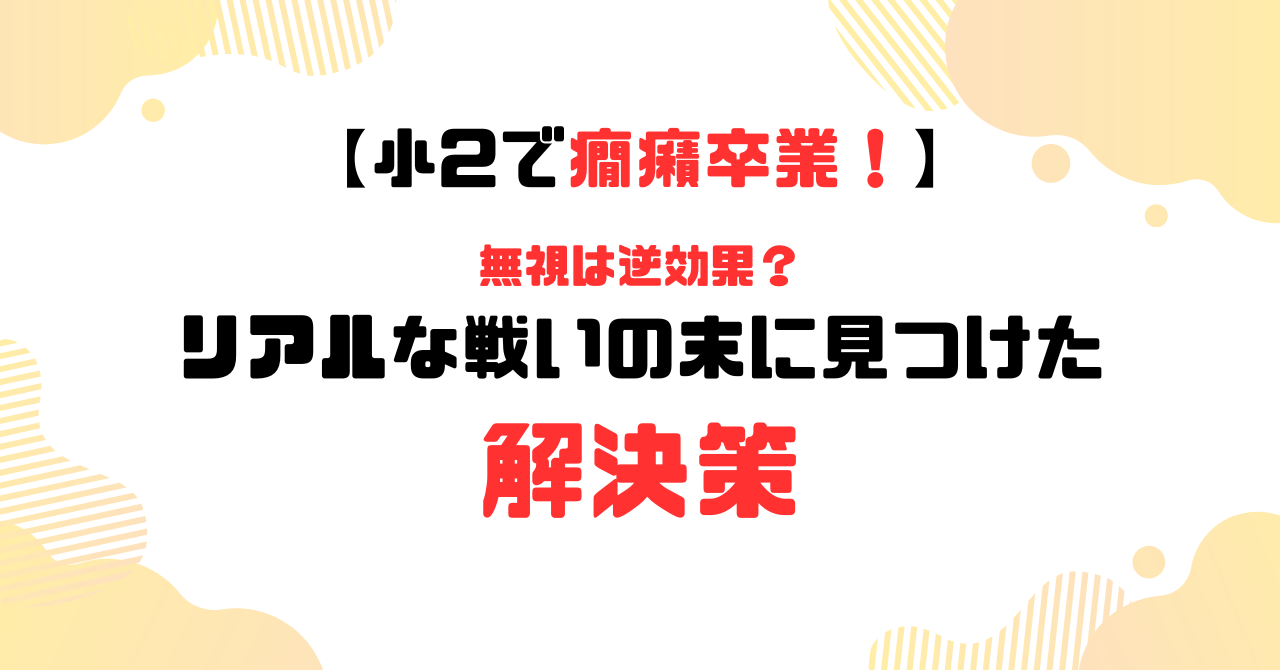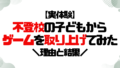「癇癪が始まると手に負えない⋯」
「無視するわけにもいかないけど、向き合うのも辛い⋯」
そんなふうに、子どもの癇癪に日々悩み、心身ともに限界を感じていませんか?
私の小学校低学年の娘も、1年前まで癇癪がひどかったんです。様々な方法を試しては失敗を繰り返し、正直「もう打つ手なし…」と諦めかけたこともありました。
特に、「癇癪は無視が効果的」というアドバイスを実際に試してみた結果は、なかなかしんどいものでした。
この記事では、娘とのリアルな癇癪との戦いと、試行錯誤の記録を包み隠さずお伝えします。
癇癪との向き合い方が、少しでも楽になるきっかけとなれば幸いです。
はじめに~娘の癇癪歴4年~
まず初めに、私の娘の癇癪レベルを説明します。
彼女の癇癪は、年中ごろから急に始まり、ほぼ毎日のペースで癇癪を起こすようになりました。その激しさは、正直、想像を絶するものでした。
特に、保育園のお迎えの時や、児童会館のお迎えの時に発動することがほとんどでした。
一度発動すると短くて1時間。長いときで3時間くらいです。それを一日のうちに2~3回発動することもありました。頻度としてはかなり多い方だと思います。
癇癪を理解する

まずは、癇癪の基本をご説明します。
癇癪って何?
「癇癪」とは、子どもが自分の感情をうまくコントロールできず、激しい怒りや不満を爆発させる行動を指します。
発達段階において、言葉で気持ちを表現するのが難しかったり、欲求と現実とのギャップに戸惑ったりすることで生じることが多いとされています。
乳幼児期から小学校低学年頃までに見られることが一般的です。
小1娘の癇癪の特徴
私の娘の場合、癇癪を起こすきっかけは「自分のペースを崩されること」が主な引き金でした。
例えば、遊びを中断させられたり、思ったようにいかなかったり、予定外のことが起きたりすると、一気に感情が爆発します。
もちろんそれ以外にも彼女なりの「地雷」がたくさんあるので、正直、毎日ビクビクしながら生活していました。
また、癇癪が起きると、ただ泣き叫ぶだけでなく、「叩く」「蹴る」「つねる」「噛み付く」と、ありとあらゆる手段で暴れるタイプ。
親として、どうすればこの嵐を乗り切れるのか、本当に悩んでいました。
癇癪の裏にある子どもの気持ち
癇癪を起こすとき、子どもの気持ちはどうなんでしょうか?
私も常に疑問でした。
実際に癇癪が落ち着いてから、娘に「どうして暴れたの?」「どうして止められなかったの?」と聞いてみたことがあります。
何度か聞いたことはありますが、そのたびに「自分でもダメだってわかってるけど、止められない⋯」と、また大泣きしてしまうんです。
この言葉を聞いて感じたのですが、癇癪は子ども自身もコントロールできない感情の暴走であり、決して「ワガママ」や「親への甘え」だけではないのだと。
むしろ、一番苦しんでいるのは、感情に飲み込まれている子ども自身なのかもしれません。
癇癪の時に試したことと結果
「癇癪には無視がいい」「寄り添うべき」「いや、時には親も毅然と…」様々な情報があります。
また、専門家の人によってもアドバイスが違うことがあります。
子どもによってどれが当てはまるかは試してみないと分からないので、親として藁にもすがる思いで試した3つの方法と、そのリアルな結果をお伝えします。
①「無視」は効果的?体当たりで検証!
癇癪の対策の中で「無視するのが効果的」というアドバイスもあります。
なぜなら、癇癪持ちの子のなかには「癇癪を起すと親が反応してくれるから繰り返す」という子どもがいるみたいなんです。
そこで、私もシンプルに無視してみました。
騒がれても、どれだけ騒がれて叩かれても蹴られても、徹底的に無視!するつもりでしたが⋯。
癇癪が起きると1時間はざらにかかる娘の場合、さすがにこちらの体力が先につきました。
無視してもやはり攻撃が止むわけではなく、なんならこちらが無防備な分、向こうの攻撃力が上がってる気がするほどでした。
結果、私の体には全身に青痣ができました。
そのうえ、子供の癇癪には全く効果なく、親がただダメージを受けただけでした。
私たちにとっては、この方法は精神的にも肉体的にも非常に辛いものでした。
②「対峙」と「寄り添い」は逆効果?
次に、よく専門家や育児書で勧められる「真剣に向き合うパターン」を試しました。
癇癪を起こしたときに、「そうだね。〇〇が嫌だったよね。」「イライラするよね。」など、共感し寄り添う言葉がけをしてみました。
しかし、娘の場合はこれもノーダメージ。
なんなら「うるさい!」「ダマレ!」と罵詈雑言を浴びるという、精神的なダメージ付きです。
結果、寄り添うだけ無駄。
こちらが暴言で精神的なダメージを受けるだけでした。
③私も癇癪を起してみたら…
最後に、「押してダメなら引いてみろ」ならぬ、「目には目を!歯には歯を!」の精神で、私も癇癪を起こしてみました。

親として、どうかな?とも悩みましたが、まずはチャレンジ。
子どもの癇癪と同じレベルで、泣き叫び暴れます。
叩かれた位置も、同じ力加減で叩きます。
(※自分が他の人にどの程度痛みを与えているのか?を理解できることを期待してやっております。ただの暴力ではないのでご理解ください。)
結果、どちらとも痛い目をみる。
そのうえ、子どもの癇癪が収まることはありませんでした。
どんだけ痛くても、子どもは立ち向かってくるので、火に油を注ぐ形になり、どちらかがギブアップするまでの長期戦になります。
この方法は、親自身も冷静さを失い、後に強い自己嫌悪に陥ることもあり、推奨できるものではありませんでした。
癇癪は成長とともに変わる!

娘の癇癪は3歳から始まりましたが、小学2年生になった今では、まったく癇癪を起さなくなりました。
本人に聞いてみると「一年生の前で癇癪起したら恥ずかしいじゃん!」と言っていたので、癇癪はよくないことが理解できるほど成長したようです。
また、児童会館へ行くことを辞め、子供の自由時間が増えたことも良いきっかけになったんだと思います。
児童会館は良くも悪くも刺激が強い環境なので、無意識のうちにストレスになっていた可能性があります。
いまでは、癇癪を起しそうになると、自ら一呼吸をおいて話せるようになりました。
また、親である私も、出来るだけ急かさないように向き合うことを心掛けています。
癇癪の本当の原因を探る
様々な方法を試しては失敗を繰り返す中で、私は「そもそも、なぜ癇癪がこんなにひどいのだろう?」という根本的な疑問を突き詰めるようになりました。
癇癪の「本当の原因」を探る(わが家の場合)
私の娘の場合は、以下の要因が複合的に絡み合っていると感じました。
感情のコントロールが苦手
衝動的な感情の波を理性で抑える力が、まだ未熟でした。
特に、怒りや不満といったネガティブな感情が芽生えると、それを言葉で表現するよりも先に癇癪が出てしまう傾向がありました。
また、何か不満があると、冷静に言葉で話すよりも先に、叩いたりしてしまうことが多く感じました。
思い通りにならないイライラ
自分のルールや期待通りにいかないと、激しい不満を見せることがありました。
例えば、「おもちゃを自分の思っている場所に置きたい」「遊びを途中で中断させられる」といった些細なことでも、感情が爆発する引き金になっていました。
切り替えの苦手さ
遊びや活動の切り替えが苦手で、次の行動に移るまでに時間がかかり、それが癇癪に繋がることが多々ありました。
これが一番大きな要因になっている気がしました。なぜならお迎えに行ったときに癇癪を起していたので、「切り替え」が苦手なんだと感じたからです。
環境が癇癪に影響する?
意外と見落としがちなのが、環境が癇癪に与える影響です。
睡眠不足・疲労
体力が十分でないと、些細なことでもイライラしやすくなり、感情のコントロールが難しくなります。特に、学校や保育園で頑張った日や、遊びすぎて疲れている日は、普段なら我慢できることでも癇癪を起こしやすいかな?と感じました。
また、運動会や発表会などのイベントごとの前は、『癇癪を起しやすい』という噂も聞いたことがあります。
空腹
お腹が空いていると、大人でもイライラしますよね。子どもも同じで、血糖値が下がると感情が不安定になることがあります。
刺激の多さ
テレビやゲーム、人混みなど、視覚的・聴覚的な刺激が多すぎると、脳が疲弊し、癇癪に繋がりやすくなることも…。
親の心境・ストレス
親自身がストレスを抱えていたり、疲れていたりすると、子どもはそれを敏感に察知します。親のイライラが子どもに伝わり、癇癪を引き起こす悪循環になることもあります。
また、こちらが家事や仕事に追われている時に限って癇癪を発動することが多いと感じていました。
とくに、親が色々なことに追われていると「早くしなさい!」と言ってしまうことが多く、そのペースに合わせるのが、子どもにとっては大きなストレスに繋がっていたんだと思います。
癇癪を通して気づいたこと
正直、癇癪は親にとって非常に辛く、苦しいものです。私も何度も心が折れそうになりました。しかし、この4年間、娘の癇癪と真剣に向き合う中で、私たちにはかけがえのない変化がありました。
娘への理解
癇癪の裏にある「止められない」気持ちや、まだ未熟な感情コントロール能力を理解することで、娘への見方が変わりました。「ワガママ」や「甘え」ではなく「苦しんでいる」と考えるようになりました。
感情の言語化の練習
癇癪が落ち着いた後、娘と一緒に「あの時、どうしたかった?」「どんな気持ちだった?」と、言葉で表現する練習を繰り返しました。
親自身の変化
私自身も、癇癪に対して冷静に対応する練習になりました。
娘の感情の爆発に引きずられず、一歩引いて状況を見る、自分の感情をコントロールする力が身についたと感じています。
絆の強化
癇癪という嵐を共に乗り越えることで、親子間の信頼関係がより強固になったと信じています。娘が落ち着いた時に「ごめんね」「ありがとう」と言ってくれる時、これまでの苦労が報われるような温かい気持ちになります。
癇癪の時、親が心がける具体的なことは?
娘が癇癪を起しそうなときに、特に気を付けていることは以下です。
- 学校や習い事の多少の遅刻は良しとする(急かすと癇癪につながるため)
- 細かいことで口出ししない。「他の人に迷惑かけるから、叱らないとダメだ!」というレベルのこと以外は、肩の力を抜く。
- 叱るときも、初めは寄り添う言葉がけをする。また、必ず冷静な口調で伝える。
これだけでも、心に余裕ができるようです。
私は割となんでも、時間通りにこなさないと嫌でしたが、「癇癪を起すくらいなら、適度に肩の力を抜こう!」と考えるようになり、それがプラスの方向に繋がっているのを実感しています。
まとめ
娘との4年間の癇癪との戦いを通して、私が最も伝えたかったことは、以下の3つです。
- 癇癪は「わがまま」ではなく、子ども自身も苦しんでいる感情の爆発であること。
- 一般的な対処法(無視や対峙)が、必ずしもすべての親子に効果的とは限らないこと。
- 原因を理解し、親自身が肩の力を抜くことで、必ず状況は好転するということ。
癇癪は、親にとって本当に先の見えない長い闘いです。
私も、娘の癇癪に何度も心が折れそうになり、終わりが見えない日々が続くように感じていました。
しかし、娘自身の成長、そして私自身の「適度に手を抜き、完璧を目指さない」という意識の変化が、私たち親子の癇癪との向き合い方を大きく変えてくれました。
もし今、あなたが子どもの癇癪に苦しんでいるなら、どうか一人で抱え込まないでください。
今は辛い状態ですが、この経験が、あなたと子どもの絆を深め、共に成長するかけがえのない時間となることを信じています。
焦らず、自身の心の声にも耳を傾けながら、一歩ずつ癇癪を乗り越えましょう。この記事が、そのための小さなきっかけとなれば幸いです。