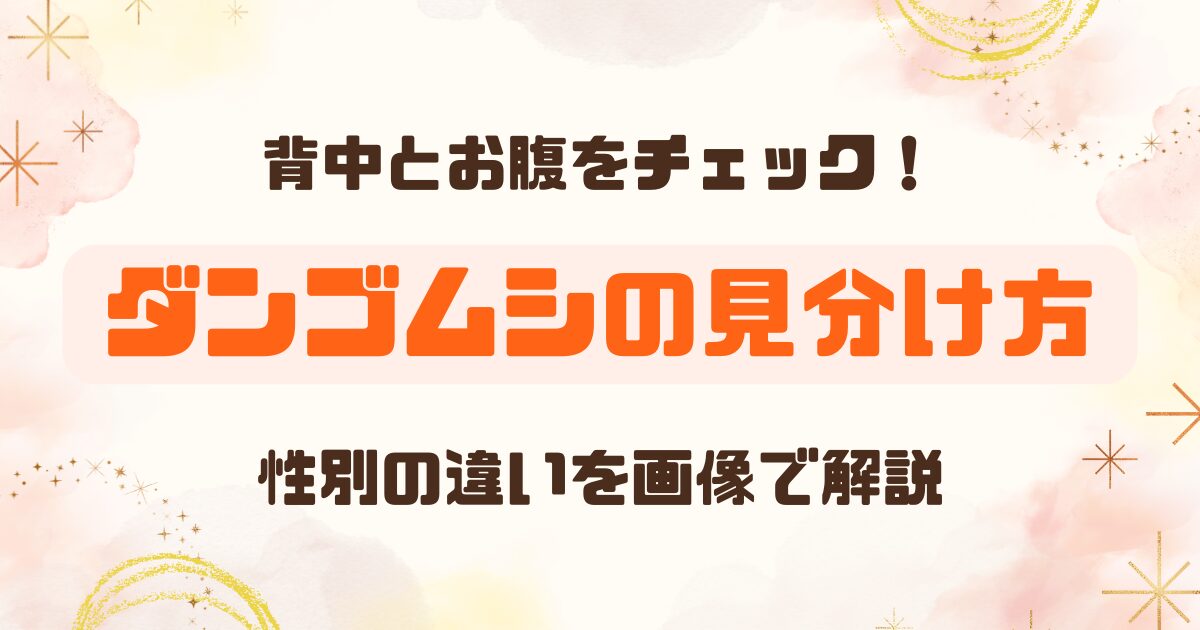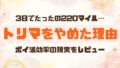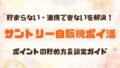子どもが突然ダンゴムシを捕まえてきて、困った経験はありませんか。
私自身、最初はどう入れ物を用意すればいいのかもわからず、とりあえずペットボトルに入れておいたことがあります。
でも調べてみると、身近なもので簡単に観察ケースを作れることや、模様の違いで楽しめる発見があることがわかりました。
この記事では、ダンゴムシを観察するときの工夫や性別の見分け方についてご紹介します。
ダンゴムシの模様でオス・メスが見分けられる!?
ダンゴムシをよく見ると、背中にうっすらと模様が浮かんでいることがあります。
とくに光の加減によって見えやすくなることもあり、子どもと一緒に観察すると発見があって楽しい瞬間です。
実際に検索すると「メスには黄色い模様があることが多い」と紹介されている情報もあり、性別を見分ける際の目安として知られています。
ご参考までに、私の子どもが捕獲したダンゴムシです。
背中に模様があるのが分かります。

一方こちらは、外で発見したダンゴムシです。黄色い模様はありません。

ただし成長段階や個体差によって必ずしも一致するわけではないので、正確に判断するにはお腹の構造も確認する必要があります。
お腹の構造でオス・メスを見分ける
模様だけでは確実に性別を判断できないため、正確に知りたいときはお腹を観察します。
オスは3本目と4本目の足の付け根に白っぽい突起があり、メスは突起がなく、卵を育てる「育児嚢(ふくじのう)」があります。
お腹の観察は無理に触らず、透明ケースに入れてそっと観察するのが安全です。
捕まえるときのちょっとしたポイント
子どもが夢中でダンゴムシを手づかみする姿はかわいいですが、できれば小さなスプーンやシャベルを使うと安心です。
ダンゴムシはとても小さい生き物なので、つぶしてしまわないためにも、そっとすくい上げるようにしましょう。
捕まえたあとは、落ち葉や土を一緒に入れると元気に観察できます。
ペットボトルで簡易観察ケースを作る
すぐに専用の観察ケースがなくても、家にあるペットボトルで簡易ケースを作れます。
1. 通気口を作る
キャップ部分にキリや千枚通しで小さな穴を数か所あけて、空気が通るようにします。
ライターで少し熱してから押し当てると穴があきやすいですが、火傷しないよう大人が管理してください。
2. 落ち葉や土を入れる
捕まえた場所の落ち葉や土を一緒に入れると、ダンゴムシも落ち着きます。湿らせたティッシュを少し入れると乾燥を防げます。
3. 明るすぎない場所に置く
直射日光は避けて、涼しくて暗めの場所に置くと元気に過ごせます。
観察するときの注意点
あくまで一時的な観察にとどめ、長期間飼うのは控えましょう。
ダンゴムシは落ち葉を分解する大切な生態系の一員なので、観察後は元の場所に返してあげることが大切です。
まとめ
ダンゴムシの背中の模様は、オスかメスかを予想する目安になりますが、個体差や種類によって必ずしも当てはまりません。正確に性別を知りたい場合はお腹の構造を観察して見分けましょう。
捕まえ方や観察ケースの工夫を知ることで、親子で楽しみながら観察できます。
丸まった姿や歩き方、模様の違いなどをスケッチして、自由研究に活かすのもおすすめですよ。
100均では「交換性転向反応」が検証できる「ダンゴムシ観察ケース」もありますので、活用すると面白い発見があるかもしれません。
詳しくは、こちらの記事で紹介しています。