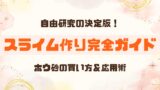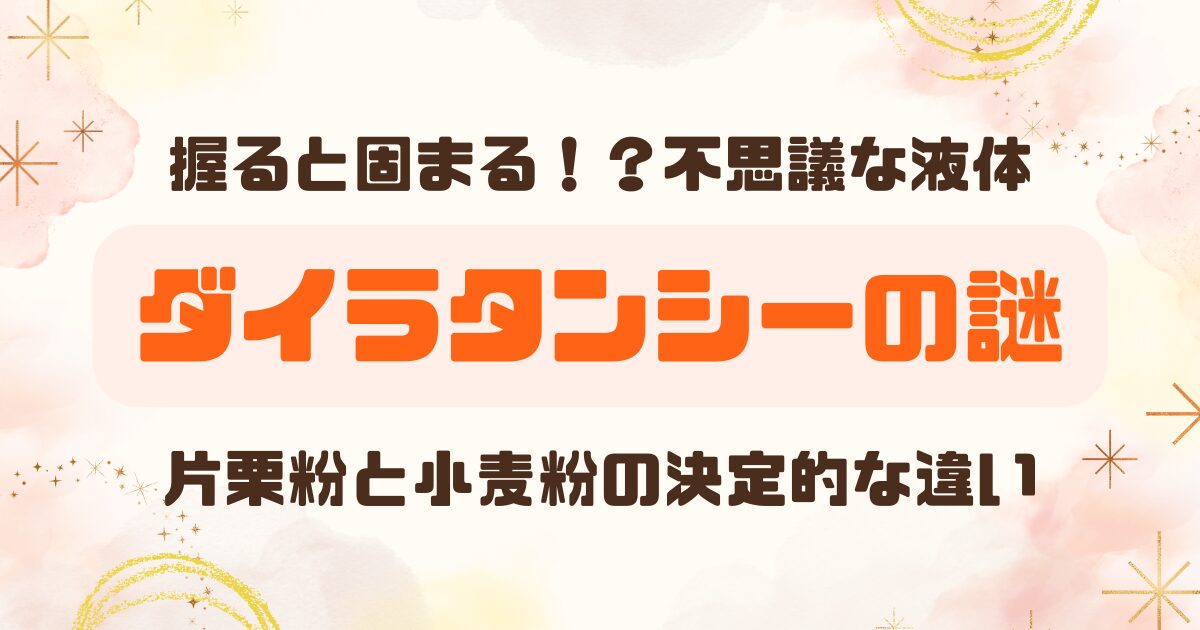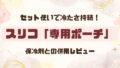私たちの周りには、多くの不思議な現象が潜んでいますが、その中でも「ダイラタンシー現象」はとても面白い現象のひとつです。
ダイラタンシー現象とは、片栗粉と水を混ぜた簡単な材料で作ることができ、触れた瞬間に液体と固体が入れ替わるかのような不思議な体験ができるんです。
「なぜ起こるのか?」という疑問を持てるので、小学生の自由研究としても人気があり、家で簡単に実験できる面白いテーマです。
ダイラタンシー現象のはなぜ起こるのか探ることで、日常に潜む化学の面白さや奥深さに子供も興味を持つと思いますよ。
この不思議な現象がどのようにして起こるのか、そして身近な所でどのように活用されているのかについて詳しく見ていきます。
ダイラタンシー現象とは?
ダイラタンシー現象とは、液体に特定の粉末を混ぜたものが、ゆっくり触ると液体のように流れ、一気に力を加えると固体のように硬くなる現象のことです。
例えば、片栗粉と水を混ぜたものを指でゆっくりかき混ぜるとドロドロの液体ですが、拳で叩いたり、強く握ったりするとカチカチに硬くなります。
この不思議な現象は、イギリスの物理学者オズボーン・レイノルズによって発見され、「レイノルズ現象」とも呼ばれることがあります。家庭にある材料で科学の面白さを体験できるため、理科の授業などでもよく使われています。
たまたま子供がYouTubeで見かけたらしく「面白そうだから作ってみたい!」と言ったので、作ることに!
家にあるもので出来て、子供にも安全なものしか使わないので、小学生の自由研究にオススメです。
※ちなみに、現象の名前を「ダイラタンシー現象」と呼ぶらしいのですが、この現象が起きてる液体(固体)の事を「ダイラタンシー」と呼んでいる人が多いそうなので、液体(固体)=ダイラタンシーとさせていただきます。
なぜこのような現象が起きる?原理を解説
ダイラタンシー現象の原理を簡単に解説します。
仕組みはとてもシンプルで、水の中にある粉の粒子が「力を加えると固まる」「力を緩めるとバラバラになる」という性質を持っているからです。
- 粒子が水に浮いた状態では液体のように振る舞う
力が加わっていないときは、粒子同士が自由に動けるため、ドロドロとした液体のように感じられます。 - 強い力を加えると粒子同士が密着し、固体のようになる
拳で叩いたり強く握ったりすると、粒子がぎゅっと押し付けられ、水が押し出されて粒子同士がぶつかり、全体が硬くなります。 - 力を緩めると粒子の密着がゆるみ、再び液体に戻る
力を取り除くと粒子の間に水が戻り、液体のように流れる状態に戻ります。
ダイラタンシーの材料
ダイラタンシーを作るのに必要なものは3点のみです。
- 片栗粉(コーンスターチでも可)
- 水
- ボウルや容器
家庭で簡単に手に入るものなので、実験を行う上で特に改まって用意するものはありません。

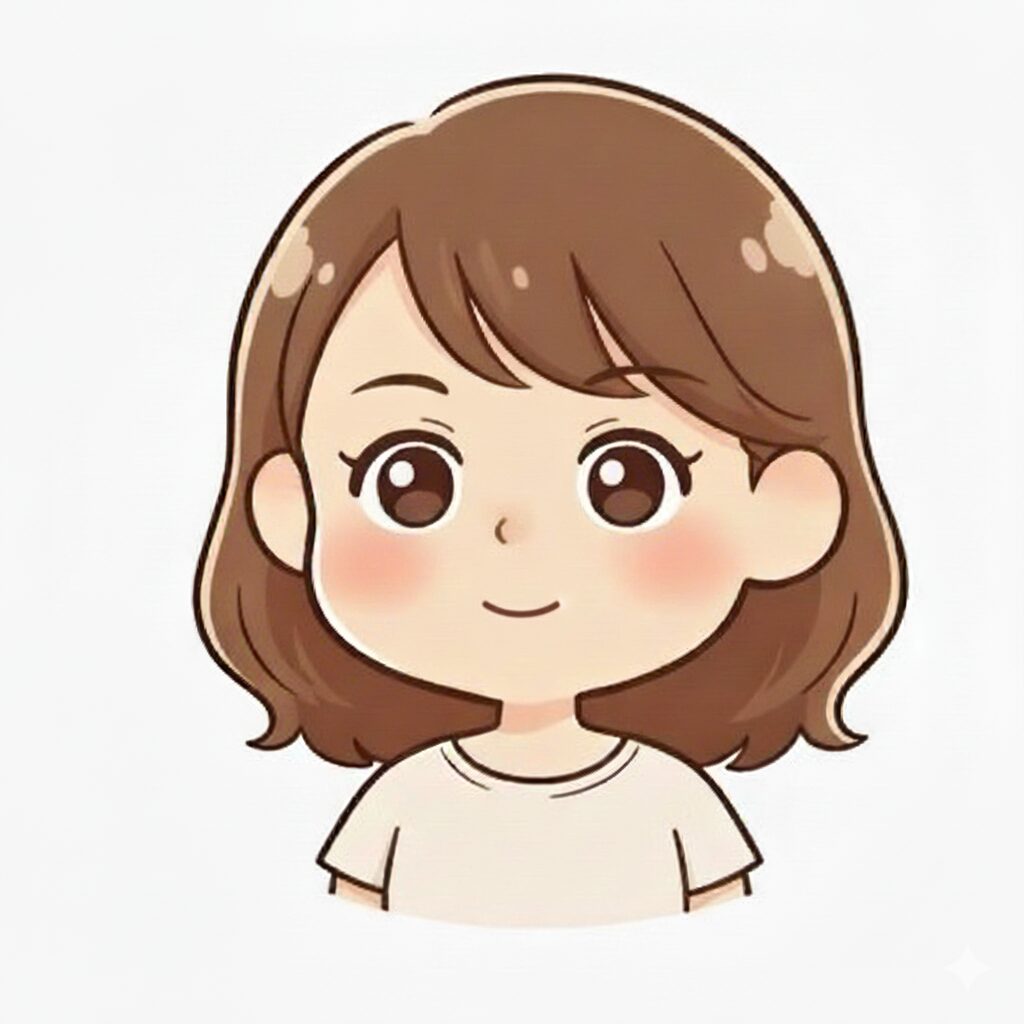
身近にあるもので簡単にできます。
ダイラタンシーの作り方
作り方も簡単です。
①ボウルに片栗粉と水を入れます。割合は「片栗粉:水=1:1」が目安ですが、硬さを調整しながら少しずつ混ぜるのがおすすめです。
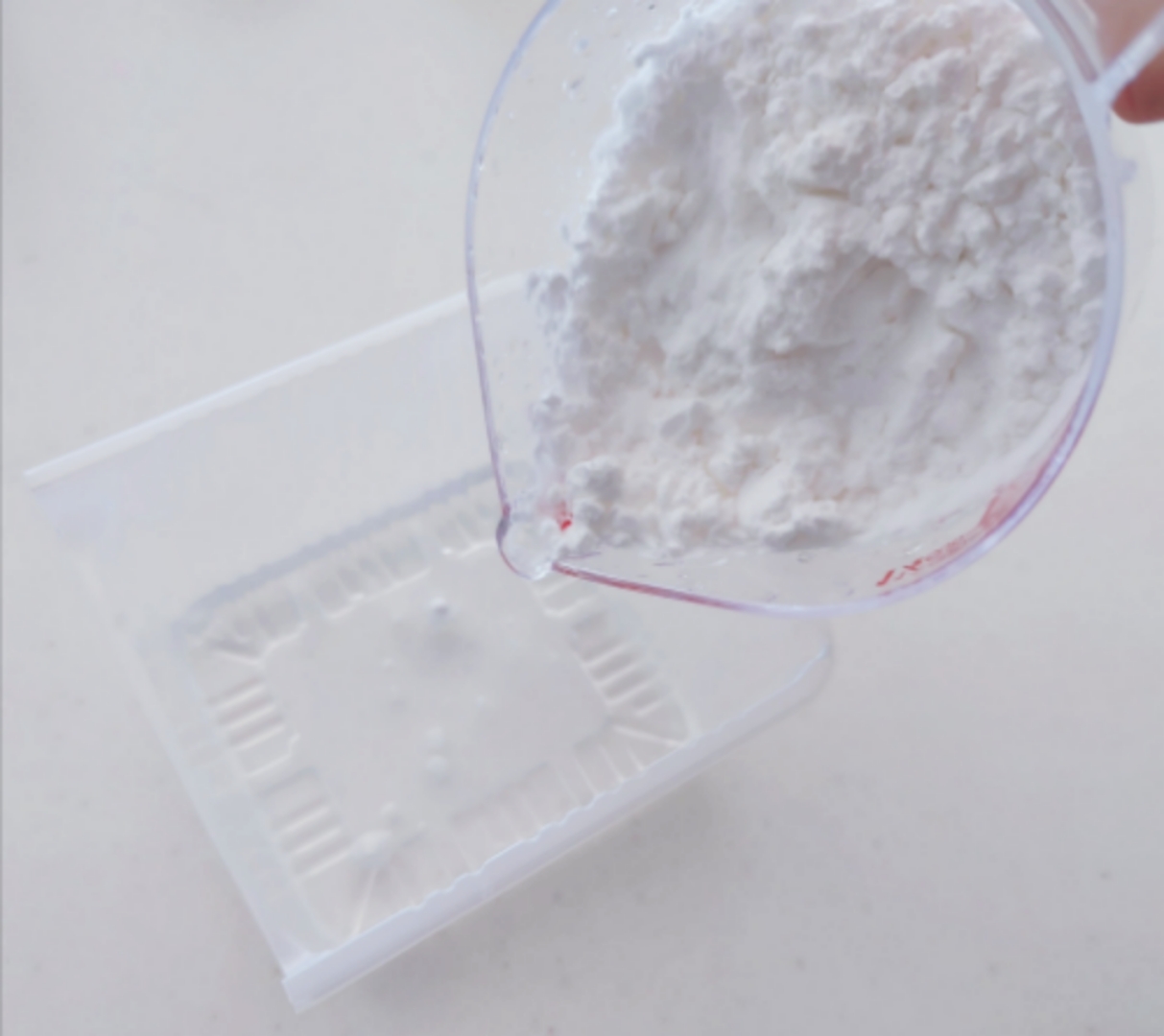
②あとは、ひたすら混ぜるだけ。手で混ぜるのが一番感触が分かりやすいですよ。

③混ぜた後、硬すぎると感じたら水を少し足し、柔らかすぎると感じたら片栗粉を少し足して調整します。
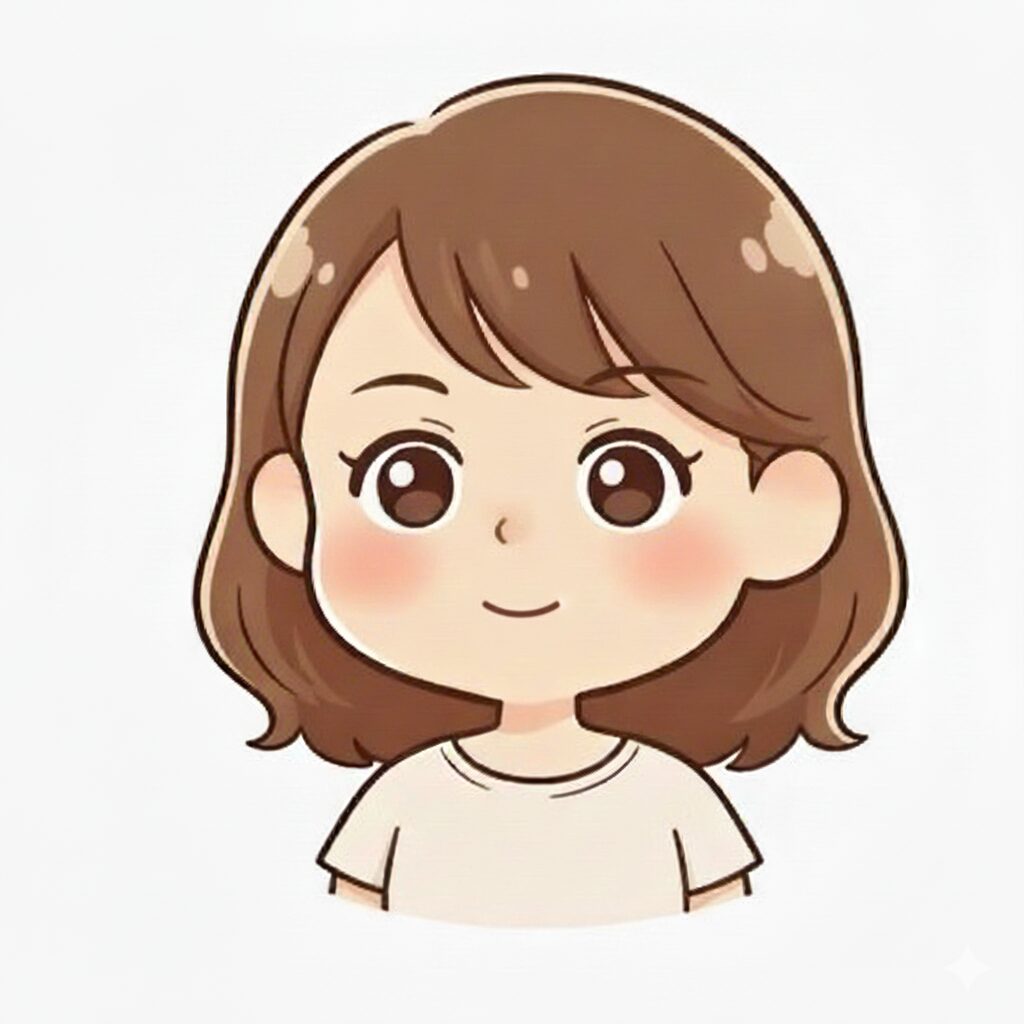
今回は硬すぎたので、少し水を足します!

これで完成です。

追加の水を入れ過ぎてしまって、かなり液体に近いダイラタンシーになりました。
かなり、液体に近いダイラタンシーですが、ギュッと握ると硬くなり、

離すと液体に変化します。

実際に触ると不思議な感覚です。



なんとも言えない面白い感覚!!
ちなみに、手を汚したくない!という方は、ビニール袋にダイラタンシーを入れると触り心地を楽しめますよ!

混ぜ合わせる際の比率は調整しながらやってみると、割合によっての変化も楽しめると思います。
大量に作って桶などに入れると、ダイラタンシーの上を走ることも出来るようです。
「走る=力が加わる=固くなる」のでダイラタンシーの上を走ることが出来ます。
ダイラタンシーは片栗粉以外でもできる?
ダイラタンシー現象は、片栗粉(水に溶かしたもの)でよく知られていますが、実は他の澱粉類でも同じ現象が見られます。
コーンスターチ(とうもろこし澱粉)やでんぷん粉を水に溶かしても、強い衝撃を与えると液体が一時的に固まるダイラタンシー現象が確認されています。
一方、小麦粉ではうまくできません。小麦粉には「グルテン」というタンパク質が含まれており、水と混ざると粘り気が強くなってしまいます。そのため、片栗粉やコーンスターチのようにサラサラした粒子が水に浮いた状態を作れず、ダイラタンシー現象が起こらないのです。
つまり、小麦粉は「粘る」性質が強いため、「固まる・戻る」という現象とは仕組みが違うのです。
身近なところで活躍するダイラタンシー現象
この不思議な現象は、実は私たちの身の回りにある様々なものに応用されています。
日常生活での例
- 泥だんご作り:少し湿った砂や泥を握りしめると固まりますが、握るのをやめるとサラサラになるのも、同じ原理が働いています。
- パン生地をこねるとき:パン生地も、優しくこねると柔らかくまとまりますが、強く叩きつけると硬く締まります。これもダイラタンシー現象の一種です。
驚きの応用例
製品にも応用されています。
- 防弾チョッキ: 特殊な繊維にダイラタンシー流体を染み込ませた防弾チョッキがあります。普段は柔らかく動きやすいですが、高速の弾丸が当たった瞬間に硬くなり、衝撃を吸収する仕組みです。
- 砂浜: 石川県の千里浜(ちりはま)は、砂がダイラタンシー現象を起こすことで知られています。海水を含んだ砂が力を加えると硬くなるため、車で砂浜を走行できるのです。
捨てる時の注意点
ダイラタンシーは、絶対にそのまま排水口に流してはいけません。時間が経つと水分が蒸発して固まり、排水管を詰まらせる原因になります。
処分する際は、新聞紙などに広げて水分を飛ばし、完全に固まってから燃えるゴミとして捨てるのがおすすめです。自治体によってルールが異なる場合もあるので、念のため確認しておきましょう。
また、片栗粉と水でできているため日持ちはしません。雑菌が繁殖する可能性があるので、遊んだ後はその日のうちに処分するのが安心です。
ダイラタンシーを誤って排水口に流してしまったら?
ダイラタンシー(片栗粉+水などの流体)は、排水に流すと詰まりの原因になることがあります。力が加わると固まる性質があるため、配管の中で固まりやすく、乾燥するとでんぷん質の塊になってしまうからです。
もし間違って流してしまったら、できるだけ早く大量の水で流すのが基本です。
40℃程度のぬるま湯に中性洗剤を混ぜて流すと、でんぷんが流れやすくなります。時間が経ってしまった場合や流れが悪い場合は、市販のパイプクリーナーを使うか、排水トラブル業者に相談しましょう。
ダイラタンシーを作った後は、新聞紙やキッチンペーパーに吸わせて固め、燃えるゴミとして捨てるのが安全です。
まとめ
ダイラタンシー現象は、身近な材料で「液体と固体が入れ替わる」という不思議な体験ができる魅力的な実験です。
強い力が加わると粒子同士が密着して固体になり、力を緩めると再びバラバラになって液体に戻るという、シンプルな原理で成り立っています。
子どもと一緒に「どうしてだろう?」と疑問を持つことから、科学への興味が広がるきっかけになります。
自由研究のテーマに迷っている方は、今年の夏にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ダイラタンシーだけでなく、よく伸びるスライムの作り方も紹介していますので、参考にしてください。