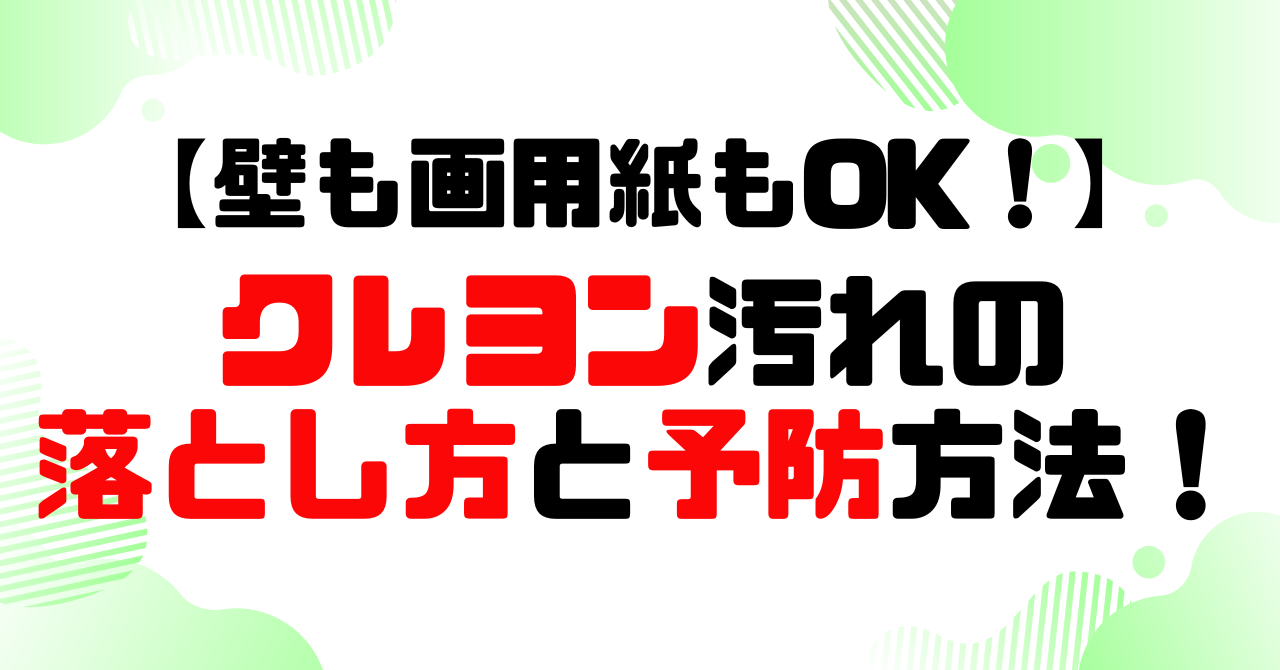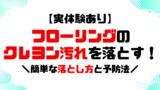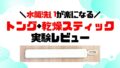あっ!また壁にクレヨンで落書きされてる…!」「描き終わった画用紙にも、うっかり汚れが…」。
子どもとのお絵描きタイムは楽しいけれど、クレヨンの汚れはつきものですよね。
わざとではないと分かっていても、目につくとため息が出ます。
今回は、お絵描き中の画用紙についた汚れから、いつの間にか増えている壁紙の汚れまで、それぞれの効果的な落とし方を調査しました。
さらに大切な壁への落書きを「未然に防ぐための予防策」も紹介します。
ぜひ最後まで読んで、ご自宅の壁と画用紙をクレヨン汚れから守りましょう!
画用紙についたクレヨンを消す2つの方法
画用紙のクレヨン汚れは、クレヨンの「油分」を溶かすか、「ロウ」を削り取ることで対応できます。
状況に合わせて試してみてください。
1. 油分を溶かして拭き取る方法
クレヨンは油分でできているため、同じく油分を含むもので溶かすことができます。
用意するもの
- サラダ油 または ハンドクリーム
- 綿棒、またはティッシュ
- 乾いたティッシュ
方法
- 綿棒やティッシュの先に、ごく少量のサラダ油やハンドクリームを付けます。
- クレヨン汚れの部分を、優しくなでるようにして油をなじませます。
- クレヨンが少し溶けてきたら、すぐに乾いたティッシュを押し当てて、油分と汚れを吸い取ります。
- ベタつきが気になる場合は、この工程を数回繰り返してください。
2. 表面を削り取る方法
クレヨンのロウ成分を、物理的に剥がし取る方法です。
用意するもの
- カッターナイフの刃、または定規の角
方法
- 刃や定規を画用紙に対し垂直に立てます。
- クレヨンが乗っている部分の表面を、紙を傷つけないように優しく、少しずつ削り取ります。
- 削り取ったロウを払い落とします。
この方法は、薄く描かれた汚れや、油分を付けたくない場合に適しています。ただし、強くやりすぎると紙が破れるので注意してください。
壁紙のクレヨン汚れを落とすのに必要な物は?
壁紙のクレヨン汚れを落とす方法として、主に以下の4つが効果的と言われています。
- クレンジングオイル
- アルカリ洗剤(台所用など)
- 歯みがき粉
- 牛乳
クレヨンは油性のため、クレンジングオイルや台所用のアルカリ洗剤が効果的です。
歯みがき粉は研磨剤が含まれているので、汚れを剥がして落としてくれます。
意外なのは牛乳。牛乳に含まれている「カゼイン」が汚れを包み込んで落ちやすくしてくれるそうです。
実践!壁紙のクレヨン汚れ、本当に落ちる?【基本の検証】
実際に壁紙にクレヨン汚れをつけて落ちるか検証してみます。
今回使う壁紙は一般的なボコボコした壁紙。色はもちろん白です。
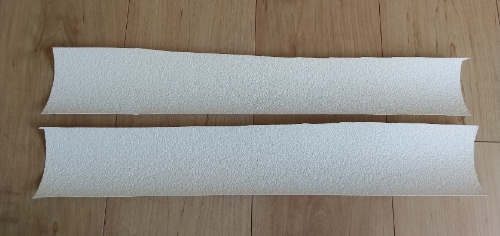
この壁紙に赤と青のクレヨン、2色で描いちゃいました。
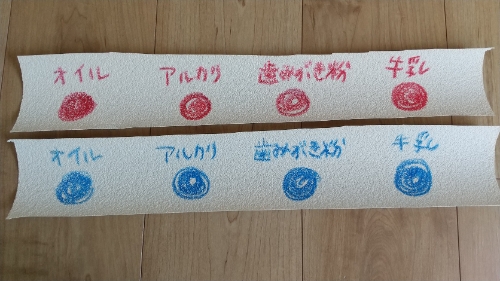
本当に落ちるか検証始めます!
検証1:クレンジングオイル
用意する物
- クレンジングオイル
- ティッシュや雑巾など
- 歯ブラシ
ティッシュにクレンジングオイルを含ませて、汚れを擦ります。
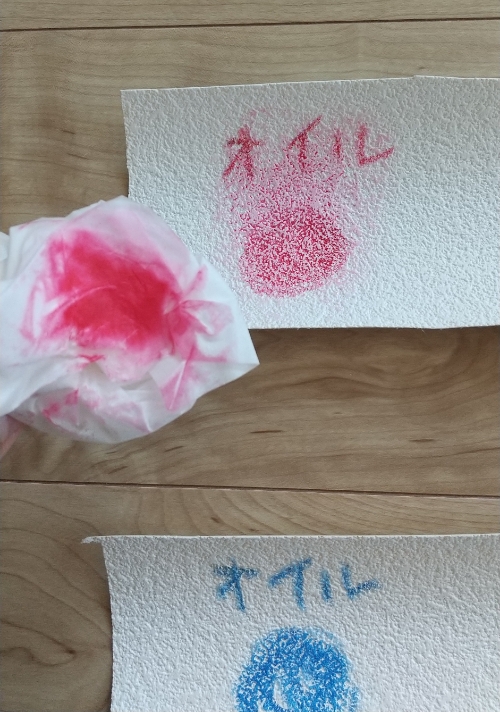
軽く擦るだけで、結構汚れがとれました。
3~4回位繰り返すと、
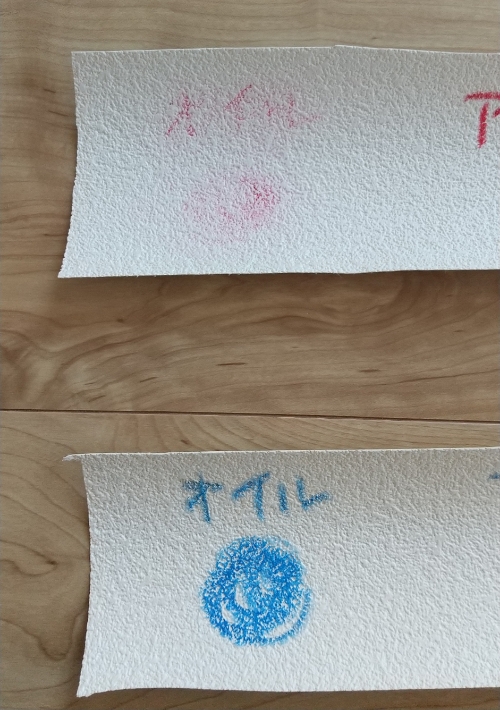
だいぶ薄くなりました。
後は、溝に入り込んだ汚れを歯ブラシで擦ります。
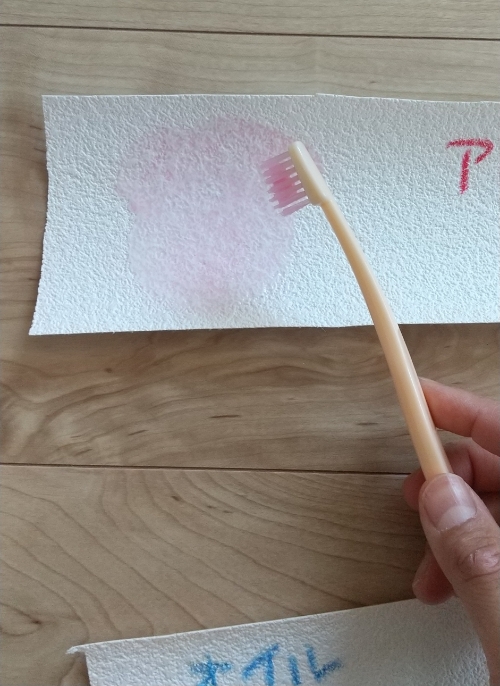
後はウェットティッシュなどで拭くと、
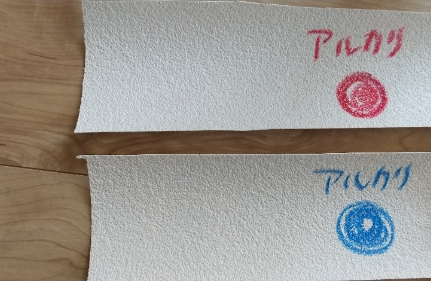
ここまで、綺麗になりました。
赤も青もどちらも、殆ど目立たなくなりました。
検証2:アルカリ洗剤
用意する物
- アルカリ洗剤
- ティッシュや雑巾など
- 歯ブラシ
ティッシュなどにアルカリ洗剤を付けて、汚れを擦ります。
※写真では、直接かけてしまいましたが、出来ればティッシュや雑巾に含ませた方がいいです。
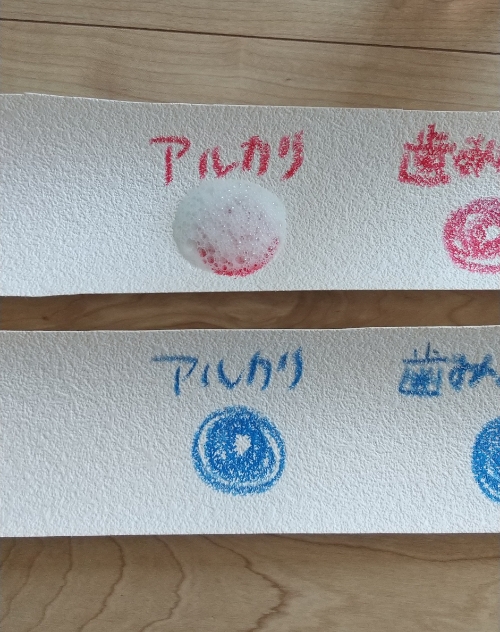
クレンジングオイルと同じように、
3~4回ティッシュで擦り、その後歯ブラシでさらに擦ると、
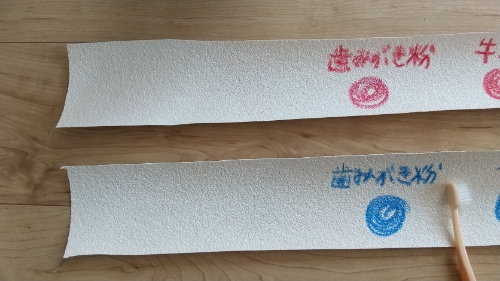
どちらの色も、殆ど分からなくなりました。
検証3:歯みがき粉
用意する物
- 歯みがき粉
- ティッシュや雑巾など
- 歯ブラシ
歯みがき粉をつけて、歯ブラシで擦っていきます。
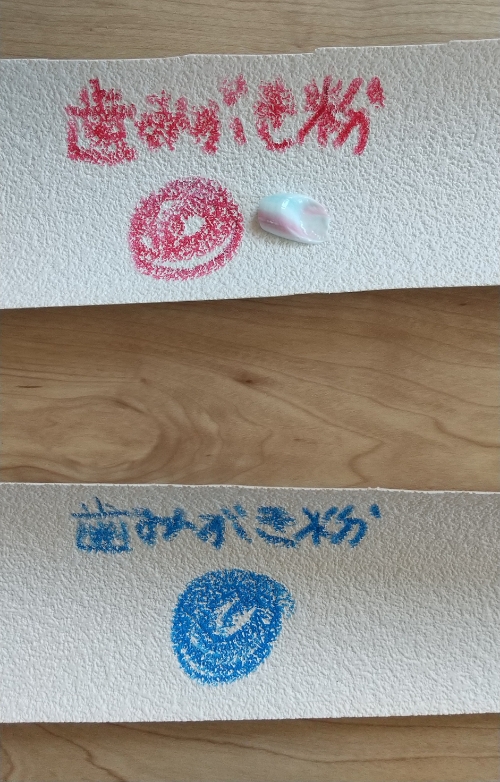
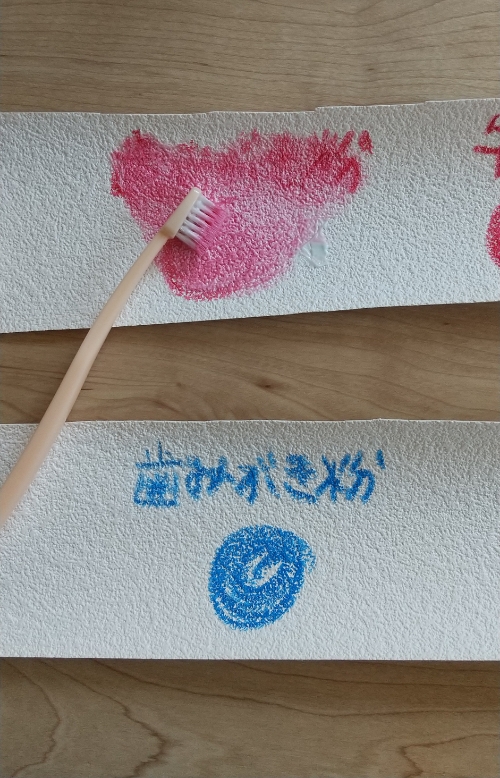
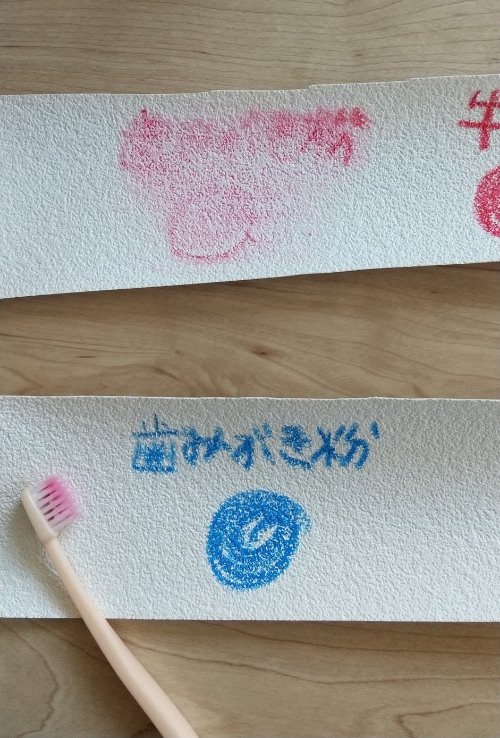
何回か擦りましたが、青が少し残ってしまいました。
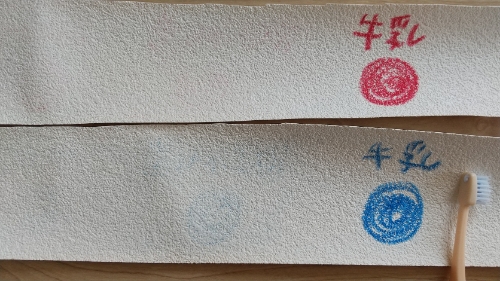
検証4:牛乳
用意する物
- 牛乳
- ティッシュか雑巾など
- 歯ブラシ
ティッシュや雑巾などに、牛乳を染み込ませます。
そのティッシュで汚れを擦っていきます。
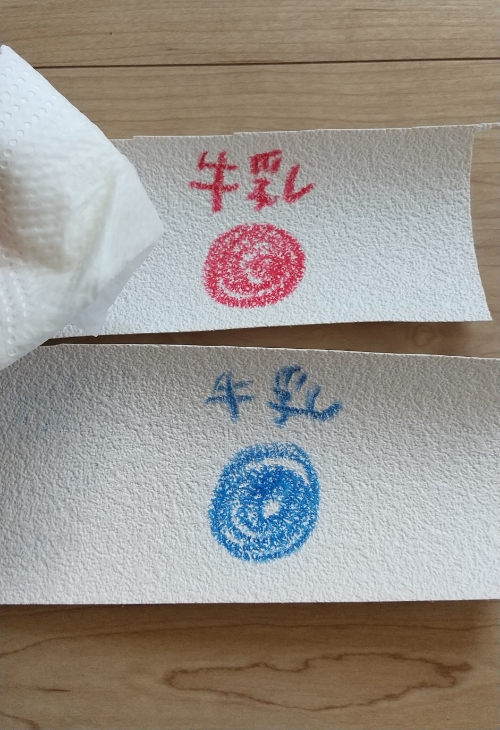

汚れが薄くなったところで、歯ブラシに牛乳を含ませて、さらに擦ります。
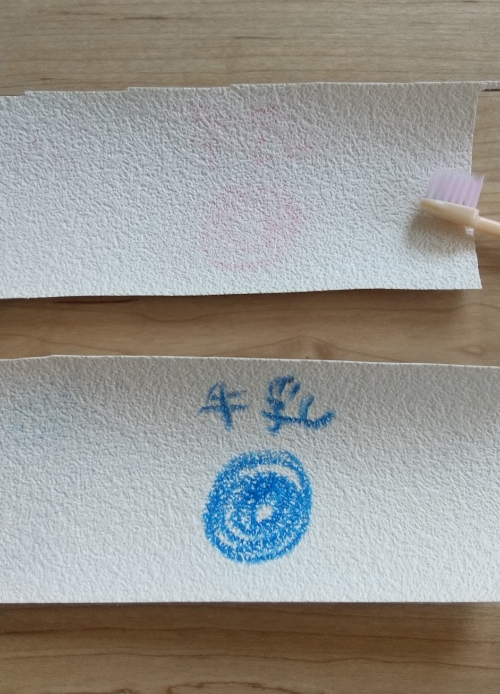
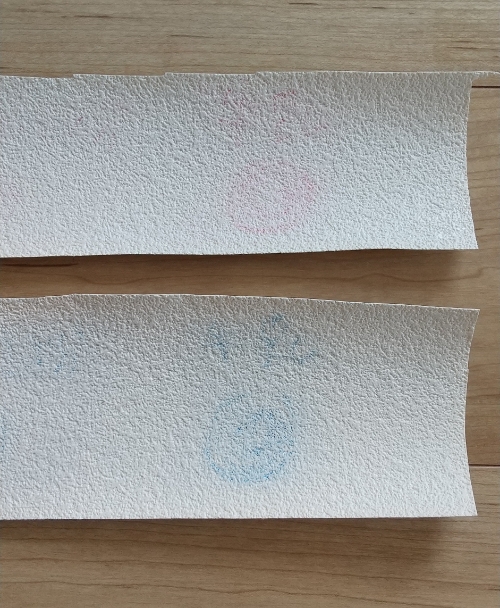
結構こすりましたが、うっすら残りました。
壁紙のクレヨン汚れ落とし、一番効果的なのは?【基本の検証結果】
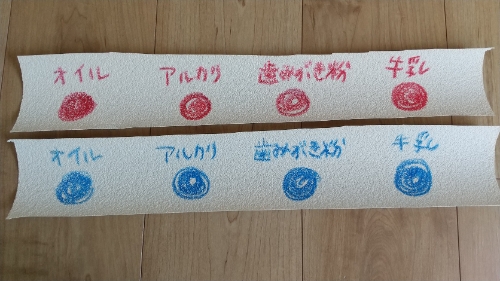

4パターンの汚れの落とし方を試してみましたが、汚れが綺麗に落ちたのは、
1番→クレンジングオイル、アルカリ洗剤
2番→歯磨き粉
3番→牛乳
の順位でした。
匂いなどを含めると、一番扱いやすいのは、クレンジングオイルかな?と、個人的に思います。
「アルカリ洗剤」は、ゴム手などをはめないと手荒れしやすいし、「歯みがき粉」「牛乳」は匂いが気になるので、クレンジングオイルが一番使いやすいと感じました。
そして今回、汚れ落としをしてわかったのですが、壁紙の裏側に結構水分が染み込んでいたこと。

その為、書いてしまってから消すことを考えるのではなく、かかれない様にどう予防するかが大事だと改めて感じました。
【徹底予防】クレヨン汚れから壁を守る!今日からできること
クレヨン汚れを落とすのは手間がかかるので、できることなら事前に防ぎたいですよね。
ここでは、壁へのクレヨン汚れを徹底的に防ぐための方法を、さらに掘り下げてご紹介します。
水で落とせるクレヨンを「約束」にする
- 万が一壁に描かれてしまっても、ダメージを最小限に抑えられます。
- 購入時に「これは特別なクレヨンで、もし間違って壁に描いても水で拭けば落ちるんだよ。でも、基本的には紙に描こうね」と優しく、しかししっかり約束しましょう。
お絵描きスペースを「楽しい秘密基地」にする
- 壁の一面に大きな模造紙や画用紙を貼ったり、ホワイトボードを設置したりして、子どもが思い切りお絵描きできる専用スペースを作りましょう。
- このスペースに子ども用の机や椅子、お気に入りの画材をまとめて収納できるワゴンなどを置けば、「ここは私の特別な場所」という意識が生まれます。
この商品は、高さ調整も可能で、机にもなります。また折りたたむことも可能なので、子供に使わせるのにぴったりです。
「描いても良い場所」を視覚的にアピールする
- 単に「壁に描いちゃダメ!」と口頭で注意するだけでなく、お絵描きスペースの周りをマスキングテープなどで囲み、「ここなら自由に描いてOKだよ」と視覚的に示してあげましょう。
- 子どもが描いた絵をたくさん飾るスペースを作るのも効果的です。

我が家は、業務用の大きなホワイトボードを設置しています。
ただし、小さな子だと倒さないように気を付けてください。
邪魔にはなりますが、お絵描き以外にも、メモとしても使用できるので意外と活用できます。
もし描いてしまった時の「お約束」を優しく確認する
- どんなに気をつけていても、うっかり描いてしまうこともあります。
そんな時は頭ごなしに叱らず、一緒に拭き取ることを習慣にしましょう。
「怒られるのが怖いから隠す」という最悪なパターンを防げます。
親の意識改革も大切
- 子どもの落書きは、成長の過程でよくあることです。「今だけ」と割り切って、ある程度は大目に見る心の余裕を持つことも、子育てを楽しむ上で大切です。
もし、汚してしまったら、汚れもありますよ。
まとめ
壁のクレヨン汚れは、適切な落とし方を知っておくことも大切ですが、何よりも日頃からの予防が重要です。
水で落とせるクレヨンを活用したり、楽しいお絵描きスペースを作ったり、描いても良い場所を明確に伝えたりすることで、壁への落書きを大幅に減らすことができます。
今回ご紹介した予防策を参考に、子どもとの創造的な時間を安心して見守りながら、クレヨン汚れのない快適な空間を保ってくださいね!
\クレヨンのフローリング汚れはこちらの記事で/