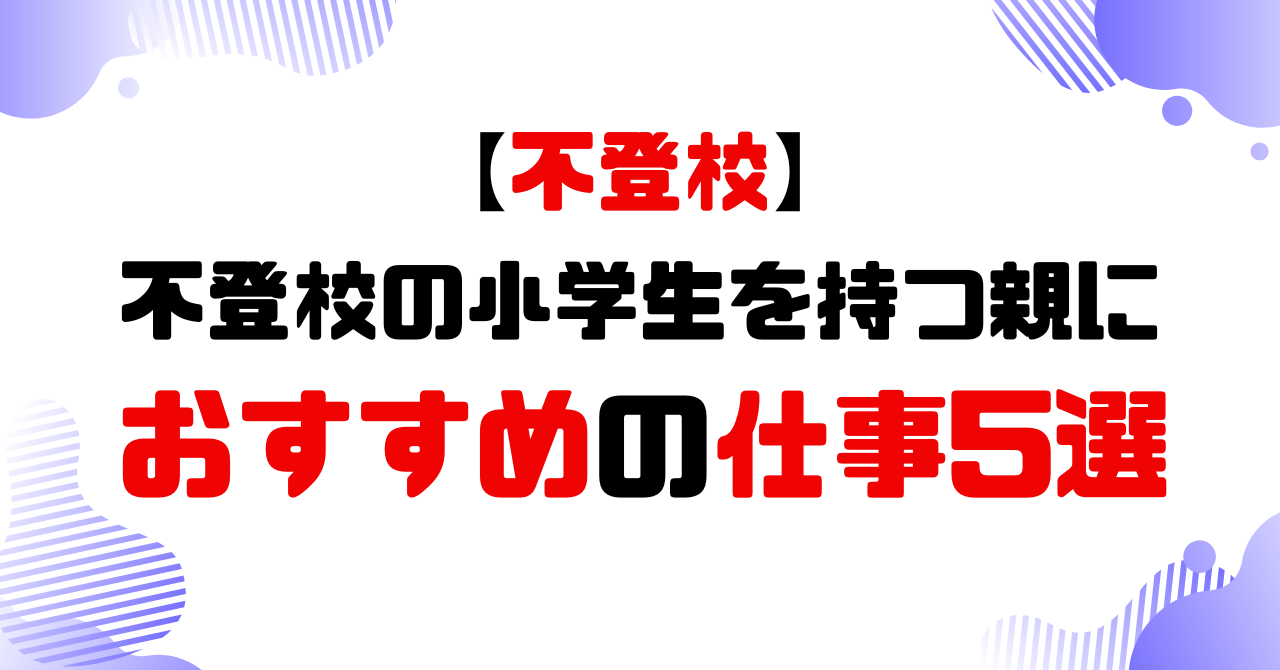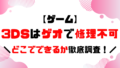不登校の小学生を抱える親にとって、「働きたいけれど、子どもに十分寄り添えないのでは」という悩みは尽きません。
私の息子も低学年の頃から学校に行けず、朝からふさぎ込む日もありました。
情緒が不安定なときは外に飛び出さないか心配で、普通の会社員として働くのは難しかったです。
そんな経験から、子どものそばで働ける在宅ワーク・内職・ブログでの収益化という方法を見つけました。
家にいながら働く安心感と、少しずつ生まれる心の余裕を、私の体験談と具体例を交えて紹介します。
不登校児を持つ親におすすめの働き方5選
ここからは具体的な働き方をご紹介します。
1. 在宅ワーク(ウェブライター・データ入力・簡単デザイン)
在宅ワークは、「子どもの急な変化にすぐ対応できる」点で不登校の親に最適です。
しかし、未経験からはじめるとなると、独学での勉強は必須です。
自分で学ぶのが難しいと感じる場合は、ハローワークの職業訓練や民間講座を事前に受けると仕事を探しやすいかもしれません。
- メリット
- 通勤不要で、時間の融通が利く
- 子どもの様子を見ながら作業できる
- デメリット
- 案件によって報酬はまちまちで、最初はほとんど収入にならないことも
- 信頼できるクライアント探しに時間がかかる
- 体験談
私も最初はデータ入力をしてみましたが、ほとんど収入にならないこともありました。文字数や案件によって大きく差があるので、最初は経験を積むことが大切です。
2. 内職(裁縫・ネットショップ出品作業など)
こちらも在宅なので、子どもの様子を見ながら自分のペースで作業することができます。求人情報サイトなどに掲載されていることがあります。
- メリット
- 子どものそばで作業できる
- 集中作業で気分転換になる
- デメリット
- 作業スペースの確保が必要
- 報酬は低めなことが多く、効率化が重要
- 体験談
内職は、少しの時間で作業できる反面、思ったより労働した時間に対して収入が少なく感じることもありました。納期を守ることが信頼につながります。
3. パート(短時間・シフト融通型)
パートだと在宅にはなりませんが、主婦が多い職場だと皆さんお互い様で、融通が利くケースも多くあります。
- メリット
- 社会的つながりが持てる
- 急な休みにも対応しやすい
- デメリット
- 外での勤務なので低学年の子どもを留守番させる必要がある
- シフト融通の限界を面接時に確認することが重要
- 体験談
「不登校児がいる」と伝えることで理解を得られると思います。また、面接の際に伝えておくことも重要です。
4. 専業主婦+副収入(不用品販売・ブログ・SNS収益)
大きな収入源にするには、時間と努力が必要ですが、お小遣い程度であれば、こちらの仕事が行いやすいでしょう。もちろん運用次第では、本業並みに稼げる可能性もあります。
- メリット
- 家にいながら少しずつ収入を得られる
- 初期投資ほぼゼロで長期的に活用可能
- デメリット
- 継続が必要で、すぐには結果が出にくい
- 販売や投稿の手間を工夫することがポイント
- 体験談
私はメルカリで不用品販売を始めました。最初は大きな収入にはなりませんでしたが、少しずつ慣れることで家計の助けになりました。しかし、写真の撮り方や商品説明、寸法計測など意外と沢山作業があります。
5. ハンドメイド・クラフト販売(アクセサリー・雑貨)
こちらも上記に同じく、すぐに大きな収入を得るのは難しいかもしれません。趣味で作ったことがある人ならば、スムーズに収益化できるかもしれません。
- メリット
- 子どものそばで作業できる
- 好きな作品を通じて自己肯定感が上がる
- デメリット
- 梱包・発送・集客など手間がかかる
- 収益が安定しにくいので「趣味+α」と割り切る
ブログで収益化するメリット
紹介した仕事はほとんど経験してきましたが、私が不登校児を抱えながら、ずっと続けている唯一の仕事が「ブログ」です。
なぜなら隙間時間で作業でき、分からないことなどはYouTubeやAIで解決できます。また、ブログは収益だけでなく、不登校で生じる親のストレスをアウトプットできる場でもあります。
そして、身近な商品などのレビューで記事をかけるので、あまりストレスなく継続することができます。
- ポートフォリオとして活用可能
- PVや広告掲載で少しずつ収益につながる
- スマホ1つで場所を選ばず作業可能
- 同じ悩みを持つ親との交流や感謝コメントで孤独感が軽減
ブログの収益化とは?
「ブログでどうやって収益が出るのか分からない…」という方もいるでしょう。
ブログを収益化するには、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)に登録することで、企業と私たちを繋ぎ、ブログに広告を掲載できるようになります。
なかでも、オススメのASPは「A8.net」です。
登録すると、「ブログの開設手順から収益化するまでの流れ」の解説を見ることができるので初心者にオススメです。
とても分かりやすいので、「何も分からない」という方は、一番初めに登録することを推奨します。
- 無料登録で年会費なし。
- 初心者でも安心: ブログ開設から広告掲載までの手順を、図解で分かりやすく解説してくれます。
- 成果報酬型で、子どもがそばにいても、自分のペースで収益化を目指せます。
\A8netへの登録はこちらから/
💡ブログ以外にも、在宅で安定して働きたい方へ
自宅で電話をかけるお仕事「コールシェア」も人気です。
「子どもの体調に合わせて休める」「平日2〜3時間だけ働ける」など、不登校の子を持つ親にも働きやすい環境が整っています。
扶養内でもOKで、初月から月4〜6万円ほど稼ぐ方もいます。
こちらも登録も無料なので、どんなお仕事があるか見るだけでも参考になりますよ。
\コールシェアの無料登録はこちら/
家庭での役割分担と居場所作り
- 話を否定せず最後まで聞く
- 共通の趣味を楽しむ(ゲーム・料理など)
- 日中の生活リズムを整える(昼夜逆転防止、規則正しい生活)
家庭全体で協力し、親の仕事が家庭の安心感に繋がっていることを伝えることが大切です。
まとめ
- 在宅ワーク・内職・ブログなど、子どもの状態に合わせて柔軟に働ける仕事が最適
- パートや副収入も組み合わせると、経済的・精神的余裕が増える
- ブログは収益だけでなく、ポートフォリオ・学び・ストレスのアウトプットとしても活用可能
\無料登録してブログ収益化を始める/
サイトに広告を掲載してお小遣いが稼げる!【A8.net】登録はこちら↓